チャイルド・オブ・ゴッド【コーマック・マッカーシー】
チャイルド・オブ・ゴッド
| 書籍名 | チャイルド・オブ・ゴッド |
|---|---|
| 著者名 | コーマック・マッカーシー |
| 出版社 | 早川書房(240p) |
| 発刊日 | 2013.07.15 |
| 希望小売価格 | 2,100円 |
| 書評日 | 2013.11.10 |
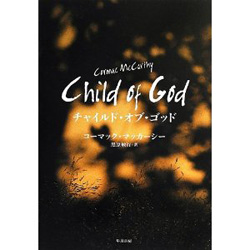
『チャイルド・オブ・ゴッド』はアメリカ東南部の山村で7人の男女を殺したシリアル・キラーを主人公にした小説だ。でも、この男がなぜ「チャイルド・オブ・ゴッド(神の子)」なのか。
主人公、レスター・バラードはアパラチア山脈の麓に住み、「ヒルビリー(hillbilly)」と呼ばれる白人貧困層に属している。ふつうヒルビリーといえばアメリカ南部やアパラチアで生まれたカントリー・ミュージックのことだけど、もともとこの地域のプア・ホワイトを指す蔑称だったのが、レコード業界で彼らの音楽を指す言葉として使われたことから音楽用語として定着した。ちなみにロカビリー(rockabilly)という言葉も「ロックンロール」+「ヒルビリー」から生まれている。
このおぞましくも美しい小説を読んだ後で、小説の背景を知りたいと思って少し調べてみた。でも音楽ではなく本来のヒルビリーについて、日本語で紹介されたものはごく少ない(国会図書館の蔵書を検索しても音楽以外は一件もヒットしない)。ヒルビリーとはもともと19世紀にアパラチア山脈の貧しい土地に入植したアイルランド移民を指す(wikipedia)。在米の映画評論家・町山智弘は彼らについて、「移民当時の経済レベルのまま生活する白人たちで、いわば『白人の土人』である」とブログに書いている。
考えてみたらここ数年、ヒルビリーや彼らが住む地域を舞台にした犯罪映画を何本か見ていることに気づいた。そのひとつが『ウィンターズ・ボーン』で、アパラチアの西、ミズーリ州オザーク高原を舞台にした映画。この高地に住む白人貧困層はアパラチアから移動した人たちなのでやはりヒルビリーと呼ばれる。住民全員がケシ栽培とドラッグ製造にかかわる村で、父親が姿を消した後、残された少女が精神を病む母と幼い弟妹の面倒をみることになる。開拓時代と変わらぬ小屋で、隣家から野菜を分けてもらい、シカやリスを獲って生活する光景に胸を衝かれた。『チャイルド・オブ・ゴッド』でも主人公のバラードは栗鼠(リス)を撃って食料にしている。
もう一本は『欲望のバージニア』。アパラチア山麓の村で密造酒をつくる3兄弟と取締官が対決する話だった。時代設定は禁酒法時代になっている。禁酒法廃止以後も今にいたるまで酒は免許・許可制になっていて、『チャイルド・オブ・ゴッド』でも密造酒をつくって物々交換でバラードにウィスキーを売る男が登場する。
南部を舞台にしたシリアル・キラーということでは『キリング・フィールズ』があった。現実に起こった事件を基にした映画。テキサス東部の湿地帯で40人近い少女が行方不明になり、未だに解決されていない。『チャイルド・オブ・ゴッド』も、訳者解説によると実際にあった事件を素材にしているという。この小説が発表され評判になったのは1973年と40年も前のことで、この種の題材としてはずいぶん早い時期のものだろう。『冷血』とともに、その後の理由なき殺人やシリアル・キラーを題材にした多くの映画や小説がイマジネーションをふくらませる源になったかもしれない。
小説に戻ろう。『チャイルド・オブ・ゴッド』は現実の事件を素材にしているといっても、『冷血』みたいなノンフィクション・ノベルではない。作者のコーマック・マッカーシーはテネシー育ち、ヒルビリーの世界を身近で見ていたらしい。でも作者が借りたのはおそらく事件の枠組みだけで、中身はひたすらマッカーシーの想像力によってのみ紡ぎだされていると思う。
主人公バラードは27歳の小柄な男。父親は自殺し、母は駆け落ちした。定職はなく、それだけが恃みなのか、腕自慢のライフルを手から離すことはない。税の滞納かなにかで競売にかけられ土地と家を失ったバラードは、森の廃屋に隠れ棲む。食料を盗み、リスを撃って食べる。雪の山中で事故死した男女の車を見つけ、女の死体を廃屋に運び込んで屍姦する。死体を天井裏に隠し、町で赤いワンピースと下着を買ってきて女に着せてみる。バラードは殺した女が着ていた服を身につけ口紅を差して森を歩きまわる。廃屋が火事で燃え落ち、バラードは山中の洞窟に隠れるのだが、そこではバラードが殺した男女の死体がミイラ化している……。
ストーリーを抜きだせばそういうことになるのだが、素晴らしいのはその描写だ。バラードの内面や心理は、ヘミングウェイやハメットのハードボイルドのようにまったく語られない。バラードと村人たちとの会話、バラードの行動、そしてアパラチア山中の自然描写が、数ページから十数ページの断章として積み重ねられる。まるで映画を見ているみたい。
例えばバラードが遠い山の斜面で繰り広げられる猪猟を見ている場面。
「猪は川を渡りたがらなかった。渡りはじめたときにはもう遅かった。…後ろでは犬たちがヒステリックに山の斜面に駆けおり周囲に雪を弾けさせる。川に入ると焼け石のように湯気をあげ対岸の木立から出てきて平原を駆けだしたときには白い雲のような湯気に身体をつつまれていた。
……
バラードはこのバレエを踊る獣たちの身体が傾き跳びはね雪と一緒にその下の泥をはねあげるのを見、闘争のホログラフィーが血にまみれるのを見た。裂けた肺から飛び散る血、暗い色の心臓から噴き出してくるくる回る血。やがて銃声が轟いてすべてが終わった」
こんなふうに「バレエを踊る獣たち」の断章につづいて、ためらいもなく人を殺し死体を洞窟に隠すバラードの行動がつづくと、いつしか両者が重なり、雪の山中で生き死にを繰り返す獣たちとバラードの所業との間に区別がつかなくなってしまう。法や共同体からはみだし家族も失い、銃だけを力とするバラードは、現代の物語なのにまるで原始の山野をさまよう男のようだ。マッカーシーがこの作品の12年後に書いた『ブラッド・メリディアン』(ブック・ナビで紹介済)は開拓時代の話だったが、考えてみればアメリカの開拓時代もまた法や共同体の希薄な世界で無数の血が流された、一種の神話的世界だった。『チャイルド・オブ・ゴッド』との差は、一方の主役が西部の砂漠でインディアンを襲っては頭皮を剥ぐ私兵集団(擬似家族)だったのに対し、バラードは家族もなくたったひとり山と森に生きることを強いられた天涯孤独な男であることだ。
殺人を疑われたバラードは、村人たちに私刑にされそうになる。死体の場所へ案内すると言って入り込んだ洞窟で、内部をよく知るバラードは村人たちを撒いて逃げおおせるが、奥深く入り込んだため出口が見つからない。岩屋に閉じ込められたバラードはこう描写される。
「夜に猟犬の声が聴こえたので呼びかけてみたが自分の声の谺が洞窟のなかで凄まじい音で響き渡り怖ろしくなって呼ぶのをやめてしまった。闇のなかで鼠がかさかさ走る音がした。もしかしたら鼠はバラードの頭蓋骨を巣にして元々は脳があった空洞でみゅうみゅう啼く小さな無毛の子鼠を何匹か産むかもしれない。バラードの全身の骨は卵の殻のようにきれいに磨かれその骨髄腔のなかで百足が眠り白いほっそりした肋骨は暗い石の洞窟のなかで骨の花のように咲くだろう」
頭蓋骨は空洞になって鼠の巣になり、そこで子鼠が産まれる。骨髄腔のなかに百足が棲んでいる。肋骨は洞窟のなかで骨の花になる。このあまりにも凄惨で美しいイメージは、バラードがもはや人間というより、意志や感情を持たない自然の一部になってしまったことを示していないだろうか。そのような存在としてのバラードを、マッカーシーは「神の子」と呼んだのだった。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





