天皇家の女たち【鈴木裕子】
天皇家の女たち
| 書籍名 | 天皇家の女たち |
|---|---|
| 著者名 | 鈴木裕子 |
| 出版社 | 社会評論社(400p) |
| 発刊日 | 2019.04.09 |
| 希望小売価格 | 3,780円 |
| 書評日 | 2019.06.20 |
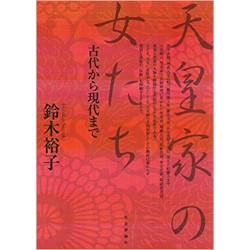
平成から令和へと時代が進む中、平成天皇の生前譲位や女性天皇、女系天皇、皇族の婚約といった皇室関係の話題がこれほど語られた一年もなかったのではないか。各々の論点は様々であり、その多様性こそが天皇制議論の特徴だと思うのだが、どのくらい歴史的、法律的な視点からの知識を持った上で議論しているのか、はなはだ心もとないと思うのは私だけだろうか。
本書の著者、鈴木裕子は早稲田大学で日本史学を学び、山川菊栄に代表される婦人運動家の研究とともに、民族差別やジェンダーに関する著作も多い学者だ。鈴木の考え方の基軸は、「天皇制」は男系父家長制で貫かれた差別的システムというものだ。だからこそ、「天皇家の女達」というタイトルを掲げ、古今の膨大な資料を引用しながら古代からの天皇とその家系を支えた女性達に焦点を当てて令和の時代までを俯瞰して語っている。大著であるが、全体を通しての文章表現は論理的に語ろうとする意識が見て取れる一冊になっている。
幅広く詳細な本書の中で、興味が持てた論点は、まず、古代における女帝の登場経緯と、その系図である。私自身あまり、女帝という意識で天皇系譜を辿ったことはなく、敢えて言えば最初の女帝は推古天皇だったといった知識レベルでしかない。本書で再認識させられたのは、初の女帝となった推古天皇(32代)以降、皇極天皇(35代)、皇極が再祚した斉明天皇(37代)、持統天皇(41代)、元明天皇(43代)、孝謙天皇(46代)、孝謙が再祚した称徳天皇(48代)とその女帝たちの系譜を示されると、女帝の多さに圧倒される。つまり、男系の血を確保しようとするための家系の複雑さだけではなく、皇子が年少のため中継ぎ的な形で女帝がごく普通に存在していたということである。
二点目は、後宮制度の歴史である。大宝律令(702年)による、体制確立の一環として後宮制度も定められたが、後宮は「妃」・「夫人」・「嬪」の三段階の身分を持つ女達で構成され、その上に「正室」である「皇后」がたてられる形式である。後宮・側室の人数は別として、この制度は明治天皇の時代まで継続した。
ちなみに、桓武天皇(50代)は32名の後宮を持ち、そこから親王(男)・内親王(女)を33名授かったという数字にいささか驚くのだが、桓武天皇(50代)から醍醐天皇(60代)までの11代の天皇の間で天皇一人当たりの子供の数は嵯峨天皇の50名を筆頭に平均19名だったと示している。このように後宮・側室制度が男系の確保の仕組みの根底を示しているとともに、跡目争いに端を発する戦乱が多発した血の歴史であることも系譜から読み取れる。
次の大きな論点は、明治維新による皇室の変化である。孝明天皇の死去とともに、側室中山慶子の子である睦仁(明治天皇)が皇位につくことになる。
明治維新といっても、千年という慣習の打破は簡単でなく、当時の海外の外交官が明治天皇と接見した際の文書が引用されているが、「天皇は薄化粧に結髪姿で女官に囲まれていて、頬には紅をさし、唇は赤と金で塗られ、歯はお歯黒で塗られていた」という天皇の姿は政府の考える国家新体制とはまだまだ乖離していたことを示している。
明治天皇は1869年に一条美子と結婚をした。美子皇后は近代天皇制を進め、族姓に関わらず女官を登用するという方針のもと、武家、平民出身の娘たちを集めるとともに、女性の学識経験者なども進講のために招集した。一方、明治天皇は国政の行事に積極的でなかったこともあり、美子皇后は妻として「国母」として政治・外交・軍事の面で積極的に活動したという。まさに明治の天皇家の近代化とは「雅び」の世界から「軍国日本の君主」への転換とともに、皇后の見え方も大きく変化していったことが判る。
次に、123代大正天皇は側室の庶子として生まれた。明治天皇の5名の親王は全て側室からの庶子であり、かつ成人出来たのは嘉仁親王(大正天皇)だけであった。病弱であり、政治的というには程遠かったと言われているが、節子皇后は4名の親王の実母としてだけでなく、「救癩」事業を支援する皇后の姿を国民にアピールして「国母」イメージの定着を図った。昭和天皇の良子皇后もまた日本の母としての主婦のシンボルとして「大日本連合婦人会(1931年創設)」の会長などに就き、戦後は歴代の皇后は「日本赤十字」の総裁に就いている。
戦後、象徴天皇として天皇制はスタートしたが、昭和の側室制度の不採用に端を発し、皇后は「国母」という象徴に天皇より早く到達したといえるのではないかと私は思った。この象徴天皇制のプロパガンダは主として新聞報道の皇室写真やキャプションによるメディア戦略がとられて「良き家族の母」「平和な家庭」といったイメージで皇后像の転換が図られていっただけでなく、明仁皇太子の結婚のニュースはテレビ映像が強力な手段として活用され、旧皇族・旧華族でもない「民間」の知的エリート一族の美智子妃の姿も国民の中に「良き象徴」を醸成させるに資するものがあったろう。そして、令和のいま、天皇・皇后、秋篠宮、その妃と内親王・親王達について多くの報道がされている。
しかし、天皇家が日本の家族の象徴的姿の体現であればあれほど、もはや男系男子のみの継承という文化は統計学的にも長続きしない文化であることは自明である。
以上の「女たち」という視点から離れて、著者はジョン・ダワーの「敗北をだきしめて」から引用して昭和天皇に関する問題提起をしている。
それは、終戦時、高松宮や近衛文麿らは昭和天皇退位と引き換えに天皇制維持を目指して連合国側と交渉に臨むべきと考えていたが、マッカーサーは昭和天皇の戦争責任ばかりか道徳的な責任さえもすべて免除する決断をした。このため、武官・文官・政治家の責任者達は戦犯として戦争責任を問われ処刑されていったにも関わらず、国家の最高責任者であった天皇は罪に問われることはなく、国民の心に「加害者意識」や「戦争責任意識」を薄れさせ、逆に原爆投下や都市爆撃などの「被害者意識」が強く残ってしまったという考え方だ。これが、他国から見た時の日本の戦争責任のあいまいさとして残るとともに、歴史修正主義者の存在の根源という見方だ。
著者は「天皇家の人々の存在を否定するわけではない。特別な家系のみが尊重されることが差別なのではないか」という言葉に天皇制に対する考えを集約しているようだ。
確かに、昭和天皇の戦前と戦後の二重性は同時代に生きた国民からはどう見えたのだろうかと思う。亡父は大正9年生まれ、昭和17年大学卒業とともに就職、昭和18年召集、昭和19年結婚、昭和20年ポツダム中尉で兵役を終え、元の職場に復帰、昭和22年に第三次公職適否審査委員会に出向し自らの親族の公職追放審査をやらされたという経験をしている。まさに、戦争に翻弄された人生であったが、父と天皇制について話し合うことはなかった。父はそうした話題を避けていたかも知れないが、今考えれは一言でも父の思いを聞いてみたいものであったと今更ながらに考えさせられた。( 内池正名 )
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





