帝都東京を中国革命で歩く【譚 璐美】
帝都東京を中国革命で歩く
| 書籍名 | 帝都東京を中国革命で歩く |
|---|---|
| 著者名 | 譚 璐美 |
| 出版社 | 白水社(246p) |
| 発刊日 | 2016.07.26 |
| 希望小売価格 | 1,944円 |
| 書評日 | 2016.09.19 |
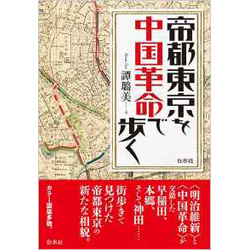
著者は1950年東京生まれ、慶応義塾大学文学部を卒業し、慶應義塾大学文学部訪問教授、ノンフィクション作家として活躍している。父親は中国広東省の出身、革命運動にのめり込み、1927年日本に脱出して早稲田大学の政治経済学部を卒業、日本人を妻として戦後も日本で暮らし続けた人物である。こうした、バックグラウンドを持った著者が辛亥革命前後の中国人たちの学びの場・生活の場としての東京での足跡を辿るとともに、そこで繰り広げられた中国革命にまつわるエピソードや人物像を描いている。
時代は二十世紀初頭(明治後期から大正)に焦点を当てている。そして、中国人留学生たちの主要活動拠点があった早稲田、神楽坂、神保町、本郷、などの地域を示すために、「東京一目新図(明治三十年)」、「東京大地図(明治三十九年)」、「東京市全図(明治四十三年)」、「東京市全図46版(大正十一年)」という、四つの時代の番地入り地図を並べて示すことで時間の変化を楽しみながらの誌上散歩である。
これらの地図を眺めてみると、明治30年の地図では、旧東京市といえども自然地形に寄り添って街が形成されていたことが判る。しかし、旧東京市の中央部は明治末期から大正にかけての30年間で急激な変化を起こしながら、ほぼ現代に近い形で街が出来上がってきた。当然、道幅や建物、人口の集積についての違いはあるとしても、住宅地、商業地、学校といった街の持つ主要な社会的機能や地域文化を支える基盤は出来上がっていると言ってよい。そうした時代に、中国人がなぜこの時代に日本で学ぶことを選択し始めたのかについてこう書いている。
「二十世紀初頭の日本は、清国の青年たちの強い興味を引いた。欧米の文化と近代科学を吸収して近代化を成し遂げ、無血革命ともいえる明治維新を実現した国であり、アジアで唯一、欧米列強と肩を並べる近代国家だった。……とりわけ、留学生や清国政府が注目したのは小国ニッポンがなぜ大国清国に勝ったのか、である」
この時期の中国人留学生の数は、1902年の500名から毎年1000名、1300名と増加して、1905年には8000名にまでになったという。特に、1905年の急激な増加の理由として挙げられているのが、「日露戦争での日本の勝利」と「科挙制度が廃止されたことによる新しいキャリアとしての日本留学」の二点である。伝統的な官吏選抜試験だった科挙の代替が日本留学によって果たされるとは考え難いが、辛亥革命前後に、これほど多くの清国留学生が日本で学んでいたというのも驚かされる数字だ。
過去、遣隋使・遣唐使の時代から、日本の幾多の役人、僧侶などが宗教、政治、技術などの新しい波を学ぼうと中国大陸を目指し、また、大陸から各分野のプロたちを受け入れてきた。この1300年程の一方通行的な知識流入の歴史に対して、二十世紀初頭前後のこの時代は、世界規模のせめぎあいの中における日中間の新しい関係構築の始まりの時期であった。また、留学生だけでなく、時の体制に反対する人々など多様な人材が日本に活動の場を求めていたことが本書でも示されている通りだ。こうした立場の違いを超えた中国人達がこの狭い東京で生活していたことを考えると、この時代は日本人・中国人の双方が互恵的に知日派・知中派を醸成していた貴重な期間だったといえるのかもしれない。
孫文、梁啓超、蒋介石、魯迅、周恩来などいった後に中国を牽引する著名な政治家、学者、軍人達の日本での活動が仔細に紹介されているものを読むと、彼らの生活感をもった人生と歴史的イベントの必然性を理解出来る。換言すれば、受験勉強のための歴史知識はイベント中心の断片であることの限界を認識させられる。また、中国革命で多様な役割を果たした多くの若者達の東京での生活が本書では取り上げられている。
当時、中国人留学生たちは来日すると半年から一年間日本語学校で日本語や基礎学問を学んだ後に早稲田、慶応、法政といった私学を中心とした大学に進学するものが殆どで、留学生の9割が東京に生活の場をおいていたという。
留学生の日本語教育と基礎教育の拠点として、神田区仲猿楽町5番地の東亜高等予備校(現:千代田区神田神保町2丁目)と牛込区西五軒町34番地の弘文学院(現:新宿区西五軒町12番)があった。両校とも毎年1000名から2000名近い学生が学んでいたというから大規模な学校である。また、清国留学生会館が神田区駿河台鈴木町18番地(現: 神田駿河台2丁目3番地)に駐日清国公使の肝いりで作られている。この会館もやがて政治闘争の拠点として使われるようになる重要な施設だ。
大学は早稲田、神田、本郷といった地域に集中していたが、特に、早稲田大学に進学する学生は多かった様で、正門前の鶴巻町には清国留学生のための寄宿舎を初め、多くの下宿屋が軒を連ねており、留学生が自主経営した清国式理髪店、中華料理屋も多くありまさにチャイナタウンの様相だったという。この地域で留学生たちは郷土料理を堪能しつつ、思いっきり方言で会話できるたまり場だったようだ。
知的満足と食欲を満たす町として神保町があった。本屋街としての神保町はまた、食の街でもあった。食で言うと、「維新號」が色々な局面で登場する。最初は中国留学生向けの雑貨などを神保町で扱っていた「維新號」は本書のいろいろなエピソードの中で登場する中華料理屋だ。おまけの様に食べ物も提供していたのが、徐々に中華料理店としての名声を博し、中国人留学生の政治的たまり場にもなって「維新號事件」として語られる中国留学生検挙騒動の舞台にもなっている。
こうした、拠点は現在の区制でいえば、新宿区、文京区、千代田区に集中していたということになる。
「芥川龍之介より日本語がうまい帝大生」という章を見ると、1921年の中国共産党設立メンバー13名の内、4名が日本留学経験者であり、他の数名も日本に滞在したりした経験があったということからも「知日派」の集まりであった様だ。その内の一人、李漢俊は1902年14才で来日し、暁星学校に6年間学び、名古屋の第八高等学校をへて東京帝国大学土木工学科で学んだという経歴。当時の学籍簿が東大に残っていて、住所は牛込区白銀町33番地(現:新宿区白銀町6番地)というから神楽坂の近くの相生坂に住んで、本郷に通っていたわけだ。
こうした記録が残っていることが本書のような企画が成り立つ所以である。帰国後の李漢俊については、1921年中国共産党の発足に係わっ後、1927年武漢の軍閥である胡宋鐸に捕えられ銃殺される、享年37才で生を終えている。
本書では、留学生の帰国後の活動も描写しているが、リーダーであるが故に歴史の奔流の中で、銃殺、暗殺、斬首といった無念の死を遂げている人々も多いことは歴史の結果とはいえ残念なことである。
この他、孫文、蒋介石、魯迅、周恩来、郭沫若、廖承志といった各界のリーダーたちの東京での足跡を丁寧に辿っている。こうした人々の日本での生活体験は知日派(親日派であるかは別)を育み、日中両国の関係において少なくともマイナス面を減少させる貢献があったと考える。例えば、この時代の留学生や亡命革命家たちによって多くの日本の文献が中国語に翻訳されていた事実を本書は指摘している。1896年以前の日本語から中国語の翻訳本の数は8冊。これが、1896年から1911年の間で958冊、1912年から1937年の間で1759冊という翻訳本が刊行されている。もっとも1937年以降は140冊と激減しているのも両国の関係をあまりに的確に示している。
本書はタイトル通り、歴史の足跡をめぐるガイドブックとして読むことも面白いのだが、中国の清国政府崩壊から国民党政権、国共合作、共産党設立といった歴史(イベント)を係わった人の留学人生から辿る面白さもある。丁度、東京の各地域や拠点の変化を縦糸として、留学生たちの人生を横糸として織りあげられた絵柄は、日中両国の関係を良かれ悪しかれ描き出していることに気付く。 (内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





