谷崎潤一郎と映画の存在論【佐藤未央子】
谷崎潤一郎と映画の存在論
| 書籍名 | 谷崎潤一郎と映画の存在論 |
|---|---|
| 著者名 | 佐藤未央子 |
| 出版社 | 水声社(320p) |
| 発刊日 | 2022.04.15 |
| 希望小売価格 | 4,400円 |
| 書評日 | 2022.10.18 |
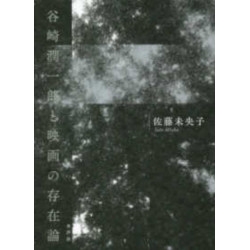
谷崎潤一郎といえば若いころ「細雪」とか「痴人の愛」とか代表作しか読んだことがなく、大作家という印象を持っていたが(それには違いない)、彼が大正時代に書いた初期作品の妖しい魅力に目覚めたのは『美食倶楽部 谷崎潤一郎大正作品集』(種村季弘編・ちくま文庫、1989)を読んでからだった。東京というモダン都市に育った知的スノッブが当時最先端の探偵小説や映画の魅力にはまり、映画館や浅草オペラや見世物が集まる浅草を歩き回り、その経験から犯罪や映画や魔術や美食や異性装を素材に小説に仕立てあげた。文豪というイメージが一気に、そのへんを歩いていそうな都会青年に見えてきた。
同時に、若き日の谷崎が映画という大衆娯楽であり新興芸術でもあったメディアに興味を持っただけでなく、のめりこんだあげく実際に映画製作にもかかわったことを知った。『美食倶楽部』と同じころ、谷崎と映画を主題にした千葉伸夫『映画と谷崎』(青蛙房)が出版され、それが実際にどんなものだったかがわかった。1920(大正9)年、谷崎は横浜にあった大正活動写真(大活)に顧問として招かれ、4本の映画の製作にたずさわっている。
その4本は、谷崎原作で谷崎の妻の妹・葉山三千子(「痴人の愛」のモデル)を主演女優にした『アマチュア倶楽部』。泉鏡花原作・谷崎脚色の『葛飾砂子』。谷崎脚本で谷崎の娘が演じたファンタジー『雛祭の夜』。上田秋成原作・谷崎脚本の『蛇性の婬』。残念ながら4本ともフィルムが失われ、見ることはできない。どれもいかにも若き谷崎の好み。見てみたいなあ、と思った。たしか淀川長治さんが、『葛飾砂子』だったかを見たことがあると話していた。
そんな記憶が残っていたので、『谷崎潤一郎と映画の存在論』の新聞広告を見て読んでみたいと思い、注文して取り寄せた。手に取った本は、エッセイというより専門的な研究書に近い。実際、本書は著者の博士論文に加筆修正したものだという。学位論文というものはそれなりの作法があり、まず先行する研究を検討し、引用して位置づけ、その上で著者の見解を述べるのが一般的。この本もそういうスタイルを取っている。だから著者が自分の見方を縦横に語った(その語りの面白さが読書の楽しみでもある)ものではない。それでも興味深く読めたのは、映画と谷崎を巡って知らなかった事実をたくさん教えられたのと、谷崎研究の主流からすれば異端であるこのテーマに興味を持つ研究者がけっこういて、へえ、こんな議論をしてるんだ、と分かったから。
映画と谷崎というテーマで先駆的な仕事をした千葉伸夫の本は、谷崎が実際に製作にたずさわった4本の映画とその実態を中心にしたものだった。本書はそうでなく、谷崎が映画と映画人、映画監督や女優を素材にした小説について主に論じる。具体的には「人面疽」「月の囁き」「肉塊」「青塚氏の話」「魔術師」といった短篇を取り上げ、それら小説の「テクストに表れた映画にまつわる思考」を追っていく。
「人面疽」は、大活が映画化に動きはじめたが実現しなかった短篇だ。当時は無声映画で尾上松之助の時代劇や新派の現代劇が人気。それが弁士と楽隊つきで上映されることが多かった。「人面疽」はどちらとも違う「純文芸物」。映画女優を語り手に、劇中映画で青年が人面をした腫物に寄生され、狂い死ぬ。著者はクライマックスたる「人面疽」のクローズアップを評して、「近代テクノロジーかつ人工物であるはずの映画に見いだされる、原初的な<不気味>さ」を狙い、「実現すれば、映画の黎明期に多くの人びとが体感した驚きや戦きを、新式の技術によって増幅させる『アトラクションの映画』となりえた」と書く。実際に映画化されたら弁士も楽隊も必要としない、ひたすら映像の魔力を追求する映画になっただろう。
「月の囁き」は「映画劇」として発表されたもの。小説ではなく、谷崎が映画用に書き下した脚本を自ら修正して「『撮影台本』、いわゆるコンティニュイティの形式」で発表したものだ。実際、この作品には随所に「タイトル(字幕)」とか「C、U(クローズアップ)」とかの文字が挿入される。例えば「水面。C、U。さし出された女の顔がそれへ映っている」といった具合。「場面」と「場面」をつなぐことで全体が構成される。ここで谷崎は「C、U」を多用している。当時、日本映画はまだ女形が女性を演じることが多かったが、この作品では入浴シーンを含め女優のエロティシズムが求められている。月を見ることで狂気を孕む女と、彼女に魅入られた男という組み合わせは、谷崎の小説によく出てくる構図。「『月の囁き』は『読物』化されても、物語を推し進める散文的な語りではなく、ショットの連辞による映画的文体を持つ作品として編まれる必要があった」と著者は記す。
もう少し挙げてみよう。「肉塊」や「青塚氏の話」は、谷崎の映画論としても読める。「肉塊」で、実業を営みながら芸術家でありたいと望み遂に映画製作に乗り出した主人公(谷崎のように)は、映画の魔力をこう述べる。「映画といふものは頭の中で見る代りに、スクリーンの上へ映して見る夢なんだ。そしてその夢の方が実は本物の世界なんだ」。谷崎はエッセイ「映画雑感」でも「まことに映画は人間が機械で作り出すところの夢であると云はねばならない」と書いている。小説の主人公の言葉は、そのまま谷崎の考えであると思っていいだろう。
「青塚氏の話」では、熱狂的な映画ファンの青塚氏が偏愛する女優について、こう語る。「此の世が既にまぼろしであるから、人間のお前もフイルムの中のお前もまぼろしであるに変りはない。まだしもフイルムのまぼろしの方が、人間よりも永続きがするし、最も若く美しい時のいろいろな姿を留めてゐるだけ、此の地上にあるものの中では一番実体に近いものだ」。映画は機械が作り出した精巧な夢であり、まぼろしである現実よりも夢のほうが本物なのだ。谷崎が繰り返すいかにも彼らしい映画論の背後に、著者はじめ研究者はベルクソンの影響を見ているようだが、それは置いといて。
大正期に映画にのめりこんだ谷崎は関東大震災を機に関西に移り住んで映画製作から遠ざかり、『春琴抄』から『細雪』に至る代表作を生み出す。以後、自らの小説が映画化され、原作者として女優と嬉々として戯れることはあっても、映画を主題にした小説や映画製作からは遠ざかる。文学史の上からは、谷崎の映画への傾倒はここで途切れた、大正期の活動はいわば寄り道だったと解されることが多いようだ。でも著者は、戦後の谷崎の創作ノートから「影」と題された映画の構想メモを取り出してみせる。これは全部で十数行の文字通りのメモだが、そのひとつはこんな具合。
「○Aなる男、自分一人でディズニーのやうな作り方(注・アニメーションということだろう)で映画を作り、自分の愛スル女を創作してその映画の中で動かす、そして自分にそつくりの男を作りその女と同棲させる、しまひにAは映画中のA’と合体してしまひ映画以外にはAと云ふ人物がゐなくなつてしまふ」
同じころ発表された短篇「過酸化マンガン水の夢」は、昼間見た映画と夢が重なる小説。大正期の映画小説をちょっと思い出させる。青年谷崎を捕らえた映画の夢が、功成り名遂げた老年期になってもそのまま保存されているのがわかる。
この本を読んでよかったのは、本書にそそのかされて谷崎の大正小説を何本か読み返したこと。また「月の囁き」を初めて読んだこと。この「映画劇」は、先に触れたように文字による絵コンテのようなものだ。谷崎が求める映像がどんなものだったかがよくわかる。ひたすら映像の美を追い求める純粋映画。それは戦後の構想メモ「影」まで一貫していよう。著者はそれをこう結論づけている。「映画へのコミットメントは文壇的視座から見れば逸脱と映るかもしれないが、そこに谷崎を捕らえこんだ映像の強度そのものを見出すこともできるだろう」。
おまけ。中央公論社版『谷崎全集』をぱらぱら見ていたら、「月報・7」に内田吐夢が小文を寄せているのが目に入った。内田吐夢は谷崎が参加した大活で映画人としてのキャリアをスタートさせている。彼はこう書いている。「谷崎先生は私の最後のたった一人の先生だったが、ついに何のご恩も返すこともなく、然も、先生の作品を生前一本も映画化していない。……何故、思い切って撮らせていただき、お叱りをうけて置かなかったかと、それこそ取り返しがつかない悔みとなっている」。
さて、内田吐夢の撮る谷崎潤一郎映画とはどんなものだったろう。またどの小説が内田らしい映画となったろう。そんな想像をしてみたくなる。ちなみに小生がいちばん好きな谷崎映画は増村保造監督・若尾文子主演の「刺青」。増村はほかにも「卍」「痴人の愛」と映画化しているけれど、増村と内田ではだいぶ体質が違う。例えば「瘋癲老人日記」はどうだろう。これは大映で一度映画化されているが、昔見た記憶ではあまり出来のいい映画ではなかった(若尾文子はよかったが)。主演は『飢餓海峡』で組んだ三国連太郎。老人が狂う息子の嫁には若尾文子をそのまま。どろどろで滑稽で、それでいながら重厚で、内田吐夢らしい映画になりそうな気がする。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





