小さな天体 – 全サバティカル日記【加藤典洋】
小さな天体 – 全サバティカル日記
| 書籍名 | 小さな天体―全サバティカル日記 |
|---|---|
| 著者名 | 加藤典洋 |
| 出版社 | 新潮社(409p) |
| 発刊日 | 2011.10.31 |
| 希望小売価格 | 2,310 円 |
| 書評日 | 2011.02.06 |
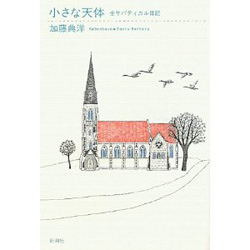
サバティカルとは大学の教員に対し一定期間毎に自主的な調査研究のために与えられる通常一年間の休暇。サラリーマンからすると想像もつかないような制度だ。もしサラリーマンが7年間働いた後、1年間の休暇を取りたいと言い出したら、まず職を失うことは確実だろう。大学の先生達の活動はチーム・プレイというよりも個人技であり、職人の世界に近い職業だと思う。そうでなければこのような制度は運用不可能だ。もっとも、サバティカルがラテン語で安息日ということを考えると、こうした制度によって充電したり、自身の研究・研鑽を深めることは意義深いことであることは疑いないと思いつつ、ある種の妬ましさとともに読み進んだ。
著者の加藤は早稲田大学の国際教養学部教授で戦後思想史、文学評論、言語学、音楽評論など幅ひろく活動している人物だ。1948年生まれだから団塊の世代真っ只中、評者とほぼ同世代の人間である。彼がサバティカルとして選んだのが、前半6カ月間をデンマークのコペンハーゲン大学、後半6カ月をアメリカ西海岸のカリフォルニア州立大学サンタバーバラ校である。2010年の3月から2011年3月末までの一年間の日記として刊行する予定が、2011年の3.11の発災もあり帰国後の2カ月間の日記を含めて出版されたもの。本書は日記と言っても定期的に雑誌掲載するために書かれたものだけに、それなりに表現に抑制が効いているところや、人名がイニシャルで記述されているところの鬱陶しさを感じつつも、それ以上に、同世代の人間が一年間の海外生活をする大変さや楽しさについて興味深い。
例えば、コペンハーゲンに6カ月間滞在中に、1/3の期間にあたる2カ月間はヨーロッパ各地を旅行するというペースの生活だ。評者も会社の出張で色々な国を訪れたが、いかんせん限られた時間で、とてもその国の文化に触れたり、人々を理解したりすることは叶わなかった。それに比して、なんと時間の流れ方のおおらかなことか。観劇や美術館めぐり、土地の食事など、たぶん時間がいくら有っても足りないという多忙感覚と同時に、のんびりと一日を過ごす余裕の双方が満たされている生活であることが良く分かる。こうした非日常的な時間の使い方の中から生まれる刺激に触発されて新たな発想が生まれてくるところに価値がある。日常生活から切り離された時間によって人間は思わぬ思考回路を働かせるものだ。
その一つが、知識と体験の間にあるギャップとそこから生まれる新たな発見だろう。著者がロンドンの地下鉄、所謂アンダー・グラウンドに乗っていての気づきが面白い。
「・・・ロンドンは日本の近代の指導者たちが実現をめざした原型がここにあった。・・・それまで西洋の大都会といえばパリぐらいしか知らない。パリは生活してみるとわかるが、東京とは似ていない。メトロでは何の車内放送もないし、ドアをあけるノブは手動であるうえ、重い。・・・東京の地下鉄は、次はどこの駅か、そこで何線に連絡するか、手取り、足取り注意してくれる。パリを西洋の標準と考えていた私は、なぜここまで『過保護的』なのか、と日本の有り方を煩わしく感じたものだ。でも、そのやり方は明治のはじめ、日本国家がこの英国から学んだものだったと、ロンドンに来て思いあたる。・・・」
こうしたちょっとした気づきをトリガーとして、伊藤博文に代表される幕末の英国留学生たちが同じ島国として「イギリスに出来ること」が日本に出来ない訳はないと考え、英国から新しい知識や思想を学んでいったこと、続く時代では、ビスマルクのドイツに「遅れてきた近代国家の追いつくノウハウ」を求めた近代日本の発展モデルについて、ロンドンの地下鉄に揺られながら考える体験も旅の効用だろう。
二つ目の点は、一度訪れたことのある土地を再度訪れることからの刺激である。時代の経過によって街や風景は様々に変化する。例えば、10年前に比べて、車が多くなったとか、人々の服装が明るくなった等々。そうした表面的な変化認識を超えた感覚を「再訪」によって認識することである。
「・・・サグラダ・ファミリア教会は三十年たち、もうだいぶ変わっている。特に正面の様子が違う・・・サグラダ・ファミリア教会から私が受け取るのは、これが一人の個人の妥協を知らない妄執の所産であることからくる感動である。・・・ここに建つ巨大な、他に例を見ないほど破格の教会は私に信仰というものについて、新しい考えるきっかけを与えてくれる。・・・教会は人間みたいだ。教会の中に入るのは、人間の内面の闇の中に入るのと同じだ。そう、今回の滞在の旅で何度も思った。これは始めての経験である。・・・」
あの教会が営々として造り続けられていることはその場に立つと圧倒的な驚異である。毎日、毎月変わって行く。だが、同時に自分自身が変わってきていることも変化感覚の大きな要素なのだろう。30歳の体験と60歳の体験の感覚はまったく違うものである。それは寺や教会といった宗教施設に対してより大きな差として体験されると思う。分かるぞ、御同輩と言ってあげたい。
また、本書を読んでいて気づくのは、電子情報機器の活用である。著者もNote PCを駆使しメールや資料の送付を行い、Skypeを利用して電話し、キンドルを活用して出版物を読んでいる。それは情報の利活用という面だけでなく、自分自身の地理的な位置認識においても大きな変化をもたらしていることを示している。著者のサンタバーバラでの一日の記述が象徴的だ。
「・・・青空文庫というものからダウン・ロードし、島崎藤村の『夜明け前』をキンドルで読みはじめている・・・カリフォルニアの椰子林を背景に読むと、藤村の長編小説の文体の生彩、叙述の懐の深さは驚くばかりである。・・・」
情報としての本は今や世界のどこにいても手に入れることが可能で、キンドルやiPadによって思いついたときにすぐ読むことができる。それは読書環境の変化の大きさだけでなく、その技術がグローバルのベースで共通化・実用化されている時代であると痛感する。
さて、著者は帰国寸前に3.11遭遇することになるのだが、発災後の数日間における各国と日本のメディアの報道写真の差について記されている。
「・・・ニューヨーク・タイムズのウェブ・サイトには二十数枚の地震・津波・原発被災の写真が掲載されている。その多くが人に焦点を当てている。遺体も写っていて、心に食い込むものが多い。・・・こういう場合、アメリカの新聞の写真は、何が起こったのかということを、それを全身で受けとめている人間を被写体として伝える。日本の新聞は、できごとをそのまま事件として伝える。・・・」
映像の扱いの文化差と情報管理の非対称性について個別の議論が必要だと考えるが、著者は以降この災害報道について積極的に警鐘を鳴らし、意見を発信している。
本書を同世代人として読んでみて、旅の非日常から新たな発見を積み上げるには「一定期間以上の滞在」が必要なのだと理解した。一カ月か、半年か、一年か。いよいよ旅に出たくなった。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





