中国民主化研究【加藤嘉一】
中国民主化研究
| 書籍名 | 中国民主化研究 |
|---|---|
| 著者名 | 加藤嘉一 |
| 出版社 | ダイヤモンド社(544p) |
| 発刊日 | 2015.07.31 |
| 希望小売価格 | 2,592円 |
| 書評日 | 2015.09.22 |
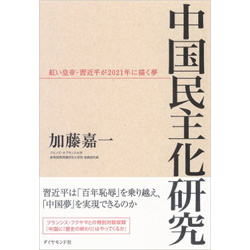
上海株式市場の混乱、天津の港湾大爆発による産業活動の停滞等の事件が続いた。以前であれば実質的な影響は中国国内に限られていたのだろうが、この手の事象が日本のみならず世界経済に影響を及ぼす時代になっていることをこの数か月の間でも実感させられている。こうした経済のグローバル連鎖において重要な要素になってきた中国に対して、本書の本来的な狙いは「習近平・中国共産党は国家・民族・文明をどこに導いていこうとしているのか」を「民主化」というキーワードで解明していこうという試みである。
著者の加藤嘉一は1984年生まれ、北京大学を卒業後、ハーバード大学フェローを経て、現在ジョン・ホプキンス大学研究員として活動している気鋭の研究者だ。著者のような文化大革命も天安門事件も体感していない世代の中国論とはどんなものなのかと言った興味も本書を手にした理由でもある。加藤は、9年以上の中国生活の体験とその後のアメリカでの研究活動、そして日本人であることの三点を統合することで本書が成立したと言っているのだが、確かにそうした経験によって得られた人脈を活用しつつ幅広い層の中国人やアメリカ人との対話が盛り込まれていて、500ページを超える大著となっている。
そこでは、彼我の視点から広範な論点を提示しており、民主化に対する希望的観測や制度的優越性といった相対的な議論から離れて、中国の民主化を促したり、あるいは拒んだり、といった現実的な要因を明確にするという考え方に基づいたアプローチで「内政」「改革」「外圧」という大きな括りでまとめられている。
「内政」の章では、フランシス・フクヤマとの対談が収められている。フクヤマと言えば、1989年書いた「歴史の終わり」でネオコン的な言い方をすれば「自由民主主義の共産社会主義に対する完全勝利の実現」を完璧に予想したといわれたものだ。確かに、その後の冷戦の終了、ソビエト連邦の崩壊などでその論は実証されたのだが、もうひとつの共産主義大国たる中国は天安門事件の発生で国家の危機を迎えたものの、民主化運動を武力で排除して終結させた。しかし、現在もその体制が持続しているという現実から、フクヤマは2011年に「政治の起源」を著し、中国政治体制と自由民主主義の比較について深く分析をした経緯がある。
フクヤマと加藤との対談はそうした意味で興味深く読んだ。また、2012年10月の第18回党大会における習近平総書記誕生の前夜に、この「政治の起源」の簡体字中国版が出版されたというエピソードが語られている。中国において出版に関しては極めて強い管理されていると言われる中で、象徴的な時期に出版されたという事実は、習近平がフクヤマの「政治の起源」を政策実施の追い風として活用しようとする意図が示されている。数千年の中国の歴史の中で西欧社会が苦労して手に入れた民主主義の条件が満たされたことは無く、「中国の民主主義の拒絶」はある種の政治的文化であり、中国にとって「民主化」とは理念や基本原理ではなく、共産党一党支配の堅持を目的とするための「手段」であるという認識が導き出されてくることの裏付けでもある。
習近平は総書記就任以来、「中国夢(チャイナ・ドリーム)」という言葉を使っている。それは、中華民族の偉大なる復興をメイン・テーマとして、中国共産党成立100年となる2021年、新中国成立100年となる2049年を重要な節目として、富強・民主・文明・和諧的な社会主義現代国家を建設するというものだ。こうしたことからも、習近平率いる中国共産党が西側諸国文明で育った民主主義を「真似る」可能性は限りなくゼロに近く、たとえ中国が政治改革・民主化に舵を切るにしても、それは「中国の特色ある」という条件を前提としている意味では、原則的な民主主義に移行することは無いと考えざるを得ない。
しかし、「中国夢」の実現についてはいくつかの疑問を加藤は指摘している。その一つが、中国共産党の「党紀は国法を超越する」という体制の持つリスクである。それは「中国の悪い皇帝問題」と言われる議論だ。良い皇帝であれば、法治や民主主義がなくても迅速に政策を行うことが出来る。しかし、悪い皇帝であった場合、大きな災いを国家にもたらすことになるというもの。従って、社会主義体制に比較して、チェック体制を持ち均衡システムである自由民主主義の方が安全であるという考え方は二元論というよりは相対論としての納得感をもたらしているようだ。
「改革」の章では、習近平による改革のアプローチを分析している。当然マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、社会主義といった問題に抜本的な見直しを行う余地は無い。そう考えると習近平のとりうる「改革」のきっかけとしては、鄧小平の行った経済改革開放を超えるというスタートポイントが現実的な発想としている。鄧小平、江沢民、胡耀邦といった時代は「安定・成長」を進めてきたが、習近平にとって現代はポスト「安定・成長」の時代であるということである。従って、統治の正統性からも「公正」を優先するという政策選択は必然と言えるし、政治レベルを含んだ改革に踏み切る前提で「反腐敗闘争」や「構造改革」に挑むという選択がされた。
薄熙来事件や周永康事件に代表される反腐敗闘争の「虎もハエも一緒に叩く」という施策において「規律違反」や「汚職・横領」といった法治に基づく大義名分はあったとしても、本質的には権力闘争を超えた路線闘争であり、経済活動への良い意味の影響を与えつつも、民主化を促進する施策かというと加藤は否定的である。「中国共産党が憲法を超える存在である」以上は「いくら名医でも自分の病気の手術は出来ない」という例え話で締めくくっているのが印象的だ。
「外圧」の章では、「言論報道の自由」について、ニューヨークタイムズ記者に対する入国ビザの発給拒否といった国外からも直接的に目に見える制約をどう解いていくのかという議論や、その他にも、香港は厳密に言えば外圧ではなく、内政であるものの世界が注視している中での一国二制度という点では外圧に近いし、台湾の政治状況や出版の連携(中国本国では許可されない出版物は台湾で出版して香港経由で中国本土に届けるという抜け穴)、中国留学生の増加による各国情報の流入、等、幅広い現状がまとめられている。また、米国は過去の冷戦時代にソ連を封じ込めようとしたが、中国に対してはその必要もなく中国が崩壊するときは勝手に崩壊する、という立ち位置としている。それは国家としての外圧を行使することなく、中国の民主化を拒絶する共産党と、中国の民主化を望まない米国という、ある意味お互いが利害を共有していると加藤の見方について、そうした見方もあるのかという感慨はあるものの、納得ではないなという意識が評者の感覚。
本書の最期のポイントとして「反日と民主化」について語られている。反日の源泉である抗日戦争は共産党が国民党を台湾に追いやり、毛沢東が中華人民共和国を建国するという歴史のプロセスの中の重要な地位を占めているだけでなく、中国共産党が第一党であるための正統性の根拠でもある。しかし、こうした意図でのナショナリズムの高揚は、一方で反日が引き金となり結果的に中国共産党の統治にヒビが入る可能性は依然として高いと指摘している。日中間の突発的事件に端を発した反日活動の制御の失敗、そして反党・反政府運動の激化、結果一党独裁体制崩壊から最後に民主化というステップを想定しての著者の判断である。
本書は、国家としての中国というよりも習近平個人の育ちから、教育、経験を詳細にトレースして、その能力、人脈、思想、をまとめたものと理解していいのではないか。時間経緯も鄧小平以降を主としている本書を読んでいると、評者の中国の知識の原点は人民公社・文化大革命・四人組・天安門事件・改革開放といった時代であり、習近平の世代とは一世代前の知識が主体だと痛感する。
鄧小平以降の時間軸とは、それ以前とは遙かに複雑化し、経済開放された中国と、相互依存関係を強めている世界各国の姿が見えてくる。そうした中、現代の日中関係の不安定さが二国間の問題に止まらずグローバル・リスクになりうることを解くことは政治の重要な役割であろう。加藤は日本の取るべき「体制面」「市場・経済面」「世論面」での処方箋を示している。著者の姿勢は感情に流されない気鋭の説としてさわやかな感覚さえ受けるのだが、一方、政治の側面からは、そうしたナイーブさを突き抜けたしたたかさや誠実さが求められるのではないかとつくづく感じるのだ。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





