統制百馬鹿 : 水島爾保布 戦中毒舌集【前田恭二】
統制百馬鹿 : 水島爾保布 戦中毒舌集
| 書籍名 | 統制百馬鹿 : 水島爾保布 戦中毒舌集 |
|---|---|
| 著者名 | 前田恭二 |
| 出版社 | 岩波書店(334p) |
| 発刊日 | 2025.07.07 |
| 希望小売価格 | 3,300円 |
| 書評日 | 2025.11.19 |
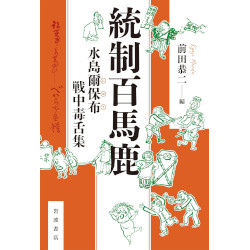
水島爾保布(におう)は1884年(明治17年)生まれ1958年(昭和33年)没。根津生まれの江戸っ子で幼いころから浅草の見世物小屋や歌舞伎、落語などに浸っていた。長じて東京美術学校(現東京芸術大学)を卒業したものの画家だけで飯を食うのは難しかったようで、大阪朝日新聞に入社。当時、写真の印刷技術は進んでおらず、街頭風景や旅の景色などの挿絵を描くだけでなく、記事原稿も書いていたという。その時の上司が大正デモクラシー立役者の長谷川如是閑だった。彼は英国流の自由主義、陸羯南系のナショナリスト、深川生まれの江戸っ子という三つの顔を持っていたといわれている。この長谷川が国民目線から政府・官僚に対して積極的に批判的発言をしていたことにも水島は影響を受けていたと思う。しかし、大阪朝日新聞の寺内内閣を糾弾した記事が摘発され、社長以下、幹部の長谷川も退任に追い込まれた。その後、水島も大阪朝日を離れて雑誌「大日」でコラムと挿絵の掲載を始める。頭山満・井上重六が率いた「大日」は国粋主義的だったことから水島の無節操さを指摘する声もあったようだが、井上からの「悪口歓迎・雑言亦可也」という言葉に支えられて、水島は戦時の不合理さを書き続けることになる。
本書は「大日」1937年から1945年2月号(最終号)まで掲載された水島のコラムで構成されている。1936年の二・二六事件以降、盧溝橋事件と日中戦争への道を歩み始め太平洋戦争に至る、まさに戦中の時代である。その中で時の総理大臣や海外の指導者達を落語に例えた漫画を描いたり、コラムで弄り回すことで陸軍省や警視庁から責められたりもしたようだが、頭山満の睨みが効いており他誌に比べて自由に書くことが出来たと戦後水島は語っている。ただ、編者の前田が指摘しているように水島には明確な思想信条があるわけではなく、戦争自体を否定せず、合理的な統制であれば耐えうるべしという考え方だったようだ。ただ、本書に取り上げられている様に不合理な統制や自粛に対しては批判的で、その表現は四書、歌舞伎、落語などに引っかけて皮肉ったり、嘲笑、罵倒の連続だが、現代の我々にとっては編者前田の注釈がないと水島のその捻った表現の面白さを十分に楽しめないと思う。私の名前「正名」は母方の祖父が名付け親で論語からとったものだが、明治・大正・昭和と生きた祖父の世代だからこそ論語から孫の名前を考えるというのも身近な教養だったのだろう。しかし、今となっては論語も我々の日常からは遠い文化になってしまったという感慨が深い。
コラムからいくつかのトピックを拾ってみると、水島は1937年3月号にオリンピック開催を返上すべきというコラムを書いている。紀元二千六百年の記念行事として東京でのオリンピック開催を決定したあと、競技場をどこに作るかとか、ホテルを作るのかといった議論が空回りする中で「東京中が毛唐のお客様の接待のため、これはみっともないとかいろいろ数え立てている。電柱が多すぎる、街路に置かれたオワイ桶は汚い、婆さんがアッパッパを着るのは醜悪。これらは単に今の日本を否定しているだけで、異人諸君に見せたくないならファシズムを発揮してアッパッパの販売を禁止するほうが手っ取り早い」と皮肉るとともに「東京オリンピックなどやめてしまえ」と切って捨てる。そして国はこのコラムが書かれた一年後の1938年に開催返上を決定している。
1938年になると、国民精神総動員運動に代表される統制・自粛の流れが強くなっていく世の中を危惧している。小学生のランドセルを止めろとか、毛糸の上着を着るなといった動きも「ご時世だから」という万能用語で片づけていく時代だった。こうした精神運動は国から自治体、隣組と活動主体を国民に落とし込んでいったことであたかも自主的な姿をとった国家統制であるとともに、その非合理性にも水島は厳しい目を向けている。例えば、防空演習について、「空襲警報か発せられ、歩行者は避難せよと言うが、どこに?と聞くと、そこらの店先の軒下に入れという。夕立じゃあるまいし。警防団服のいかめしい親方も軒先へ。我らともに当世百馬鹿に見えてくる。」と手厳しい。また、英語排斥が叫ばれて「カタカナ表記のものをことごとく日本語に変える。トンカツを衣揚げ豚肉とか、スポーツ用語の中でも野球のボールとストライクは「悪玉と善玉」する案が出たとか、まさにくすぐりネタの供給」と笑い飛ばしている。1943年になると竹やりで藁人形を突く訓練が隣組で行われ、「アメリカの大軍が内地に上陸してくる想定の下『一突必殺』の気持ちを錬成するために各戸に竹やりを常備せよとはまるで百姓一揆である」とあきれ果てている。
こうした日本の状況と比較する形で、1939年に水島は漫画家仲間と満州を慰問して回った旅の中で感じた事柄を描いている。一つは満州国で地名が満州語音で呼ばれている場所と、日本語読みの場所が混在していることを取り上げて「地名は固有名詞なので満州人の満州国であれば、日本人の便利さでおかしなことはやらない方が良い」と指摘している。また、鉄道で乗り合わせた日本軍の歩兵将校との会話についてやたらに伏字を多用してコラムに書いている。これも読者の想像力を試しているようでもあり、伏字にしなければならないようなことをこれだけ語っているという政府・軍部批判の一つの表現としては凄い挑戦である。
1941年に宇治茶とかいった産地名でなく産地毎の番号を振って管理することになったが、そうした管理に疑問を呈している。「これが嵩じると懲役人は番号で呼ばれ、町内の人々も電話番号で認識され、そして最後は生れ出る赤ん坊に番号をつけるまでに至るかもしれない。人間の機械化だ」と語っている。この時代日本が番号管理を推進した政策の一つは、朝鮮に於いてすべての国民に番号を付して植民管理を推進したことだと言われている。同様の施策はドイツにおけるユダヤ人管理で、一人ひとり番号が振られ管理され、例外なく収容所に送り込まれた。こうした施策に活用されたのが当時の最新情報技術の統計機(パンチカード計算機)である。これらが、情報処理効率化の負の側面として語られるように、今のマイナンバーカード施策も負の部分を回避する識見が必要になることにまた気付かされる。
不要不急の旅行は止めろとの御触れが出ると、物見遊山の団体旅行は「武運長久」を祈るためと称して寺や神社の参拝を付け足したうえで継続されていたという。このように、世の中は統制価格や配給制度をかいくぐる闇市場も存在していた。金持ちは物を確保できたろうし、物を横流しして儲ける輩も多かった。そうした統制社会を1945年2月、最後のコラムで次のように書いている。「世間人間が正直で、嘘もつかなれば統制法だの配給制というものは必要ない。これらが施行されたのも、つまりは世間人間が不正直で嘘つきだからの話で、国家・国民がお互いに侮辱しあっているようなものだ。もっと言えば、正直正道の君子であれば戦争なんかは起こりもしなかったろう」。まあ、1945年2月ではもはや敗戦を目前にして「欲しがりません、勝つまでは」とか「一億火の玉」といった追い詰められた世情の中でのコラムとしてみると良くぞ言ったと思うのだ。
また、水島は豊島区西巣鴨堀之内に住んでいたとのことで、本書の中にも巣鴨新田とか堀之内踏切といった言葉が出てくる。私は学生時代まで西巣鴨に住んでいたこともあり、勝手に都営荒川線(戦前の王子電車)などの風景などを思い出しながら読み進むことも楽しかった。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





