バカの壁【養老孟司】
バカの壁
| 書籍名 | バカの壁 |
|---|---|
| 著者名 | 養老孟司 |
| 出版社 | 新潮新書(208p) |
| 発刊日 | 2003.4.10 |
| 希望小売価格 | 680円 |
| 書評日等 | - |
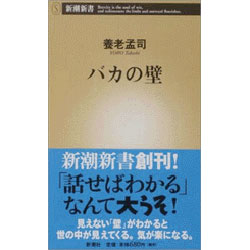
バカの壁とはなにか?
それを著者は、解剖学者らしくといったらいいのか、養老孟司らしくといったらいいのか、1次方程式を使って説明している。
y=ax
xは、目や耳など五感を通して脳へなんらかの情報が伝えられる入力。yは、入力した情報に反応して運動(考える、話す、書く、手足を動かす等々)として表現される出力。aは、入力されたxが好きだとか、嫌いだとかの反応を決める係数。人によって、また入力された情報によってさまざまに変わってくる。
たとえば恋人に会って、aがプラスの値であれば行動yはプラスになるし、いやな奴に会ってaがマイナスの値であれば、行動yはマイナスになる。aの値がプラスにせよマイナスにせよ適切な値であれば、情報を現実としてきちんと認識し、環境に適応していることになる。
ところがa=0の場合がある。例えばパレスチナの主張に対するイスラエル側の係数、逆にイスラエルの主張に対するパレスチナ側の係数は0に近い。だからどんな入力に対しても出力はない。つまり入力xは行動yになんの影響も与えない。
a=無限大の場合もある。例えば原理主義とか、神とか、なんらかのイデオロギー。その人にとって、ある情報や信条が絶対のものとなるから、その人の行動yを絶対的に支配する。
脳の仕組みは別に高級なものではなく、単純な入出力装置(計算機)にすぎない、と養老教授は言う。だから、人間のたいていの行動はこの方程式で説明できるのだ、と。こんなすごいことを、しかもさらりと言ってのける文章に出会う瞬間が、養老孟司を読むいちばんの快楽の時だ。
ここまでくれば、「バカの壁」がなにを意味しているかは想像がつくだろう。係数aがゼロ、あるいは無限大の状態。壁に囲まれた私の意識がそのまま世界のすべてであり、その外にある情報は壁で遮断し、外の世界を見ようとしない人。特殊な人々のことではない。僕たちだって、ある種の入力に対してはaがゼロになったり無限大になったりするかもしれない。いや、きっとなるに違いない。
著者は大学の教師(東大医学部教授)として、長年、aがゼロになったり無限大になったりする学生や学者に接してきたからだろうか。若い人にこれだけは言っておきたいという思いと、いいかげんにしろという突き放し、そこに養老孟司らしい断言がかぶさって、これは談話を文章化したものだが、書かれた著書とはまた別の面白さをもった読みものになっている。
ここで教授が繰り返し言っているのは、「人間は変わる」ということだ。
人間は起きている間も寝ている間も成長したり老化したり、刻々と変化しつづけている。寝る前の「私」と起きた後の「私」は別人なのだ(鶴見俊輔が、1年前の日記を見ると自分が書いたものとは思えない、1年前の自分というのは他人だと言っていたのを思い出す)。そうであるのに、脳内の自己同一性を求める運動によって、僕たちは「私は私だ」と思いこんでいるにすぎない。
現代社会は脳化社会、意識中心社会なのだ、と教授は言う。肥大化したヒトの脳は言語や芸術、科学、宗教を生んできた。それが極端になったのが現代の都市で、建物も道路も交通機関もなにもかもが人工物でできており、街路樹や公園も人工的に配置された、すべてヒトの脳がつくりだしもののなかに僕たちは生きている。
「昨日の私と今日の私は同じ」というのが近代的個人の前提だけれど、「私は私だ」と考えた瞬間に、意識の外にある無意識や身体は切り捨てられ、「私は変わるものだ」という、かつては誰もがもっていた考え(ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず)は失われる。
人間は変わるものなのだから、悩んだり迷ったりするのは当たり前なのだ、と著者は繰り返す。それを無理にはっきりさせようとしたり、確かなものがほしいというところから、係数aがゼロになったり無限大になったりする。
ページのあちこちから、養老教授らしい独創的な言葉が飛び出してくる。「個性は脳ではなく身体に宿っている」とか、「人間は流転するが情報は流転しない」とか、「巨大になった脳を維持するために刺激を自給自足している状態を「考える」という」とか、「「働かなくても食える」というかつての理想をホームレスが実現している」とか。論理の積みかさねというより、いきなり抜き身をつきつけられるように出現するそんな断言が痛快だ。
そして、常識をくつがえすような議論の末に「常識=コモン・センス」へとおもむろに着地するのが、養老流の人生論の骨頂なのだろう。
「世の中で求められている人間の社会性というのは、できるだけ多くの刺激に対して適切なaの係数を持っていることだといえる」
「「自己実現」などといいますが、自分が何かを実現する場は外部にしか存在しない。人生の意味は自分だけで完結するものではなく、常に周囲の人、社会との関係から生まれる。とすれば、日常生活において、意味を見いだせる場はまさに共同体でしかない」
ヒトとヒトは、そのようにしか生きられない。これはヒトという大脳が異常に肥大した動物の身体を研究対象としてきた解剖学者の、このおかしな生物への愛の表明とでも言えるかもしれない。
この本は新潮新書の一冊として刊行された。新潮新書は新書戦争が一段落した今年4月の創刊だけれど、後発らしく著者やテーマの選び、タイトルなど、とてもよく練られている(嵐山光三郎「死ぬための教養」もタイトルに惹かれて買ってしまった)。「バカの壁」は最初に出た10冊のなかでも、いちばんよく売れているらしい。
とはいえ、この本の語りおろしという形式は、岩波新書や中公新書で育った世代には物足りないかもしれない。そうであれば、養老教授を有名にした「唯脳論」(青土社)をお勧めしたい。モノの見方をひっくり返される、目からウロコの名著です。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





