背信の科学者たち【ウイリアム・ブロードほか】
背信の科学者たち
| 書籍名 | 背信の科学者たち |
|---|---|
| 著者名 | ウイリアム・ブロードほか |
| 出版社 | 講談社(354p) |
| 発刊日 | 2014.06.20 |
| 希望小売価格 | 1,728円 |
| 書評日 | 2014.08.11 |
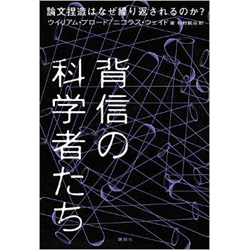
原書「Betrayers of the Truth ( 真実の背信者たち)」は1982年にアメリカで出版され、1988年に化学同人から邦訳が出版された。科学の世界の不正の歴史とその構造に正面から取り組んだものとして高い評価を得た本である。発刊後30年たった現在でも科学不正に関する「古典」として確たる評価を得ている。そもそも本書が書かれたトリガーは1970年代から80年代にかけて、アメリカで科学不正が数多く発覚したことにあるのだが、本書が本年(2014年)6月に日本で再刊行された経緯は、STAP細胞に係る科学不正事件の発生にあることは言うまでもない。本の帯には「STAP騒動の底流をなすものは、この本を読めば、すべてわかる」という挑戦的な言葉が並んでいる。
著者、ウイリアム・ブロードは1951年米国生れ。ニューヨークタイムズの科学記者で、ビューリツア賞をジャーナリズム部門で2回受賞している。もう一人の著者、ニコラス・ウェイドは1942年英国生れ、「サイエンス」「ネイチャー」といった有名科学雑誌の記者を経験し、ニューヨークタイムズで科学担当論説委員。両者とも科学記者として科学不正(ミスコンダクト)報道に携って来た経験が長い。また、訳者の牧野賢治は1934年生まれ。大阪大学理学部大学院から毎日新聞に入り、科学記者として30年間活動をしてきた。著者・訳者ともにジャーナリストとしての視点を保ちつつ、科学界に迎合する素振りを微塵も見せない姿勢が本書で貫かれている。
加えて、今回の再単行本化に際し、牧野は直近四半世紀におけるミスコンダクト事件について、新たな訳者解説と事件年表、参考文献等を追加している。この部分は本書全体の10%を超えるボリュームがあり、その意味からも原書の「科学が社会でどう機能しているか」についての「古典」の要素と21世紀における科学界のミスコンダクト事件(欧米・アジア・日本)に関する訳者なりの理解を付加したという二つの側面を持っているのが特徴だ。
本書は、1980年代初めに、米国議会の下院科学技術委員会の証人喚問に米国科学アカデミーの会長が招集されたところから始まる。
「科学研究上の欺瞞などという問題で証言するのは不愉快だし、心外である。この問題は報道によって、あまりに誇張されたものである。科学における欺瞞は非常にまれで、かつ、効果的で民主的で自己修正的に機能するシステムの下で、必ず看破される」と発言した。科学不正が発覚すると科学界の重鎮たちのコメントはきまって「不正を起こした科学者の精神的・心理的混乱の産物」であると個人の問題(腐ったリンゴ説)に原因を求めるのが常だった。STAP細胞論文に疑義が生じた時、理化学研究所の野依所長も「一人の未熟な科学者によって」といったことを思い出す。これは科学界に限ったことではないが、組織の中にいる人間はなかなか問題の原因を自組織に求めることは心理的にもハードルが高いということを示している。
しかし、著者たちは、ハーバード大やエール大といった名門で1970年代からいろいろと発覚していた 捏造(Fabrication),改ざん・偽造(Falsification),盗用・剽窃(Plagiarism)といった科学不正事件を報道する中で、その原因を個人の精神的混乱や未熟さだけに求めることは出来ないと結論付けている。科学界のボスたちが言うように「自己修正的に機能するシステムの下で、不正は必ず看破され」欺瞞は間違いなく失敗に終わるとするならば、不正に手を染めた科学者たちが公然と「仮説・実験・検証」というプロセスや第三者による再現追試や検証確認といった基本規範さえ黙殺してきたのかは説明できない。
一般人が常識として信じてきた科学の正当性については次のような、二つの考え方にあると言われている。一つは、科学を職業とみなして「真理を求める科学者の情熱こそが科学を純粋にする」という科学者個人の誠実さや美徳にその源泉を求める考え方。第二の意見は、「科学とは精密な論理プロセスであり、自己検証的な科学システムによって、あらゆる種類の誤りは速やかに、容赦なく排除されるという制度的システムに担保されている」という考え方だ。こうした二つの考え方は伝統的科学観・科学者性善説とでもいうべきものなのだが、著者たちの結論は、本来の科学の本質はこうした伝統的科学観とは似ても似つかないものだとしている。
「新しい知識を獲得するとき、科学者は論理と客観性だけによって導かれるのではなく、レトリック(修辞説明=今様にいえばプレゼンの上手さ)・宣伝・個人的な偏見といった非合理的な要因にも左右されている。・・・科学は社会における合理性の守護者と考えられるべきものではなく、社会の文化的側面を形作る主要な一部にすぎない」
たしかに、科学哲学者のように純粋論理だけを議論してばかりでは片手落ちとしても、科学界における俗欲的要素は否定できないということのようだ。栄誉はオリジナリティ(発見の先取)に対してだけ与えられ、エリートの過度な優遇、科学の報奨制度、経歴を重んずる師弟関係、発表論文の数への評価、研究開発費の獲得のための根回し、政治の介入、など多くの欺瞞・不正誘発要因があるという指摘だ。
本書では数多くの科学におけるミスコンダクトの歴史と事例が示されていて、あらゆる不正の手段や手口が例示されていると言ってよい。また、医学や自然科学、物理学など広範な領域での科学観や手法に関しても基本的な説明から始まり、詳細かつ具体的に触れられているので、科学の方法論を包括的に理解するという意味では恰好の指南書だと思う。本書を読んでみると、いかに多くの科学者たちが不正や誠実さの欠如といった指摘を受けていたかを知り、驚くばかりである。俎上に上がっているのは、プトレマイオス、ガリレオ、ニュートンなどのデータの選択における不誠実さとか、他人の実験・観察データの流用とかが、ことこまかに指摘されている。
その中で、エリートが甘く取り扱われるという事例として野口英世が取り上げられている。サイモン・フレクスナーはロックフェラー医学研究所を率いるアメリカ医学研究の創始者であったが、彼の下で野口は梅毒、黄熱病、小児マヒ、狂犬病といった、数多くの病気の原因となる微生物を分離し続け、短期間に200編という驚異的な数の論文を提出し、野口の生存中その論文に異議が唱えられることはなく、論文審査から免れ続けたという。まさに、「名誉は優れた仕事だけにではなく、地位によっても与えられる。ボスに率いられた論文工場のような組織では、真理のためよりも個人的な栄光のために研究を行う傾向が強い・・エリートの仕事を不当に賞賛し、厳密な審査からの免除を与える」という事態である。しかし、野口英世の研究は50年後の総括的評価では業績価値はほとんどなく、業績の多くは科学の舞台から静かに姿を消している。
牧野の訳者解説に目を向けると、直近のSTAP細胞の問題を初めとして、30年前のアメリカでの議論と何ら変わっていないことに気付かされる。日本の科学界は体質を変えるチャンスを二度失っているように思える。一度は1980年代から1990年代にアメリカでの科学不正に端を発し、ヨーロッパや中国では科学界の内部改革が進展したにも関わらず、我が国は対岸の火事とばかりに傍観していたという事実。第二は2000年代はじめに発生した、「旧石器発掘捏造事件」、理化学研究所での「血小板論文データ改ざん」に始まり、大阪大学や東京大学でも論文不正が発覚、2005年に日本学術会議は「科学におけるミスコンダクトの現状と対策」を公表し、理研でも「科学研究における不正行為とその防止に関する声明」や「指針」を制定したものの、結果として仕組みづくりに終わり、2014年のSTAP細胞論文事件の発生を防げなかった。多くの国費が投入されている科学分野において、こうした管理状態は看過すべきではないと思う。
小保方氏の博士論文についても、常識的には理解し難い報告が早稲田大学からなされた。大学の調査委員会は「本来、正しく審査されていれば決して博士の学位は発給されていなかった」・「博士学位を授与されるべき人物に値しない」としながら「学位を取り上げない」という判断が出されるとともに「学位はく奪による生活破壊を配慮」といわれては、科学界の自浄能力は地に落ちたというほかはないのではないか。民間のまっとうな会社で不正行為をすれば無条件で解雇され、「生活破壊を配慮」されることなどありえないだろう。こう考えると、STAP細胞問題で理化学研究所の内部検証調査では問題の把握と再発防止策を作り上げることは出来ないのではないかと思う。こうした組織を運営してきた科学者達の限界が見えてしまったようだ。
STAP問題が起きていなかったら、本書に目を通すことはなかったろう。過去からの科学ジャーナリズムの地道な活動を本書によって確認出来たことは収穫であった。冷静に考えれば「科学者」と「管理者」を兼務できる人材は育成もされてこなかったし、そもそも違う特性の人材と割り切って、機能分離するしか対策はないようにと思われる。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





