文化大革命五十年【楊 継縄】
文化大革命五十年
| 書籍名 | 文化大革命五十年 |
|---|---|
| 著者名 | 楊 継縄 |
| 出版社 | 岩波書店(284p) |
| 発刊日 | 2019.01.30 |
| 希望小売価格 | 3,132円 |
| 書評日 | 2019.04.22 |
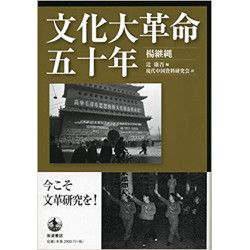
「文化大革命五十年」という本書のタイトルを目にしたとき、時間の経過する速さに驚きつつ、あまりに遠くなってしまった当時の思い出が湧き出して来た。1960年代の初頭、中学生の私はベリカード(受信確認証)をもらう目的で各国の中波の日本語放送を聴いていた。その一つが北京放送だった。受信の記録を送ると美しくデザインされたベリカードとともにその後日本語小冊子が毎月の様に送られて来た。「人民公社好」・「大躍進」といったスローガンが躍る小冊子だったが、中学生だろうが関係なく送付していたのだろう。そんなきっかけで、中国という国に興味を持ちはじめた。1960年代中頃になると「文化大革命」という先鋭的な言葉と、報道される三角帽子を被せられた昨日までのリーダーたちが街を引きずりまわされる映像の持つギャップに不気味さというか違和感を覚えながらそのニュースに接していた。自分自身も騒然とした時代のど真ん中で混迷を深めていただけに、この対岸の騒動はニュース以上のものではなかった。
著者の楊継縄は1940年生まれ。新華社の記者の後、多くの著作を発表し、彼の代表作である「墓碑—中国六十年代大飢荒紀実」(2008年刊)は世界的にも注目された一方、楊に対する当局からの圧力が強まったといわれている。そうした理由からか、多少なりとも自由な香港で本書の原本である「天地翻覆----中国文化大革命史」(2016年刊)は出版されている。90万字という原本を要約する形で日本語版である本書は作られているが、要約とはいえ、二段組で300ページの本書は高齢者の視力ではなかなか厳しい読書であった。
著者は「文革の悪夢から逃れ、災禍の再来を避けることこそ、中国が直面する重大な任務」として、文化大革命を科学的に研究することの重要性を強調しつつ、研究がまだまだ十分でないという認識である。本質的には、依然として「中国大陸」では文革研究はタブーとされていることから、真相の研究も表面的なレベルにとどまっていると著者は考えている。中国において、当局による出版審査を通った「文革史」と呼ばれる本はいくつか出版されているが、そのほとんどは官僚や知識人を被害者として紹介しており、一方、その迫害の加害者がその時点で権力を持っていたものであったと明確にしていないという。こうした状況に対する、著者の苛立ちが本書を書こうとしたモチベーションのように感じられる。そのため、歴史に対する「責務」や「責任感」という強い言葉を使って、真相を解明しようとする論調と併存して、自らの「熱」を抑えるかのように「科学」・「事実」という視点を語っているのが印象的である。
本書は文化大革命の始まりから紅衛兵、林彪事件、毛沢東の死、四人組裁判にいたる終焉までを描いている第一部。文化大革命後の名誉回復、官僚体制下の改革開放を描く第二部。文化大革命五十年の総括として、建国後17年間の制度に立ち戻って文革の根本原因を探るなど、現在の中国にとって文革の対価や遺産は何なのかを述べている第三部、という構成になっている。
全編を通して登場する人物も圧倒的な数で、既知の名前の方が稀であることなどからも、どんどん読み進み文革を俯瞰的に理解するという読書となった。
1965年の彭真への批判、続く劉少奇と毛沢東の対立から、1966年の中国共産党中央委員会で反革命修正主義分子を摘発するという通知が出されて、時を置かずに「中央文革小組」が成立して文化大革命が始まった。以降の10年間に発生した、林彪事件、毛沢東の死、四人組の裁判といった中国の混乱した状況に関して、膨大な資料を引用しながら記述されていく。それは複雑極まりないジグソーパズルの様で、個々のピースが全体のどこに、どう関連して行くのかを理解して行く難しさを痛感させられる。
しかし、著者が一番言いたいことは、10年間の文革の結果と収束以降を語ることにあると思う。文革の結果として判り易いのは、人的な被害の規模感である。1978年の中央政治局会議で報告された数字は、一定規模の武闘・虐殺事件で127,000人が死亡、党幹部の闘争で10,500人が非正常死、都市部の知識人・学者官僚が反革命・修正主義・反動とレッテルを貼られ683,000人が非正常死、農村部における豊農とその家族1,200,000人が非正常死、と報告されている。文革に関連して2百万を超える国民が死亡したというこの数字を示されると、権力者間の政治的な闘争といった概念を超えて、壮大な内戦であるといえる。
そうした抗争の中で、1971年の林彪事件はまだまだ多くの不明点があるものの、その結果については著者は「この事件は中国のみならず、現代世界で最大級の政治ゴシップであり、それは毛沢東に痛撃を見舞ったばかりか文化大革命の弔鐘として鳴り響いたのだ」と語っている。この事件が文革のターニング・ポイントであったとしている。
その後、1976年1月に周恩来死去、9月9日に毛沢東死去、10月6日に四人組逮捕という推移を見ると、けして政治の理によって文革が終焉したのではなく、「象徴」の死によって文革の最終章を迎えたというのが良く判る。
文革後、多くの人的損失に加えて、毛沢東の死後、文革が中国にもたらした危機に対応するために、改革が必要とされ、経済改革は進められたが、政治改革は実施されることはなかった。つまり文革後権力を握った勢力は文革を全面的に否定しながらも毛沢東の政治遺産である一党独裁と官僚の集権化を捨てることは出来なかった。
1981年6月の中国共産党十一期中全会は文革を「指導者が間違って引き起こし、反革命集団に利用されて、党と国家を各民族・人民に大きな災難をもたらした内乱である」という結論に対して楊は次の様に語っている。
「文化大革命を否定しているが、文革を生み出した理論・路線・制度は否定していない。こうしたある意味、中途半端な結論によって、現在の中国に文革の悪魔が残っている。このため、災禍の再来が避けられない。……自由主義の角度から見ると、『官僚集団』とは中立的な言葉であり、制度の執行者であるが、中国の様に官僚集団の権力が国民から支えられたものではないので、権力を抑制したり均衡させる力はなく、官僚は公務上の権力を使って、大衆を抑制することが出来る。経済は市場化したが、権力構造は計画経済時代の状態を維持している。この状態は権力の濫用と資本の貪欲さが悪質に結合しているのが現代の中国の一切の罪悪が群がるところであり矛盾の源泉である」
これが、著者が文革を研究することの熱源である。ただ、著者は自らが先達と言っている訳ではなく、「後学の徒」であり、先行の研究者の優れた大量の著作を起点として始められた良さもあると語っている。それでも、著者はその時代の当事者であったことには違いない。
本書を読んで思うのだが、「自分の体験としての時代」と「歴史としての時代」を峻別して考えることは難しいことが良く判る。自分を正当化することと相反する色々な視点からの意見を客観的に聴く姿勢を持ち続ける気力が必要だ。他者の視点を加えて時代は完成する。つまり、自分が見聞きした体験は大切にすべきであるが、それは歴史を語る上での一面でしかないのだから。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





