終わりなき危機 君はグローバリゼーションの真実を見たか【水野和夫】
終わりなき危機
君はグローバリゼーションの真実を見たか
| 書籍名 | 終わりなき危機 君はグローバリゼーションの真実を見たか |
|---|---|
| 著者名 | 水野和夫 |
| 出版社 | 日本経済新聞出版社(540p) |
| 発刊日 | 2011.09.05 |
| 希望小売価格 | 2,940円 |
| 書評日 | 2012.05.11 |
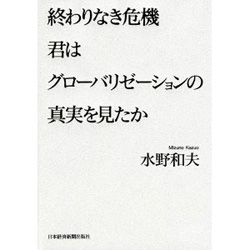
『終わりなき危機』は3つの「危機」の日付から始まる。「9.11」「9.15」そして「3.11」。米国同時多発テロ(9.11)とリーマン・ショック(9.15)、福島第一原発事故(3.11)のことだ。「9.11」はジェット旅客機がミサイルと化して、「9.15」はサブプライムローンが「金融版大量破壊兵器」として、「3.11」は原発が「放射能兵器」へと姿を変えて弱者に牙をむいた。
この3つの危機は何を意味しているのか。さらには、こうした危機が連鎖する21世紀とはどのような時代なのか。それがこの本を通底している問いだ。答えをあらかじめ言ってしまえば、これらは「近代の終焉を告げる事件・事故」であるというのが著者の考え。そのことを検証するために水野は、中世から近代への転換点となった16世紀のグローバリゼーションと、1970年代から現在へと続くグローバリゼーションとを重ね、比較している。
「『コロンブスとヴァスコ・ダ・ガマ以来の近代史とは、要するに、ヨーロッパによる北アメリカの開発に伴う超長期のブーム』だと捉えれば、……近代化は米国によるアジアの開拓史へと受け継がれ、『地理的・物的空間』(実物投資空間)を広げていった。/『海の時代』(注・海洋国家が覇権を握った近代)のシステムに決定的な打撃を与えたのは1973年の第一次石油危機と、75年の米国のベトナム戦争敗北である。この二つの事実が意味するのは、石油危機が先進国の永続的な交易条件の改善を終わらせ(注・原油価格が永続的に上昇するようになり)、ベトナム戦争敗北が米国によるアジア市場の開拓を止めてしまったことである。この二つは、近代が依って立つ根幹なのだから、それが同時期に崩壊したということは、『近代史』が終わったということになる」
先を急ぎすぎたかもしれない。この本の面白さは、そうした壮大な見取り図だけにあるわけではない。長らく金融の世界でエコノミストとして活躍してきた著者が、数多くのデータを駆使して1970年代以降の日本と世界を分析し、「成長がすべてを解決する時代は終わった」と結論づける過程こそが本書の最大の読みどころである。そこからいくつかのデータと、彼の読み解きをひろってみよう。
1974年、先進国の1人当たり粗鋼消費量がピークに達し、その後は低下している(日本は73年がピーク)。近代化は都市化と移動距離の増加として表れる。19世紀の鉄道と運河の普及、20世紀のモータリゼーションは鉄の消費量を飛躍的に増大させた。だから鉄の消費量は近代化のバロメーターとなる。それがピークをつけたということは、先進国では近代社会を特徴づけた大量生産・大量消費社会が「飽和点を迎えた」ことを意味する。
日本の粗鋼消費量がピークに達した1973年、日本の中小企業・非製造業の資本利潤率も9.3%のピークをつけ、以後は低下している。輸出の割合が大きい大企業と違って、中小企業・非製造業は営業基盤を国内におくから、「その資本利潤率が日本国内における資本利潤率を代表する」と考えてよい。それは「日本国内において拡大路線が終わったことを意味している。『地理的・物的空間』の膨張が止まり、かつ縮小する傾向がますます強まっているからこそ、その後長期金利は低下基調をたどった。そして97年以降、日本の10年国債利回りは14年間にもわたり2.0%割れを続けている」。
では日本の1980年代の「バブル」と、それに続く欧米の「バブル」は何だったのか? 資本主義はもともと「実物投資を増大させ、投資が投資を呼ぶことによって利潤を極大化させる」システムである。ところがそれが飽和に達したとき、「恒常的な貯蓄超過経済において、『余剰マネー』に金融技術革新で高レバレッジをかけることにより、『電子・金融空間』の中で利潤極大化」を図った。「日本の1980年代の土地・株式バブルから2010年のギリシャ問題まで一貫しているのは、立体空間(注・電子・金融空間)を駆使してバブルを起こすことでしか、先進国は成長できなくなったことである」。バブルが崩壊すると、「成長戦略の名のもとに政策の総動員」が行われるが、先進国でそれは解決の決め手にならない。日本では1992年以降193兆円の景気対策が行われ、国の借金が584兆円増えたが、その間の名目GDPはほぼゼロ成長である。
2002年から2007年の「戦後最長の景気回復期」に、にもかかわらず1人当たりの賃金は低下した。19世紀半ばから1世紀以上安定していた名目GDPと雇用者報酬の関係(一方が増えれば他方も増える)が、1999年以降、先進国で劇的に変化して労働分配率が低下したのだ。例えば日本では、2006~08年に名目GDPが増加しているにもかかわらず雇用者報酬は低下した。
「グローバリゼーションを背景として、資本が労働を圧倒する力を持つようになったときに市場原理主義を推し進めれば、企業が利潤率を極大化しようとするので、限界労働分配率がゼロに向かって低下していく」
「企業が利潤極大化を目指してUP(注・1生産量当たりの利潤)を高めようとすれば、家計の購買力が低下し、望むと望まないとにかかわらず、結果としてデフレになるのである」
日本では1990年代後半から金融資産ゼロの貯蓄非保有世帯が急増し、2010年には2人以上の世帯で22.3%、単身世帯で33.8%に達している。
「問われなければならないのは、1人当たり4万ドル以上の所得がある日本で、なぜ豊かな暮らしができないかである。1990年代半ば以降、日本では(労働分配率の低下などにより)所得の二極化が急速に進んだ結果、分配面で大きな歪みが生じた。……その結果、先進国共通の現象として中産階級が没落する」
「近代とは、技術進歩によって経済成長をするということを皆が信じて疑うことがなかった時代だが、9.15や3.11以後、成長しようとすればするほど、一方で貧しくなる世界がある。近代の原理に忠実であろうとすればするほど、反近代を招来させることになった」
水野はこのような「21世紀のグローバリゼーション」を、1世紀に渡った中世から近代への転換「16世紀のグローバリゼーション」と重ねて考えている。
16世紀のグローバリゼーションは先進地域である地中海世界2400万人と、後進地域である英蘭独仏、食料供給地帯である東欧諸国の計4500万人の統合プロセスだった。その過程で食料価格を中心に物の価格が8倍に高騰した。結果として、ヨーロッパの先進地域と後進地域の価格差が2倍程度に収まり、また新興国・英国と先進国・イタリアの生活水準の逆転が起こった。
それに対して21世紀のグローバリゼーションは、「先進国の10億人と、控え目にみてもBRICs4カ国だけでも28億人との市場統合である」。16世紀に食料価格が8倍に上昇したことを考えれば、食料価格だけでなくエネルギー価格が10倍になってもおかしくはない。
水野は、現在の世界で進行している「近代の終焉」はこれから先も長く続く過程であるという。その先に見えてくるはずのポスト「近代」の姿は、さまざまな危機が露わにした「近代」の枠組みの延長線上にはありえない。
「21世紀は、経済的に見ればゼロ成長の時代であり、後半になると『グローバル資本帝国』解体の時代となるであろう」と水野は言う。逆に言えば、科学技術と成長の神話の上に成立した「グローバル資本帝国」を解体しないと、安定した社会はやってこない。
その具体的な姿は、むろんまだ誰にも描けない。水野も「脱テクノロジー・脱成長の時代」「自然と人間の共存の時代」「脱化石燃料社会」「『定常』で成り立つシステム」「貯蓄と投資がバランスし、ゼロ成長で持続する社会」といった言葉で素描するに留めている。
今、私たちができることは、近代のシステムがもたらした歪みとその理由を正確に認識し、それをどう克服するか、だろう。その過程のなかからしか、来るべき社会の姿は見えてこない。そのために、本書はものすごく参考になるし、大きな知的刺激を与えてくれる。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





