ブルックリン・フォリーズ【ポール・オースター】
ブルックリン・フォリーズ
| 書籍名 | ブルックリン・フォリーズ |
|---|---|
| 著者名 | ポール・オースター |
| 出版社 | 新潮社(336p) |
| 発刊日 | 2012.05.30 |
| 希望小売価格 | 2,415円 |
| 書評日/翻訳者 | 2012.07.11/柴田元幸訳 |
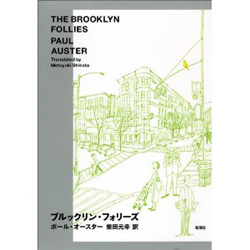
「ブルックリン・フォリーズ」とは、あえて訳せば「ブルックリンの愚行」とでもなるのか。ポール・オースターの新作は、彼が愛し、今も住んでいるニューヨークのブルックリンを舞台にしている。ブルックリンに住んだことのある僕としては、見逃すわけにいかない。
例えばオースターはブルックリンの町について、こんなふうに書いている。
「白、茶、黒の混ざりあいが刻々変化し、外国訛りが何層ものコーラスを奏で、子供たちがいて、木々があって、懸命に働く中流階級の家庭があって、レズビアンのカップルがいて、韓国系の食料品店があって、白い衣に身を包んだ長いあごひげのインド人聖者が道ですれ違うたび一礼してくれて、小人がいて障害者がいて、老いた年金受給者が歩道をゆっくりゆっくり歩いていて、教会の鐘が鳴って犬が一万匹いて、孤独で家のないくず拾い人たちがショッピングカートを押して並木道を歩き空瓶を探してゴミ箱を漁っている街」
僕はダウンタウンの繁華街と中流白人の住宅街とアフリカ系が多い低所得者用公共住宅との境目にあるアパートに住んでいたけれど、10分も歩けばオースターの描写する光景のほとんどに出会うことができた。高層ビルの立ち並ぶマンハッタンとは違う、雑多なものが雑多に交じりあった「ニューヨークであってニューヨークでない」町なのだ、ブルックリンは。
小説の舞台は、広大なプロスペクト・パークの西に位置するパーク・スロープという中流白人の住宅街。100年以上前につくられたブラウンストーン(褐色砂岩)の家が並ぶ。ポール・オースターが脚本を書いた映画『スモーク』(いい映画でした)を見た人なら、ここで撮影された映画が映し出す風景を覚えているだろう。
小説は、「私は静かに死ねる場所を探していた」という一文で始まる。語り手の「私」は保険のセールスマンだったが、60歳で肺ガンを手術し、放射線治療で頭髪を失い、気力を失い、仕事を失い、妻も失って「傷ついた犬のように」生まれ故郷ブルックリンに帰ってきた。たったひとつ自分で決めた「仕事」は、「自分が犯したあらゆる失態、ヘマ、恥、愚挙、粗相、ドジ」を記す「人間の愚行の書(The Book of Human Follies)」を書くこと。
ささやかに暮らし始めた「私」は、やがてこの町で二人の男に出会う。ひとりは甥のトム。優秀な成績で大学を卒業し、学者として前途洋洋だったはずのトムは、7年ぶりに会うと肥満体で、「全身から敗北の空気が立ちのぼる」古書店員になっていた。もうひとりは、トムが勤める古書店の店主でゲイのハリー。ハリーはシカゴで画廊を経営していたが、贋作づくりに手を染めて刑務所暮らしをし、名前を変えて古書店をやっている男だった。
「私」はこの「カボチャ頭の悪党」が好きになり、傷ついた三人の男たちはやがて気を許しあった仲間になる。地元のレストランで食事しながら、ハリーは「ホテル・イグジステンス」の夢を語る。「ホテル・イグジステンス」とは架空のコミュニティというか、ささやかなユートピアというか、ハリーが小さいころから夢想してきた、そこにいれば誰もが幸せになれる「絵空事のサンクチュアリ(避難所)」のことだ。
ハリーの夢物語に対して「こんな話、どこにも行きつきませんよ」と言うトムに、ハリーはこんなふうに答える。「あたしたちはここに座って、次の料理が来るのを待ちながら極上のサンセール(ワイン)を飲んで、意味のない話に興じてる。何も悪いことないじゃないの。これって世界中たいていの地域で、洗練されたふるまいの極みに見られると思うよ」
そんな会話を交わしながらも、日常生活ではいろんなことが進行している。「私」はいきつけのダイナーで人妻のプエルトリコ系ウェイトレスに熱を上げ、悶着を起こす。トムもパーク・スロープで出会った美しい人妻ナンシーに一目ぼれし、「私」は仲を取り持ったりする。「私」の妹の娘、9歳のルーシーがいきなりアパートのドアを叩いてころがりこんでくる。音信不通の妹(母)について、ルーシーはひとこともしゃべらない。
ハリーの店には、かつての悪党仲間で元恋人の男が戻ってくる。ハリーは男と組んでアメリカ文学の古典、ホーソーンの『緋文字』の直筆原稿を偽造して最後のひと儲けをたくらむ。そんな時、「私」とトムはヴァーモントの郊外で、「ホテル・イグジステンス」の夢を実現できるかもしれない、営業していない古びたホテルに出会う……。
これ以上、筋を追うのはやめよう。でも読者は、まるで映画のようなストーリー展開と、ポール・オースターらしい形而上的な問いと、時事風刺と知的ジョークを楽しみながら、三人の「愚行」の行き着く先から目が離せなくなる。傷ついた男たちの夢追い物語であり、何組ものカップルの愛の物語でもある。本当は悲しい話なのに、全体が優しく、温かい。歳をとること、生を楽しむことが穏やかに肯定される。「すべてにおいて世界と和解したかった」と「私」は述懐する。
そんな小説の舞台としてオースターが選んだのがブルックリンだった。住みはじめた「私」はこんな発見をする。
「純粋に人類学的な見地から言って、ブルックリンの民は、これまで遭遇したどの部族より見知らぬ他人と話すのを嫌がらないことを私は発見した。人々は好き勝手に他人の用事に口出しし(子供に十分暖かい服を着せていないといって年配の女性が若い母親をたしなめ、犬のリードを引っぱりすぎだといって通行人が飼い主を叱る)、駐車スペースをめぐって狂乱の四歳児同士のように言い争い、当意即妙の短いジョークを平然と決めてみせた」
実際、僕がブルックリンに住んでいた一年間、見知らぬ老女から声をかけられたことが二度ある。一度は初冬の夕方、ブルックリン橋近くの交差点で信号待ちをしているとき。寒くなったのでウールの帽子をかぶったら、後ろから来た品のいいおばあさんが背中のデイパックから帽子を取り出し、「あなたがかぶっているのを見て、あたしもかぶることにしましたよ」と話しかけてきた。
もう一度は、ご近所で行きつけのカフェからの帰り。歩いていたら、アフリカ系の60代くらいの女性が二階のバルコニーから、「今日は気持ちのいい日だわね」と声をかけてきた。そういうことはマンハッタンではまったくなかった。ブルックリン独特の文化で、昔ながらのコミュニティが残っているからだろう。
ブルックリンっ子の郷土意識と、マンハッタンの発展から取り残された悔しさを示す、こんな小噺も聞いたことがある。お前は密室にいて、部屋には三人の男がいる。ヒトラーとスターリンとブルックリン・ドジャースを西海岸ロスに売却したオーナー。お前は銃弾を二発詰めた銃を持っている。さて、お前は誰を殺すか。答えは、ドジャースをLAに売ったオーナー。で、もう一発は? もちろん、オーナーにもう一発、お見舞いする。
これなども「ブルックリン・フォリーズ」として記録してほしい。
マンハッタンを舞台にした小説は数あるけれど、ブルックリンを舞台にした小説は意外に少ない。その意味で、これはまぎれもなくブルックリンという町を主役にした小説だと思う。柴田元幸の訳はいつもながら読みやすい。
(雄)| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





