ぼくの文章読本【荒川洋治】
ぼくの文章読本
| 書籍名 | ぼくの文章読本 |
|---|---|
| 著者名 | 荒川洋治 |
| 出版社 | 河出書房新社(240p) |
| 発刊日 | 2024.11.27 |
| 希望小売価格 | 2,475円 |
| 書評日 | 2025.02.18 |
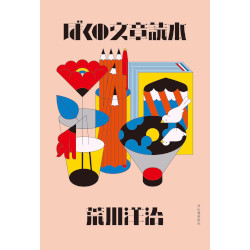
2003年からこのサイトで毎月一冊の読書感想文を書き始め、本書は252冊目となる。その中で荒川洋治の本は「忘れられる過去」に次いで二冊目である。
荒川は1975年(25才)に「日本読書新聞」の詩時評を書いたのが最初で、以降2024年までの50年間で4300編以上のエッセイや評論を書いて来たという。本書は「文章を書くことについての僕の文章」をテーマとして直近25年間に書いた「文章」に関わる55編のエッセイで構成されている。これらの初出の新聞・雑誌は25種類と多様であり、彼のエッセイを全て読み尽くしている人はそう多くないだろうから、その意味からも本書の様に評論集として出版されることの価値は大きいと思う。
本書では大きく四つのテーマに分けられている。「暮らしのなかで書く」と題して我々の日常生活で感じた面白さ等を起点として書かれた文章について。次に「詩の言葉」ではエッセイと詩の違いを語り、「文学を読む」は自ら読んで来た作家を取り上げて言葉づかい、表現の遊びなどを語っている。最後に「書く人が知っていること」としてエッセイ・散文と評論・論文などの違いや、時代による小説・評論の有り方などを書いている。
一編ずつのエッセイを読む楽しさもあるが、全編を通して、多くの作家・作品に対して荒川の解釈を示すことで作品を知るとともに、荒川の読み取り方を体感できる一冊になっている。荒川は「長く文章を書いてきたが、いまもどう書いたらいいのか不安な気分は常に付きまとう」と書いている。冗談だろうと思いつつ読み進んだが、詩人でもある荒川は「この作品は」と書くと「この」と「作品」と「は」に分割して見るというジレンマがあるという。そうした荒川は「詩の言葉は個人の感覚から生れ、個人を濃厚に感じさせる。一方エッセイは多くの人に伝わるように書く。読む人のために作者個人の知覚を抑え込んで出来ている」という違いを指摘しつつ、詩もエッセイも書いている。
「暮らしのなかで書く」とは「我々の生活という身近な風景に結びついたちょっとした面白さに惹かれて文章は生まれる」と言うのもエッセイで有ればこそという感じがする。それだけに多くの人達に響く文章が生まれる。新聞や雑誌など不特定多数の読者を対象としたエッセイは特にそうした視点が強まると思う。特にエッセイの起承転結の「起」は身近な視点から始まることが多いのは私自身の感覚である。
荒川は自らの文体について心がけている三つの点を「知識を書かない」「情報を書かない」「何も書かない」としている。最後の「何も書かない」というのは詩人的表現と受け止めておこう。こうした自らに課したルールで文章を書き「読み人に威圧感を与えないようにしている。読み手が学んだりするより、感心したり何か印象を持ってくれればよい」との考えは彼の文章に表れている特徴だ。「俺はこう思う、あなたもこう思え」的な書き方をしていないという事。
そして、荒川は文章との係わり方を8段階に分けて説明している。その第一段階は「日記」で、自分の事を書くのに遠慮もいらないし、表現に凝る必要もないために良い学習チャンス。第二段階は「試験や書類・報告書」で書式がはっきりしているだけに空欄を埋めて行けば形にはなるが、場所によって言葉を選ぶ必要がある。第三段階は随筆やエッセイなどで立場の数だけ文章があるとしている。また、その具体例として国語辞典を挙げており「岩波もあれば三省堂もある」のは編者によって言葉の説明は変わるとしているのも荒川流である。第四段階は看板などに表示される大きな文字を書いたり、天下国家などの大局を語ったりすると人の感覚は狂ってくるという指摘。最後は小説家などのプロを目指す人は「文章の書き方」なんていう本は読まない方が良いとしている。そうか。この文章読本もプロを目指す人は読まない方が良いのかも知れないが、私は全く目指していないので面白く読み飛ばすだけ。
書くという観点から、作者による言葉の選択の重要を指摘する。一般的に「先鋭」と言う言葉を文芸作品では「尖鋭」と書いたり、「興奮」を「昂奮」などと常用漢字から外れた古くから使われている字によって「情緒的・特権的な雰囲気」を作りだしていると見ている。また漢字の読み方でも「本当」と言う言葉について、漱石や鴎外は「本当」と書いているが、国木田独歩は「真実」と書いて「ほんとう」と読ませたり、室生犀星や高見順は「本統」と書いたりもしているようだ。ちなみに、「ほんとう」の語源は「本途(ほんと・本来の道筋)」が変化したもの。しかし、現代の若者は「ほんと」と縮めて発音しているので、「語源」に戻っているかもしれない。
また、文章を読むことを勧めつつ「いつまでも読む立場に甘えていては、ものごとのほんとうの理解は得られない。文章を書くことは、責任を持つだけに大きな意味を持つ」と語っている。確かに、読むと書くとは大きな違いが有ると思う。「責任」という重い言葉ではなくとも、文章は残るという意味では全く違う観点での意識が必要だ。私もこのブック・ナビに書き始めて20年以上が経つが、当初の10年間はフルタイムで働いていたこともあり、個人的に書いた文章で万一でも会社に迷惑が掛かってはいけないとの判断から、当時はペンネームを使っていた。ただ、その責任を感じて文章表現に手加減したことは無い。ただ、今思えば、こう表現した方が良かったという反省はある。それは印刷物であれ、ネットであれ、世に出せば、消せないという文章の特性が持つ責任なのだろう。
一方、書き手が自分の作品を世に出すという手段は極めて限られていた時代が長いことに気付く。大正・昭和初期の「新小説」「太陽」「中央公論」「新潮」といった主流大衆誌には既成作家だけが掲載されており、若手・新人の作品発表の場は「文章世界(博文社)」「文章倶楽部(新潮社)」「中央文学(春陽堂)」などに限られていて、若手はまず作品をその投稿欄に出して有名作家からの評価を受けるという腕試しの場だった。ここからスタートしたのが、室生犀星、内田百閒、吉屋信子、今東光、横光利一など錚々たる作家達と聞くとこの時代の自由度の高さも感じさせられる。
こうした時代と現在のネット社会における発信構造の違いは極めて大きい。加えて、手で書くこととワープロでの記述の違い、手紙とメールの違いにも表れる。荒川は「メール」で文章を始めて受け取った時の感覚を書いている。
「メールをおそるおそる開けた。すぅーと先方の文字があらわれる。静かである。音もない。時もない。文章が生まれた瞬間に立ち会うような気分だ。古代の空気を感じた」
この文章が書かれたのは2001年である。今やAIによる文章生成にまで行きついてしまった現代の文章について、彼の感想も聞いてみたい気がする。
本書では詩・エッセイ・小説・評論など、多くの著者と作品・文章を取り上げている。私も読んだことのない作家・作品が紹介されていたり、懐かしく思い出される作家・作品もあった。高校の頃、父や伯父の本棚から引っ張り出して読んでいた内田百閒の「阿呆列車」や萩原朔太郎の「虚妄の正義」などをまた読んでみるかと思いつつ、本だけでなく父や伯父の姿が思い出される。また、1970年代前後の時期を「評論の時代」として、丸山真男、鶴見俊輔、吉本隆明など多士済々の学者や評論家を挙げている。団塊の世代の人間としては10代後半から20代半ばまでの激動の時代に、「共同幻想論」や「思想の科学・転向」など多くの評論に出逢ったことなど、自分の読書史とともに日記など書くことを習慣化してきた40年を思い巡らす一冊になった。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





