はじめての沖縄【岸 政彦】
はじめての沖縄
| 書籍名 | はじめての沖縄 |
|---|---|
| 著者名 | 岸 政彦 |
| 出版社 | 新曜社(256p) |
| 発刊日 | 2018.05.05 |
| 希望小売価格 | 1,404円 |
| 書評日 | 2018.07.24 |
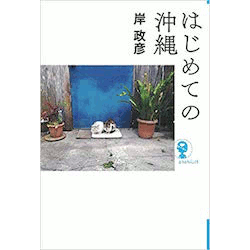
「中学生以上すべての人に。」とキャッチコピーのついた「よりみちパン!セ」シリーズの、久しぶりの新刊。以前、このシリーズから小熊英二『日本という国』をブック・ナビで取りあげたことがある。この国が抱えるさまざまな問題の本質を、中学生でも理解できるよう、コンパクトかつやさしく語ろうという編集者の意図はよくわかる。
岸政彦という名前は『断片的なものの社会学』(朝日出版社)ではじめて知った。社会学者の岸がいろんな聞き取り(インタビュー)をして、研究者としての解釈や理解をすり抜けてしまうが心に残るささいなエピソードややりとり、その「断片」をつなげながら、でも世界はそんな断片からできていることを知らせてくれる本だった。若い世代(といっても1967年生まれ)の書き手が出てきてるなあと実感させられた。そのスタイルは、『はじめての沖縄』にも受け継がれている。
那覇でタクシーに乗ったときの話が面白い。友人とタクシーに乗ったら、運転手のおじいがそわそわしはじめ、突然に路肩に車を止めた。おじいは岸たちに「もう降りましょうね」と独特の言い方をした。故障でもしたの? と聞くと、「私もう帰りたいから。ここで待ってたら、すぐ次の車くるから」と言う。岸たちは「お疲れさまでした」と言ってタクシーを降り、路上で次のタクシーを探したそうだ。
自分たちのことは自分たちで決める。このタクシーのおじいが体現しているものを岸は「自治の感覚」と名づける。「沖縄の、いつも自分流で、時には『自分勝手』でもある『自治の感覚』は、その独特の歴史的経験から生み出されたものだ。戦後のウチナンチュ(評者注・沖縄人)の生活の知恵やたくましさは、この島に正しく受け継がれていて、たとえばその自由できままな『自治の感覚』に、私のようなナイチャー(内地人)がいつも驚かされる」
こんなエピソードも紹介される。ある冬の日、著者は公共図書館で調べものをしていたが、寒い。職員に暖房を入れてくれないかと頼んだら、この建物には暖房設備がないという。昼になったので外出して席に戻ったら、足元に小さな電気ストーブがおいてあった。その職員に聞くと、「私が使っているものでよければお貸しします」と笑って答えてくれたという。
この職員のような親切は、評者のように団塊以上の世代であれば必ず思い当たる節がある。大雑把な印象で言えば1970年代くらいまで、こういう出来事は日常的にごく普通にあった。でも管理社会化が進み、なにごとにもマニュアルや細かな規則が定められるようになって社会は一変した。職員が個人の判断で融通をきかせることは、規則違反を咎められかねない。そのストーブで万一事故が起きれば、あなたのルール違反だけじゃなく図書館も責任を問われることになるから、などと。岸は言う。無意味な規則はできるだけ破ったほうがいい。沖縄には「規則をやぶることができるひと」がたくさんいる。自分で決めて、自分のルールで、他人に優しくすることができるひとがいる。
著者は沖縄でずっと、沖縄戦から現在いたる「生活史」の聞き取り調査をおこなってきた。その調査に基づいて、現在の沖縄社会の出発点には沖縄戦があり、戦後も27年間の米軍統治という本土と別の経験をしてきたことから、本土と異なる社会規範をつくりあげることになったという。
本土防衛のために沖縄を犠牲にした沖縄戦の悲惨はよく知られている。戦後、米軍の占領下、社会秩序が解体した沖縄は米軍の物資を窃盗・横領する「戦果」や、台湾との「密貿易」で暮らしを支えた。むきだしの犯罪と暴力もあった。やがて人口が爆発的に増え、那覇に人口が集中して沖縄は自前で「高度成長」し、復帰前の好景気に沸いた。戦後の沖縄社会は「沖縄の人びとが『自分たちで』作ってきた」のであり、だからこそそこから「お上に頼らない生き方」が生まれた。
もっとも、こんなふうに要約しては本書のスタイルの面白さを伝えられないかもしれない。著者は沖縄でのさまざまな経験を考えつつ、同時に「沖縄について考えることについて」考える。だから、何度も立ち止まり、行きつ戻りつすることになる。
沖縄のよいところ、沖縄的なものを称賛する。それはいかにも観光客的な目線ではないか。自由でゆるい社会規範を「本土から失われたもの」として語る。それは「植民地主義的な」視線が捏造した「理想化された亜熱帯の島のイメージ」ではないのか。たしかにそういう面はある。でも一方で、そうしたものが実在することもまた確かだ……。
沖縄が維新以来150年に経験してきたことは、明らかに本土とは異なる。規格化と均一化が進むこの国で、「沖縄は、その独特なものを色濃く残す、ほとんど唯一の場所」となっている。だからこそ、沖縄のよさや「ほんとうの沖縄」を語る「立場」にいつも自覚的でなければいけない。なぜなら沖縄と本土の関係は非対称で不平等であり、「区別」あるいは「差別」されてきたからだ。
「『ほんとうの沖縄』は、どこにあるのか誰にもわからない。でも、『ふつうの沖縄』なら、そこらじゅうにある。それは久茂地のビジネス街でも、渋滞する五十八号線でも、浦添や宜野湾の住宅地でも、コンビニやハンバーガーのチェーン店でも出会うことができる。……ふつうの沖縄こそがほんとうの沖縄であり、そして私は、ふつうの沖縄が大好きだ」
本書には「ふつうの沖縄」の断片が、たくさん記録されている。文章は中学生にもわかるようやさしいけれど、中身はとても高度なことを伝えようとしている。そのむずかしさを補うように挿入される、著者が撮影した数十点のなにげない風景が素晴らしい。「ふつうの沖縄」の空気を沁みいるように伝えてくれる。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





