敗北力─Later Works【鶴見俊輔】
敗北力─Later Works
| 書籍名 | 敗北力─Later Works |
|---|---|
| 著者名 | 鶴見俊輔 |
| 出版社 | 編集グループSURE(256p) |
| 発刊日 | 2016.10.19 |
| 希望小売価格 | 2,376円 |
| 書評日 | 2016.11.20 |
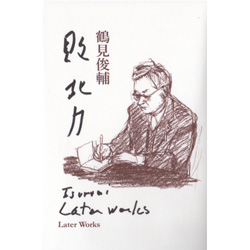
昨年7月に亡くなった鶴見俊輔の、僕はきれぎれの読者にすぎない。100冊を超える鶴見の著書・共著・編著書のうち、手に取ったのは10冊に満たない。鶴見が組織したベ平連の集会やデモに参加したこともない。それでもはじめて読んだ『日常的思想の可能性』(1967)以来、亡くなるまでずっと気にかかる存在だった。その気にかかる部分が、年とともにだんだん大きくなってきていた。
20代のころ読んで強烈に印象に残っている一節がある。吉本隆明対談集『どこに思想の根拠をおくか』に収録された、書名と同じ標題の鶴見と吉本の対談。べ平連の評価をめぐって、吉本がベ平連は社会主義に同伴するもので折衷的であり、世界を包括しうる運動ではないと批判した後のやりとりだった。
「吉本 あいまいさは残らないのだということが一つの原理としてくみ込まれていなければ、それは思想じゃない。……ぼくは思想というものは、極端にいえば原理的にあいまいな部分が残らないように世界を包括していれば、潜在的に世界の現実的基盤をちゃんと獲得しているのだというふうに思うんですよ。……
鶴見 私は思想として原理的に定立するのは、あくまでも思想のわくぐみの次元のこととして考えるんです。それを現実とからめて考えるときには、かならず適用の形態で、こういうふうにも適用できる、別のふうにも適用できると、あいまいさが思想の条件として出てくる根拠があって、そのあいまいさは思想からどうしても排除できない」
互いに敬愛するふたりが正面からぶつかりあったこの対談は今読んでもスリリングだが、僕は当時、吉本隆明の熱心な読者だったので、吉本の原理的な態度に共感をおぼえた。でも、あいまいさを残さず世界を原理的に捉えるのが思想の条件だと詰めよる吉本に対して、思想が現実とかかわるとき「あいまいさは排除できない」「自分がまちがっているという可能性は……排除できないというのが、基本的な考え方です」と低音で対抗する鶴見の姿勢もまた否定しがたかった。
ところで鶴見俊輔の読者なら、彼の書くものや発言にたびたび出てくるキーワードが「一番病」と「悪人」なのを知っているだろう。どちらの言葉も、鶴見と父親、母親との関係に根差していることを彼自身が語っている。「一番病」の知識人がこの国をだめにしているという考えは、東京帝国大学卒で「一番になる以外の価値観をもっていない」政治家だったと鶴見が評する父・祐輔との葛藤に密接に絡んでいる。
もうひとつの、「自分は悪人だから」と鶴見がしばしばつぶやく「悪人」は、子供のころ母親から毎日のように「お前は悪い子だ」と折檻されたことからきた自己認識だと、これも彼自身が語っている。万引きしたり、カフェ街に出入りしたり、自殺未遂を繰り返し、高校を退学になるといった自罰的な行為も、厳格で支配的な母親に対する反抗だったろう。そんな個人的体験に根差していることは理解できるけれど、鶴見がそれを生涯引きずるほどの「思想のわくぐみ」としての「悪人」とは、なにを意味しているのか。それがいまひとつわからなかった。
『敗北力─Later Works』は、鶴見が生前「自分の書いたものとして、自選の最後」と選んだ最晩年の23編のエッセイを中心に、単行本未収録の12編のエッセイと5編の未発表詩稿で構成されている。そのなかで、鶴見は最後まで「悪人」にこだわっている。父の呪縛より母の呪縛のほうが、晩年にいたるまで自らを拘束するほど強かったということだろうか。
「悪人」がなんなのかを考える前に、まず鶴見がその反対概念である「善人」についてどう語っているのかを見てみよう。
「人を疑わず、あらゆる場面においてその言を信用して行動することを『善人』の特徴とするならば、もともと『善人』には危うさがつきまとっている。たとえば、『善人』が『善人であること』を他の人についても強く求めるとすると、どうなるか。戦争中の日本とは、まさに国民が総体として『善人』になった時代だった」
鶴見はこうも言っている。親や先生に対してウソをつくなという教育には害があるのではないか。そのように教えられると、大人になったときあらゆる情報を国家と政府に独占され、自由に内面を操作される危険が生まれる。自分の内面にウソをつくなというのはいいが、そのことと権威に対して秘密をもつなというのは別のことだ。自分の内面を維持し権力に対して自分の秘密を守る、言いかえれば国家を疑う権利があることを子供のうちから身につけなければいけない。
こういう鶴見の考えと、子供のころ鶴見が母に対して抱いた思いを重ねてみる。ときに暴力すら用いて自分を支配しようとしてくる親や国家に対して、自分が自由だと感じられる秘密の空間を内面に確保する。親や国家が正義をふりかざすとき、それに対抗する自分のちっぽけな空間には絶えず不安とためらいがつきまとう。そんな不安定な秘密の空間を守りつづける姿勢を鶴見は「悪人」と言ったのではないか。本書に収録されたインタビューで鶴見は、こうも言っている。
「私の著作は全部、おふくろに対して『でも、そんなこと言ったって……』という言い訳、悲鳴みたいなものなんです。それと、おふくろが私のことを悪い人間って言うんだから、悪い人間なんだ。だけど、自分としては自由が欲しいんですね。自分にとっての自由とは、悪人として生きることなんです」
「悪人」について語っているのは、本書のごく一部にすぎない。この国の急ぎすぎた近代化について、自らが起こした戦争と敗戦について、広島と長崎に落とされた原爆について、東日本大震災と原発事故について、さまざまな主題を論じながら鶴見が繰り返し語っているのは「敗北」をどのように受けとめるかということだ。
「敗北力は、どういう条件を満たすときに自分が敗北するかの認識と、その敗北をどのように受けとめるかの気構えからなる」。敗北は、それ自体が負けなのではない。なぜ、どのように敗北したのかの認識と、敗北にどう対処するかの気構えがないとき、人は二度敗北する。そうならないための「認識と気構え」とは、鶴見がこの本で使っている別の言葉で言いかえれば、「自分を時代の外から見る力」ということだろうか。「私たちは時間を薄切りにしてとらえる習慣になれてしまった」とも書いている。
広島・長崎への原爆をヒポクラテス以来の自然科学の歴史のなかで考える。原発事故を日本文明だけでなく世界文明の蹉跌として考える想像力をもつ。今の日本は応仁の乱以来つづいているものとして、近隣の助け合いと物々交換から再出発する。そういう態度によって、敗北が「敗北力」になるのだと語っている。
そんな姿勢の先に、鶴見はこの国のありようをこう見ていた。「明治の大国主義のようなものを目指してはいけない。『万葉集』にあるような、それぞれのちょっと小高い丘の上から『くにみ』をするような、そんな国になってほしいと思います」(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





