ハイスクール1968【四方田犬彦】
ハイスクール1968
| 書籍名 | ハイスクール1968 |
|---|---|
| 著者名 | 四方田犬彦 |
| 出版社 | 新潮社(256p) |
| 発刊日 | 2004.2.25 |
| 希望小売価格 | 1600円+税 |
| 書評日等 | - |
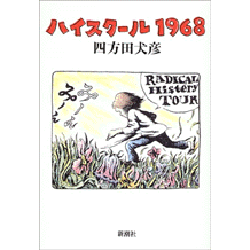
高校生だった四方田犬彦が熱中した小説、詩、評論、映画、音楽などを、本文からひろってアトランダムに挙げてみる。
「マルドロールの歌」、「悲しき熱帯」、谷川俊太郎、田村隆一、谷川雁、「死霊」、「悪の華」、ビートルズ、ドアーズ、ローリング・ストーンズ、「2001年宇宙の旅」、横尾忠則、ゴダール、ピーター・ブルック、パラジャーノフ、ブニュエル、「ガロ」、「COM」、白土三平、つげ義春、佐々木マキ、宮谷一彦、岡田史子、大江健三郎、ランボー、マイルス、コルトレーン、アルバート・アイラー、「血と薔薇」、渋澤龍彦、種村季弘、バタイユ、寺山修司、吉岡実……。
これでこの本の半ばまでに出てくる固有名詞にすぎない。文学者の名前や映画の題名はまだまだつづき、後半にはブランショやバシュラール、吉本隆明からセリーヌ(高校生がセリーヌ!)まで出てくる。
これらの固有名詞は、1960年代文化の総カタログそのものと言っても過言ではないだろう。東京の山の手に育った早熟な少年は、新宿の映画館やジャズ喫茶、gogo喫茶を巡りながら、この町にあふれていたカウンター・カルチャーや反体制文化の波に全身をさらしていた。
しかも1968年といえば、世界的に学生運動、日本では全共闘運動が最高潮に達した年でもあった。学生によるバリケード封鎖は大学から高校へと波及し、今は半ば忘れられているが、かなりの数の高校で紛争が起こった。
彼が在籍していた東京教育大付属駒場高校でも、1969年の秋、「1日だけのバリケード」が張られた。その空間に身を置くことになった四方田少年の、これは35年後のメモワールである。
「1日だけのバリケード」は新左翼のセクトに属する上級生に主導されたものだったが、その中にいたのは主に文学好きの四方田少年の仲間たちだった。しかし彼が自宅に食料を調達しに帰り、数時間して学校に戻ってみると、バリケードは機動隊導入の噂に動揺した仲間たちによって自主的に解除されていた。
そんないかにも高校生らしく幼い、1日だけの体験を境に、早熟でスノッブで悪戯好きの少年は、果てのない孤独と無力感の淵に沈み込んでゆく。
「心はすっかり乾ききって、世界全体に向けての憎悪」に満ち、学校を辞めるつもりでケーキ工場でアルバイトをしてみるが、単純労働にも未来を見いだせない。学校へ戻っても、皆、バリケードなどなかったような振りをして受験勉強にいそしんでいる。なにしろ教駒といえば、生徒の半数以上が東大に進学するエリート校なのだ。
こうしたなかで、彼はフリージャズに聴き入り、セリーヌを読む。「わたしは二十(はたち)を待たずして「心が朽ちてしまった」のである」。大学生だった全共闘世代が、その数の多さから挫折すらもある種の共同体験でありえたのに対し、彼ら少数の「遅れてきた世代」は徹底的に孤立したなかで敗北を噛みしめなければならなかった。
以後の35年、彼はこの「1日だけのバリケード」の陶酔と屈辱にこだわりつづけ、しかし表だって語ることを決してしなかった。
四方田犬彦といえば、映画、文学、漫画を、しかも日本、韓国、アジア、イタリア、アメリカを股にかけて論ずる、幅広い好奇心と行動力をもった批評家として知られる。しかし、生き生きとした好奇心と行動力の背後に、どこか冷え冷えとした視線をも感じさせるのがこの批評家の文体でもある。この本は、それがどこから来たのかを教えてくれる。
彼は自分の高校時代の体験を、こんなふうに分析している。「年少者の幼げなスノビズムを擽るには、とりあえず難解な事物に就くことが一番だった」。「(数学に熱中したことは)今日のわたしに、抽象的な理論に対する恐怖心の不在と、いわゆる「実感」への素朴な信頼への懐疑という形をとって残っている」。
音楽についていえば、前期ビートルズより後期ビートルズが好きだったというのも、いかにも彼らしい。「わたしが後期の作品を好んだのは、要するに音楽において巧みに構築されたもの、ジャンルを超えて実験的な性格をもち、文学や哲学といった文化的参照性に満ちたものに憧れるという性癖による」。
高校時代から、すでに前衛好き、実験的作品が好きだったわけだ。ここに、次のような言葉を加えてみる。
「悪虐な攻撃性の権化であるマルドロールという少年が、パリのいたるところで残酷な悪戯を繰り広げるさま(「マルドロールの歌」)を、わたしは羨望と共感のもとに読んでいた」
「実感」より構築的、実験的なものを好み、文化的参照性に満ちた(言葉で語りうる)ものに憧れ、挑戦的・攻撃的なものに共感する。ここから批評家・四方田犬彦の誕生までは、あと一歩の行程だ。
「実感」を信頼しないという四方田の文体は、だからいつでも冷たい距離を感じさせる。にもかかわらずこの本からは、ある痛苦な気配が文章の背後から漂ってくる。それは、最後に彼自身が明かしているように、2人の死者と、彼自身を含む多数の精神的死者の魂を鎮めるための書でもあるからだろう。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





