ブラッド・メリディアン【コーマック・マッカーシー】
ブラッド・メリディアン
| 書籍名 | ブラッド・メリディアン |
|---|---|
| 著者名 | コーマック・マッカーシー |
| 出版社 | 早川書房(436p) |
| 発刊日 | 2009.12.25 |
| 希望小売価格 | 2,310円 |
| 書評日 | 2010.03.07 |
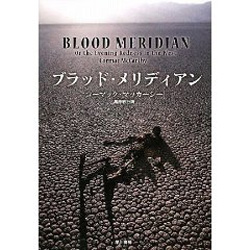
この人の小説を読むのは2冊目。最初に読んだのはニューヨークに滞在していた2年前で、『血と暴力の国』(扶桑社ミステリー)というやつだった。評判になったコーエン兄弟の映画『ノー・カントリー』の原作といえば、ああ、あれかと思う人もいるだろう。ヴィレッジの映画館でこの映画を見たとき、主演したトミー・リー・ジョーンズはじめ登場人物が激しいテキサス訛りの英語をしゃべっていて、ちっとも聞き取れなかった。アクション映画だから、アクションを追うことでストーリーはある程度理解できるけれど、大事なことをセリフでしゃべられるととたんに分からなくなる。映画のラスト近く、殺し屋がある女性を殺したのかどうか、コーエン兄弟らしくくどくど説明しないから、肝心なところが分からない。そんなことをブログで書いたら、僕の英語の実力のほどを知る友人が翻訳を日本から送ってくれたのだった。
2005年に発表された『血と暴力の国』は一応はクライム・ノヴェルの体裁を取っているとはいえ、主人公の一人称での長い語りや、純粋悪とでも言えそうな殺し屋の造形など、エンタテインメントからはみだす部分をたくさん持っていた。
『ブラッド・メリディアン(訳せば、血の子午線)』は、『血と暴力の国』に先立つこと20年、1985年に発表された小説で、著者の代表作と言われている。ニューヨーク・タイムズ紙が選出した過去四半世紀のベスト・アメリカン・ノヴェルスの1冊にも選ばれた。
そんなに評価の高い小説の翻訳がなぜ遅れたかといえば、原書を見てないのであてずっぽうだけれど、日本語に移しかえるのにむずかしい文体のせいだと思う。例えば、こんな文章がある。
「至るところで馬が倒れ男たちが這いずりまわりある男は坐ってライフルに弾をこめながら両耳から血をだらだら流し別の男たちは拳銃を分解して弾薬を装填した弾倉を取りつけようとしある男は膝立ちの姿勢で前に上体を倒して地面の自分の影を抱きしめ何人もの男たちが槍で刺し貫かれ髪をつかまれて頭の皮を剥がれ野蛮人の軍馬が倒れた男たちを踏みにじり薄闇のなかから白い顔の片眼が濁った馬がいきなり現れて犬のように少年に咬みつこうとしてまた姿を消した」(黒原敏行訳)
これでワン・センテンス。すぐ後には、この倍ほど長いセンテンスも出てくる。読点(、)も打たれてないのは、原文もカンマなしでつながってるからだろう。おまけに「野蛮人」(インディアンのこと)なんて差別語も頻出する。どんな場面かといえば、主人公の名無しの少年が白人無法者たちの「インディアン頭皮狩り隊」に加わり、その部隊が逆にインディアンに襲撃されるところ。
小説の舞台は1840年代のテキサスとメキシコ。テキサスはもともとメキシコ領だったが、アメリカ人入植者が一方的に独立を宣言、1845年にアメリカ合衆国に併合された。そのためアメリカとメキシコの間に戦争が起こり(米墨戦争)、1948年、アメリカが勝利して、現在のカリフォルニア州、ニューメキシコ州などのメキシコ領土を手に入れた。小説はこの戦争のさなか、あるいは戦争が終わった直後に設定されている。
テネシー生まれの少年が家出してテキサスに流れつき、元米騎兵隊の大尉を頭目とする「インディアン頭皮狩り隊」に加わる。大尉は知事(アメリカのかメキシコのか判然としないが)と契約して、インディアンの頭皮1枚につき100ドルの報酬を得る約束をしている(頭皮剥ぎはインディアンの残虐の象徴のように言われるが、白人も同じことをしていた)。この時代、この地域では、国家としてのアメリカとメキシコが戦い、抵抗するインディアンはアメリカ人ともスペイン系のメキシコ人とも戦い、誰もが勝手に国境を越えて動いていた。
頭皮狩り隊には元軍人、流れ者、犯罪者、黒人、メキシコ人、従順なインディアンなど雑多な者たちがいる。彼らはテキサスから国境のリオ・グランデ川を越えてメキシコまで入り込む。
もともとが私兵集団だから、隊員たちは行く先々の町や村で住民と喧嘩し、乱暴狼藉を働き、泥酔して女を追い、果ては殺し合いにいたる。仲間同士の殺しもある。抵抗しているインディアンはアパッチ族だが、おとなしく暮らしているインディアンの村を襲って皆殺しにする。そんなことで、インディアンを追いつつメキシコ軍からも追われることになる。
読む者は、主人公の少年とともにこの暴力と血と恐怖にまみれた流浪の旅に同行することになる。荒野をさまよう頭皮狩り隊はインディアンを追跡しているはずだが、なにかから逃げている逃亡集団のようにも思えてくる。
「一行は行方不明の斥候がパロベルデの枝から逆さ吊りにされているのを見つけた。両足のアキレス腱に鋭く尖らせた緑色の木の枝を通され灰色の裸の体がぶらさげられて頭の下には冷えた灰が残っていたがあぶられた頭は黒く焦げ頭蓋骨のなかで脳が泡立ち鼻の穴に蒸気が歌いながら噴き出した跡が残っていた。舌が引き出され尖った木片を刺されて引っこまないよう歯止めをされ耳朶が切り取られ腹は火打石で切り裂かれて内臓が胸まで垂れ落ちていた」
すさまじい描写がつづく。著者のマッカーシーは、白人無法者たちの残虐も、追いつめられ仲間を殺されたインディアンの残虐も、どんな倫理的判断もなしに等しく読者の前に投げ出している。会話の文章はカギカッコなしだから、地の文章と区別しにくい。会話には英語とスペイン語が入り混じり、当時は実際こんなふうに会話していたんだろう。地の文では人称がたびたび変わる。お世辞にも読みやすい文章とはいえないけれど、読む者は次第にフロンティア開拓史の現場に居合わせているような感覚を味わうことになる。
16世紀にヨーロッパの白人が北アメリカ大陸に入植して以来、各地に暮らしていたインディアンは西へ西へと追われてきた。インディアンに圧力をかけたり騙したりして土地を取り上げ、強制的に西部へ移住させる。移住先の土地でも土地投機業者が入り込み、騙して(インディアンにはもともと個人の土地所有という概念がなかった。なのに個人所有を認め、結局は土地を騙し取る)、さらに西へと追うことの繰り返し。
「インディアンの強制移住は、広大なアメリカの土地を農業のため、商業のため、近代資本主義経済の発展のために開放する上で不可欠だった」 「アンドリュー・ジャクソン(注・米国第7代大統領)は、土地投機業者であり、商人であり、奴隷売買業者であり、また初期アメリカ史上もっとも攻撃的なインディアンの敵だった。彼は1812年戦争(注・米英戦争)の英雄になった。その戦争は、イギリスに対する生存のための戦争だけにとどまらず、フロリダ、カナダ、インディアン領への新国家の膨張のための戦争だった」(ハワード・ジン『民衆のためのアメリカ史・上』)
『ブラッド・メリディアン』は、そうしたアメリカのフロンティア開発史の最終段階を舞台にしている。この小説が書かれたのが1985年であることに注意したい。ベトナム戦争が終結して10年。アメリカでは「白人ヒーローは善玉、インディアンは悪玉」といった単純な図式で語られてきた歴史を見直そうというリヴィジョニズム(歴史修正主義)の機運が起きていた。
マッカーシーの小説は、明らかにそうした流れのなかにある。ただし、単に善玉と悪玉を引っくり返しただけでもないし、インディアンを一方的に被害者として描いているわけでもない。そんな大きな歴史の流れを踏まえた上で、局面局面では誰もが加害者にも被害者にもなりえ、誰もが残虐にも崇高にもなりうる。そんな混沌としたリアリティの現場に読む者は引きずり込まれる。
そうした作者の姿勢を体現しているのが、頭皮狩り隊に同行している判事と呼ばれる男だろう。体じゅう無毛、スキンヘッドの巨漢。数ヶ国語を話し、哲学から博物学まで、深いヨーロッパ的教養をもつ。植物採集して標本をつくっているかと思えば、無慈悲に殺人を命ずる。判事はこう言う。
「戦争はなくならないんだ。石のことをどう考えるかというのと同じだ。戦争はいつだってこの地上にあった。人間が登場する前から戦争は人間を待っていた。最高の職業が最高のやり手を待っていたんだ。今までもそうだったしこれからもそうだろう。それ以外にはあり得ない」
この判事、読んでいてまるで映画『地獄の黙示録』のマーロン・ブランドみたいだな、と思った。そしてそれは見当外れの連想ではなかったみたい。
なぜなら『地獄の黙示録』はジョセフ・コンラッドの『闇の奥』を下敷きにしており、ブランドが演じたカーツ大佐は、コンラッドの小説ではクルツと呼ばれる男。彼は「蛮人ども(注・アフリカの黒人)を皆殺しにせよ!」と叫ぶ。訳者は解説のなかで、判事の造形には『闇の奥』のクルツが影響を与えているようだと書いている。ならば、小説が発表される6年前につくられた映画『地獄の黙示録』のマーロン・ブランドを、作者が見ていないはずはない。
この小説から連想した映画がもう1本ある。ダニエル・デイ=ルイスが主演した『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』。僕はこの10年のアメリカ映画のベスト(少なくともそのひとつ)だと思っている。タイトルに「ブラッド」という単語を含むことも両者に共通するけど、なにより小説に描かれる血なまぐさい西部の荒野の感触と、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』に流れる暗い基調低音が似ているのだ。
『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』の舞台は小説から半世紀後、20世紀初頭の同じテキサス。デイ=ルイス演ずる石油掘りの山師が石油を掘り当て、他人を騙し、裏切り、殺人を犯しながら大富豪にのしあがる話だった。『ブラッド・メリディアン』がフロンティア開拓史の暗部に目を据えていたとすれば、映画はアメリカ現代史の根っこにも同じ血と暴力が流れていることを抉りだしている。
そうそう。ひとつ忘れていた。この小説、頭皮狩り隊が荒野をさまよう、その風景描写が素晴しい。
「太陽が燔祭の火(ホロコースト)を燃やす西の砂漠からは小さな蝙蝠が一列に途切れることなく飛び立ち北のほうでは世界の震える外周に沿って砂埃が遠い軍隊の硝煙のように虚空のなかに漂っていた。青い黄昏が長くつづく空の下でくしゃくしゃに揉んだ肉屋の油紙のような山並みが襞の影を鋭く刻み中景には乾いた湖の光沢のある底が月面の雨の海のように薄暗く光り暮れ残る夕陽のなかで鹿の群が砂漠と同じ色をした狼の群に襲われて北に向かって駆けていた」
いったんマッカーシーの文体に慣れてしまうと、ひとつのイメージの上に別のイメージを塗り重ねるこんな重層的な描写が、とても魅力的に思えてくる。血と暴力に満ちた人間の愚行を、砂漠の赤い夕陽や黄昏が取り巻いている。そういえば、この小説には「Or the Evening Redness in the West(あるいは西部の夕陽の赤) 」という副題がつけられているのだった。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





