北支宣撫官【太田 出】
北支宣撫官
| 書籍名 | 北支宣撫官 |
|---|---|
| 著者名 | 太田 出 |
| 出版社 | えにし書房 (292p) |
| 発刊日 | 2023.10.15 |
| 希望小売価格 | 2,970円 |
| 書評日 | 2024.01.15 |
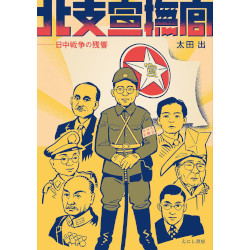
「宣撫官」の役割について確たる知識があったわけではないが、本書を読んで具体的にその任務を知る事ができ、派生的に戦中記憶の継承について考えさせられた一冊。タイトルにある「北支宣撫官」とは、日本の北支那方面軍が占領目的の広報や抗日宣伝の打消活動により敵対心を減少させて、現地民との協調の助成を任務とする「武器なき戦士」とも呼ばれていた軍属である。
宣撫官の成り立ちは昭和7年に八木沼が班長になり満州鉄道株式会社社員4名で宣撫班を組織化した。線路沿線の村を「鉄道愛援村」と指定して、村民に対し無償で穀物の種子や苗、塩・石油を配布したり医療支援といった活動をして、鉄道の防御を担わせている。こうした、満鉄を守るということからも、満鉄社員が宣撫活動を行う班を組成したというのも判るし、軍の中に組成する契機となったほど満州国のインフラを担っていた満鉄の機能も分かってくる。
中国の戦線の拡大とともに、昭和12年に支那派遣軍は内地で宣撫官を募集して、占領地における支那民衆の宣撫活動のため中国各地に派遣していった。八木沼は「宣撫官任務・目的は今次聖戦の意義を徹底し、容共・反日・反満思想を根絶し、東亜新秩序を確立するもの」と言っている。「聖戦の別動隊、宣撫官出陣す」、「皇軍第一線とともに占領部落に入り宣撫活動を担う」、「平和の戦士・宣撫官の活躍は北支八千万民衆から感謝されている」といった表現でメディアは宣撫官を報じて積極的に募集に協力していることも判る。結果、第七期までの内地採用で1770名、現地採用を含めると総数3270名が宣撫官として任命されている。
著者は宣撫官の活動実態を明らかにするために、宣撫官の生みの親である「八十沼丈夫」、宣撫官として活動し戦後13年間中国に戦犯として捉えられていた「笠実(りゅうみのる)」、中国人宣撫官の「陳 一徳」といった人々に焦点を当てて、本人の文章や言葉、報道・公的資料、家族などのインタビューなどからの記録である。当然、宣撫官の活動に対しては「物資の配布や安全の確保といった人道的行為」としての肯定的な見方もあれば、「侵略戦争の尖兵」といった否定的見方の相反する意見が存在する。著者は「どちらかのレッテルを貼るということではなく、宣撫官一人一人の歩いてきた道のりを見つめ直し、国家間戦争の中で日本軍と中国民衆の間に立たされた宣撫官の苦悩や葛藤を書き留めようと思った」と本書の意図を語っている。
「笠実」は昭和14年(1939)に旧日本軍の嘱託として宣撫官に任命されて中国に渡っている。そして、昭和36年(1961)に大戦後中国で戦犯として禁固12年刑期を終えて横浜港に降り立った。この時点は、高度成長期に向かって走り始めた日本において、笠の帰国は戦争を否応なく思い出させる話題であり、新聞各紙やアサヒグラフ等の雑誌が特集を組みインタビューなども多く掲載されたという。しかし、当時「戦艦大和の最期」を父親の本棚から引っ張り出して読むなど歴史にそれなりの興味を持っていた中学生の私にとっても笠の帰国についてそれほど記憶に残っていないのだ。この時代、団塊の世代が中国と聞くと「大躍進運動」や「人民公社」が興味の中心だったと思う。
加えて、多くの宣撫官が書き残したものは少ないという事実について、宣撫官が自らを語る事に後ろめたさが有ったのではないかとも指摘している。存命の宣撫官経験者も少なくなっている中でこうした記憶・記録を集めることの限界に警鐘を鳴らしている。
笠は戦後、宣撫官の役割を「私たち日本軍宣撫官は青年の純情と燃える愛国心を中国人民に注ぎ、東亜の建設を夢見たが、所詮は日本軍国主義者が発動した侵略戦争の走狗でしかなかった。宣撫官はけして中国民衆の味方ではなく、中国民衆にとっては、溺れる者は藁をもつかむという感覚だった」という見方を示している。
こうした点からも、本来は宣撫官に接した中国民衆の記憶を集めるべきではあるが、本書で言えば中国人宣撫官の「陳一徳」とのインタビューなどに限られている点の不十分さも課題としている。
陳は満州の日本企業で働き、昭和12年に宣撫官募集で合格して終戦まで日本軍の宣撫官として活動していた。それも「生きて行くための身近な選択」と表現している。しかし、終戦とともに日本人は大陸から撤退して行く中、日本軍に協力した中国人は「漢奸(売国奴)」と言われ、投獄・銃殺された者も少なくなかった。彼は日本軍の宣撫班の支援を受けて日本兵に紛れて昭和22年2月に佐世保に逃れることが出来た。その後、新聞社で働いた後、中華料理店を開店して今に至っている。陳は自らの宣撫官経験について「肯定も否定もしていないという」そうした感想も聞くと辛さがよりわかるというものだ。
しかし、著者が指摘している様に、一部の例外を除き、多くの戦争体験世代は「戦時中の体験」や「戦争そのもの」についてあまり語らずに世を去っている。笠もそう多くを語っている訳ではないが、宣撫官経験者の会や山西省の軍関係の会には積極的に顔を出していた。また、国の恩給対象は陸軍省の軍属であることが必要で、宣撫官は方面軍に採用された軍属で国の恩給の対象にならないことから、恩給対象にすべきとの陳情書に名を連ねるなど、地道な活動を続けていた。また、宣撫官の戦没者は靖国神社に祀られていないのだが、宣撫官たちは宣撫廟を福岡県久留米市の浄土宗善導寺に創設してその霊を祀っている。東の靖国神社、西の宣撫廟と語っているのも宣撫活動のプライドなのだろう。
また、笠にとって中華人民共和国の文化大革命は歴史の繰り返しと写ったようだ。「あなたたちは我々宣撫官が中国大陸で行ってきた工作や、大東亜共栄圏のスローガンと同様の過ちを繰り返している」と批判しているが、こうした宣撫官を経験してきた視点も活用しつつ戦後の日中関係の捉え直しも提起している。そう考えると、過酷な戦時中の体験から得られる視点は多様であるとともに、平穏な日々の経験からは想像もつかない発見や発想がちりばめられているのだろう。当然、後世の我々はその意味を丸のみにすることは無いにせよ、耳を傾けて聞いてみる価値は有るのだろう。
私の父は大正9年生まれ、昭和17年大学卒業、昭和18年徴兵。母は大正13年生まれ、二人は昭和19年に結婚している。真っただ中の戦中派だ。両親も積極的に戦中を語ることは少なかった。父が戦争に係わる言葉は「仲間の1/3は戦死した。生き残った俺は彼らの為にも一生懸命に生きなければならない」とか、「お前は死んだつもりで努力したことが有るのか!!」と息子の私を説教するときぐらいであった。今更ながら、両親の戦争の記憶をもっと聞いておけば良かったと思いつつ、居間に置いてある二人の写真を眺めている。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





