増補版 1★9★3★7【辺見 庸】
増補版 1★9★3★7
| 書籍名 | 増補版 1★9★3★7 |
|---|---|
| 著者名 | 辺見 庸 |
| 出版社 | 河出書房新社(408p) |
| 発刊日 | 2016.03.20 |
| 希望小売価格 | 2,484円 |
| 書評日 | 2016.04.19 |
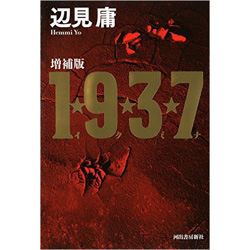
この本のタイトルは「イクミナ(逝く皆)」と読ませるらしい。1937、つまり昭和12年という年号は以前から気になっていた。というのは昭和史に関する本やエッセイを読むとき、1937年は社会の空気が戦争に向かって雪崩をうって傾斜していった年だった、と複数の体験者がそろって指摘していたからだ。
この年7月、盧溝橋事件が起こり日中戦争が始まった。もっとも、人々にとって戦争はまだ遠い外地の出来事で、戦争はすぐに終わると楽観的な空気が流れていた。しかし10月に国民精神総動員運動が始まり、新聞やラジオ、映画などメディアが動員され、全国津々浦々の町内会まで組織されて兵士への慰問、勤労奉仕、節約などが呼びかけられた。戦争は、一気に身近なものとなった。11月に日本軍は上海に上陸、中華民国の首都だった南京まで侵攻して大虐殺を引き起こす──そういう年だったのだ。
十数年前、必要があって上海に上陸した日本軍が南京を目指して進軍する過程を調べたことがあった。ある連隊の行動を追って、防衛庁が編纂した戦史はじめいくつかの記録、研究者の著作、当事者の手記や日記、新聞報道に当たり、当時80代だった元兵士にも話を聞いた。
新聞について言えば、このとき各新聞社は従軍記者を送って連日大きな紙面を割き、どの部隊が(どの新聞社が)南京へ一番乗りするかの報道合戦を繰り広げていた。紙面では、将校が常熟、無錫など占領した先々で中国兵(捕虜も含む)を何人斬ったかを誇らしげに語っている。あたかも講談でも語る調子で、誇張に満ちた、読むに耐えない記事が紙面を埋めていた。しかし、まるでスポーツ読み物のようにヒロイックな物語に仕立てられたそれらの記事からすらも、中国人が「殺(シャー)・掠(リュエ)・姦(チェン)」と呼んだ皇軍兵士の非戦闘員に対する所業の一端はうかがい知ることができた。
ついでに言えばこのとき、南京大虐殺は「まぼろし」であると主張する人たちの書いたものもずいぶん読んだ。そしてその論議の仕方に、ある共通した特徴があるのに気づいた。
上海から南京への行軍にしても南京占領にしても、日々戦闘しているなかでのことだから第三者がいるわけでもなく、確実な資料など大して残っていない。日本軍は当然のことながら自軍に都合の悪いことは記さないし、敗者は記録を残す余裕もない。南京にいた外国人の見聞にも限りがある。だから後に南京虐殺の証拠として挙げられた見聞や写真のなかには、推測や誇張、誤りも含まれている。
「まぼろし」と主張する人たちの議論は、それらの間違いをひとつひとつ指摘してゆく。一方、あいまいさや誤りを排除した上で明らかになった「殺・掠・姦」については口をつぐむ。そうした論法がメディア上で繰り返されると、あたかも虐殺はなかった「かのような」印象がつくりだされる。一本一本の木を否定することで、あたかも森は存在しない「かのような」空気が醸成される。プロパガンダの話法とでも言ったらいいか。
十数年前のそんなことを思い出したのは、従軍慰安婦をめぐる論議のなかでも似たような論法に出会うことが多いからだ(さらに脇道にそれるなら、従軍慰安婦を集めた慰安所そのものが、南京戦線での軍紀のあまりの乱れに狼狽した軍上層部が、それまで個別にあった似たような施設をシステムとして整備したものだった)。
先日も、外務省が国連の女性差別撤廃委で「軍や官憲による強制連行は確認できなかった」と説明したというニュースがあった。加害の側からのそうした発言は、仮にするにしても慰安所の設置・運営に旧日本軍が関与したこと、強制的・性奴隷的な労働があったことをまず語った上でなされるのが常識だし、国の倫理というものだろう。でも、そのような発言があったとは聞いていない。思いだせば、第一次政権のとき訪米した安倍首相も米国議会で同じような発言をして顰蹙を買った。木を否定して森が存在しないかのように印象づける論法が、一国の首相や外交官の口からすら出ることに暗澹たる思いがする。
本書に触れる前にずいぶん脇道にそれてしまった。『1★9★3★7』は、南京虐殺をテーマにしたいくつかの小説や記録といった縦糸に、中国戦線に出征した著者自身の父親の記憶という横糸をからませたエッセイ、というより自問自答するモノローグのような著作だ。
取り上げられているのは、中国戦線に兵士として従軍したり、特派員として現地に赴いた作家による次のような作品、そして上級将校の記録である。
日本軍に包囲された南京に残る中国人インテリを主人公に、彼の目から見た南京虐殺を描いた堀田善衛の長編小説『時間』(岩波現代文庫)。
出版社特派員として現地で取材し、発表と同時に発売禁止になった石川達三の(今ふうに言えば)ノンフィクション・ノベル『生きている兵隊』(中公文庫)。捕虜や非戦闘員の殺害、「生肉の徴発」という隠語で語られる女性へのレイプ・殺害が描かれる。
スパイ容疑で捕まえた農民の母と息子を日本兵の輪のなかで裸にして性交させ、あげく焼き殺した話を描いた武田泰淳の短編「汝の母を!」(webの日本ペンクラブ電子文藝館で読める)。
第十六師団第三十旅団長として南京戦線に参加した元陸軍中将・佐々木到一の手記「南京攻略記」(集英社版『昭和戦争文学全集 別巻』所収)。国際法や軍紀の乱れを気にするふうもなく、下半身をむき出しにされた中国人「女兵士」の死体を繰り返し見たことや、数千人の敗残兵・捕虜が「処分」されたことを記している。
『生きてゐる兵隊』は別にして、『時間』や「汝の母を!」は評者もその存在を知らなかった。いわば忘れられかけている作品といっていいだろう。これらは小説だから事実そのままではない。にしても、現地に赴いた(あるいは現場にいた)作家の目に真実と映ったものを描かずにいられなかった作品であることは、武田泰淳や堀田善衛の読者なら信ずることができる。
こうした小説や記録を論じ、さらに中国戦線で戦った父親になにも聞こうとしなかった自分を悔いつつ、辺見は自身にこんなふうに問う。
「一九三七年の実時間にわたしがもしも生きてあったならば、時代の空気に染まらずに、じぶんを表現することができただろうか。じぶんがじぶんであることができたか。戦争に反対することができたか。『暴支膺懲』のスローガンをはげしくうたぐったか。中国を侵略した『皇軍』の一員であったとしたら、中国人を一人も殺さずにいられたか。南京の大虐殺にまったくかんけいせずにいられたか。レイプも掠奪も放火もぜったいにしなかったか。まわりのみながやっていても、じぶんはこばむことができたか。後知恵ではない。後知恵ならば、どうとでも言える。歴史が奔流するただなかの実時間にあって、じぶんはどうふるまったであろうか」
正直に言って、本書を読みすすめるのは息苦しさを伴う。それは、ここには日本人なら目をそむけたくなる事柄が描かれているのに加え、それが著者や評者の父親世代のなした行いであること、そしてなにより「じぶんはどうふるまったであろうか」と繰り返す辺見の問いかけがあまりに重いからだ。
そしてこれは答えることが困難な問いでもある。「もし」という仮定のもとでの自問自答は、外部との通路がない分だけ煮詰まりやすい。またこうした自己存在への問いかけは、その姿勢が真摯であればあるほど答えにいたる道が細くなり、どんづまりにしか行きつかないことがしばしば起こる。辺見庸は作家として、その一本道を孤立して行くことを選んだ。それは尊敬に値する。
ただ僕らがこの本から受け取るべきは、自分をとことん追いつめるこうした問いではないと思う。もう少し広い場所で、ゆるく考えてみたい。ひとりひとりが孤立してこの問いに答えなければならない状況にいたる前にできること、その問いに直面するような事態をつくらないためにできることがあるのではないか。
戦争を体験した世代が少なくなり、彼らの書いたものも忘れ去られようとしているいま、まずは歴史を、近頃はタブーめいた空気も感じられる1937年の中国でなにが起こったのかを知ることから始めたい。僕もこの本で初めて知って、『時間』と「汝の母を!」を読んだ。この国を誇ってもいいとしたら、このように他者に対する想像力に富んだ小説を書くことができた作家を僕たちは持っていることだと思った。
「一億総活躍社会」とか「電波停止」とか「国家緊急事態」とか、1937年を思い起させるような言葉が飛び交ういま、この本が刊行された意味をそのように受け取りたい。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





