アフターダーク【村上春樹著】
アフターダーク
| 書籍名 | アフターダーク |
|---|---|
| 著者名 | 村上春樹 |
| 出版社 | 講談社(292p) |
| 発刊日 | 2004.9.07 |
| 希望小売価格 | 1400円+税 |
| 書評日等 | - |
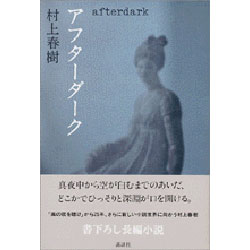
久しぶりに村上春樹を読んでみようと思った。最後に彼の小説を手に取ったのは「ねじまき鳥クロニクル」(1994~95)だから、それから10年近くたっている。以前は長編も短編も、ほとんどの作品を読んでいた。処女作「風の歌を聴け」(1979)から「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」(1985)あたりまでは、かなりのファンだったと言っていい。
最初に違和感を感じたのは、大ベストセラーとなった「ノルウェーの森」(1987)だったろうか。ひとつには、こちらが年をとったのだ。この小説あたりから、読んでいて主人公の「僕」に自分を重ねることがむずかしくなってきた。いろいろな仕掛けはあっても、つまりは恋愛小説だもんね。
僕は村上春樹より2歳年上、ともに「団塊」とくくられる世代に属している。ほぼ同じ時代を生きてきたわけで、だから「1973年のピンボール」(1980)や「羊をめぐる冒険」(1982)には、表側はそんな顔をしていないが、作品の裏には全共闘体験が隠れている(彼が具体的にどうかかわったかではなく、あの時代をどう感受したかという意味で)と感じてきた。「鼠」という副主人公が、その体験のゆがみやひずみを体現していた。
村上春樹は「風の歌を聴け」で、現実を遮断したある場所に自分の立ち位置を定めた。社会や歴史とのかかわりを絶ったその場所に佇むことによって、彼には地上では終わりなき日常の日々だけが残された。その立ち位置で「風の歌」を聴き、その微妙な変化をキャッチしながら、比喩的にいえば足元の地面を地球の中心に向かってひたすら掘削していった。
頬に日々の風を感じながら立ちつくしている自分と、地下世界に向かってひとり掘り進んでいる自分。村上春樹の小説がしばしばおしゃれな小道具と会話にあふれた日常世界と、観念的なゲームが繰りひろげられるメタ世界との往還で成り立っているのは、そういう2つの姿勢を表象しているから――というのが僕のおおざっぱな村上春樹理解だった。
そんな自分の村上像にささやかな疑いが生じたのが「ノルウェーの森」。「ねじまき鳥クロニクル」では、それがより大きな疑問に成長した。ひとことで言えば、村上春樹は立ち位置を変えようとしているのか。村上春樹は立ちつくすことをやめて、現実にもう一度コミットしようとしているのか。
「ノルウェーの森」や「ねじまき鳥クロニクル」で「満州の戦争」として語られていることが、その立ち位置の変化を表しているし、その後、サリン事件の被害者にインタビューしたノンフィクション「アンダーグラウンド」も出た。ひとりで地球の奥深く掘りすすんでいることこそが村上春樹を村上春樹たらしめているのに、今さら歴史や現実とかかわろうとするの? それは村上春樹でなくてもできるんじゃないの?
そう感じたことが間違っているかは分からないけれど、そこで僕は読むのをやめてしまったのだった。
「アフターダーク」を読んで、自分でもおかしくなるほど陳腐な感想が頭に浮かんだ。村上春樹も年とったなあ。
なにより、主人公が「僕」ではなくなっていた。「風の歌を聴け」以来、村上春樹の長編の主人公は一貫して「僕」で、それは大なり小なり作者自身の自画像として読めるものだったと思う。読者としては「ノルウェーの森」あたりから「僕」(確か30代後半に設定されていたはず)とのズレを感じていたけれど、作者にとっても「僕」とのズレが意識されていたということだろうか。
「アフターダーク」では、主人公の若い男は「タカハシ」と3人称で描写されている。そこにどんな意味でも作者を重ねることはできない。この小説の本当の主人公は「マリ」と「エリ」という2人の姉妹なのだが、かつての村上春樹なら間違いなく「僕」が登場して彼女らにからんできたはずだ。
その代わりにこの小説では、「私たち」という1人称が使われている。この「私たち」は、いかにも彼らしい仕掛けに満ちている。「私たち」が誰でどういう人物なのかは、最後まで明らかにされない。どころか、「私たち」は肉体をもたない「カメラの目」として設定されている。
「私たちの視点は架空のカメラとして、部屋の中にあるそのような事物を、ひとつひとつ拾い上げ、時間をかけて丹念に映し出していく。私たちは目に見えない無名の侵入者である。私たちは見る。耳を澄ませる。においを嗅ぐ。しかし物理的にはその場所に存在しないし、痕跡を残すこともない」
小説世界のどこにでも侵入でき、主人公たちをどの角度からでも観察できる「カメラとしての私たち」。それは、小説の背後にいてこの虚構世界を統御している作者=神のことだということもできるだろう。
今ふうに言えばメタ・レベルの侵入であり、平たく言えば作者が作中に顔を出している。それがカメラとして、さらにいえば監視カメラかインターネットの覗き部屋に設置されたカメラのように描かれているのが、彼らしい風俗の取り入れ方。
いずれにせよ、かつて「僕」に仮託されていた作者は、ここでは肉体をもたない視点とならなければ、一夜の喪失と再生をテーマとするこの小説に登場することができなかった。肉体をもった存在として描くには、「僕」は青春小説のなかでは年をとりすぎてしまったのか。
その代わりに登場するのが、「コオロギ」という「農具を入れる納屋並みに頑丈にできている」元女子プロレスラーの女性。「僕」に代わる年上の大人として、「マリ」の「自分にどうしても自信がもてない」悩みにつきあってくれる。
「そやからね、マリちゃんもちゃんとええ人を見つけたら、そのときは今よりもっと自分に自信が持てるようになると思うよ。中途半端なことはしたらあかん。世の中にはね、一人でしかできんこともあるし、二人でしかできんこともあるんよ。それをうまいこと組み合わせていくのが大事なんや」
「マリ」はこの言葉にうなずくのだけれど、書き写しながら、これが村上春樹の小説の登場人物のセリフとは信じがたかった。こういう説教口調に対して、かつての主人公ならしゃれた冗談で圧力をすっと脇にそらしてしまったにちがいないのだが。
もっとも、「コオロギ」を関西弁にしているあたりは、作者もいささか照れたのか。このセリフを東京弁でやられてはたまったものではない(村上春樹は西宮出身だけれど、これまで関西弁が登場したことはほとんどなかったのではないかな)。
無論、村上春樹らしさは、いたるところで発揮されている。「君はろくに口もきかず、ずっとプールに入って、育ち盛りのイルカみたいに泳いでいた」なんて比喩のうまさは健在だし、現実とメタ・レベルの入りまじった2つ、あるいは3つの物語が同時進行するのもおなじみ。
姉の「エリ」が眠りのなかで「別の世界」へ行ってしまうあたりはホラー映画のイメージに満ちているし、ジャズやポップスの引用も読者を喜ばせる(タイトルはカーティス・フラーの「ファイブスポット・アフターダーク」から)。
というわけで、10年ぶりの村上春樹を楽しむことはできたけれど、かつてのように興奮させてはくれなかった。村上春樹って、こんなにまともな(まともすぎる)青春小説を書くんだっけ?(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





