「美しい」ってなんだろう?【森村泰昌】
「美しい」ってなんだろう?
| 書籍名 | 「美しい」ってなんだろう? |
|---|---|
| 著者名 | 森村泰昌 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発刊日 | 2002.11.20 |
| 希望小売価格 | 1,500円 |
| 書評日等 | - |
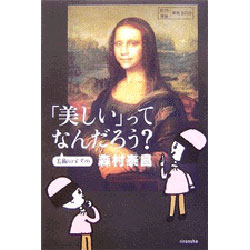
森村泰昌を一言で語ることは難しい。ある種の芸術領域のリーダーだと思うが、他に比較対象がないだけに、その森村による「中学生以上の全ての人」向けの美術指導書というコンセプトが想像しがたいというのが本書を手にしたときの実感。 理論社から出版されている「よりみちパンセ」というシリーズの中の一冊である。小学生四年生以上で学ぶ漢字にはすべてルビが振ってあるので、小学校高学年からの読者を想定しているようだが、内容は大人も十分楽しめる。このシリーズでは小倉千加子の「オンナらしさ入門(笑)」や森達也の「世界を信じるためのメソッド、ぼくらの時代のメディア・リタラシー」等。手にしたくなるような既刊が並んでいる。
本書は「美しさ」とはなにかを十章に分けてアプローチしている。当然ながら、表紙にもなっている「森村・モナリザ」の世界も色濃く出ているが、全体構成は「学校でも家でも学べない知恵満載」という狙いにそった読み物として成功している。ただ、基本的には森村のパフォーマンス(芸術活動)を面白いと感じる人向けであることは間違いないだろう。
彫刻する人を「彫刻家」、画を描く人を「画家」というように、森村は自己を「美術をする人」なので「美術家」といっている。その意味は、美術世界に近づいていく方法として「見る」「作る」「知る」いう一般的なものから、それらを超えて「なる」という方法で美術世界に近づくことこそ、森村をして「美術をする」といっていることである。例えば、ゴッホになるケースのステップを踏んでの説明や、マリリン・モンローになっていく段階写真を見せながら、「まねる」は「まなぶ」という確信を披瀝する。そうした、森村美学だけでなく、選ばれているテーマはいろいろあるが、一つは芸術と芸能の違いを語っている。芸能とは絶対的に多くの人たちにうけなければならない。べつの言い方をすると、「世界に広くいきわたらせること」と定義。一方、芸術とは、ウケなくてもやらなければならない世界。べつの言い方をすると、深く行きつくこと。
古今の芸術家、特に画家で生きているときから現在の評価を得ていた人はある種、少数であり、厳しい生活を強いられたことを考えると、森村自身どちらが良いかといっているわけでないのだが、どこか、「美術家」としては、多くの人に理解してもらわなくても良いという矜持と、そうはいっても「そりゃウケた方が良い」という大阪人のDNAも垣間見られ、両方を達成したいとの思いが素直なところなのであろう。
「しあわせ」と「ふしあわせ」についてルノワールや印象派の表現や、ムンクの「思春期」を題材として読み解いている。彼の発想に接していると、なるほどと思うところもいろいろあり、面白い。
「ノルウェーの画家、ムンクもそのひとりです。・・・・「思春期」というタイトルの絵です。一八九四年ごろに描かれています。壁に大きな影ができていますね。この黒い不気味な影は、ひとりで勝手におおきくなっていきそうな気配です。この影は絵の主人公の少女の心の奥深い暗さであると同時に、当時の不安定な社会の暗さでもあるのでしょう。ムンクの一人歩きしそうな不安な影・・・暗いですね。不安がよぎります。・・子供からおとなになってゆく過程を人間ならだれでも経験します。・・からだがどんどん変化していきます。この子は、不安を不安としてうけとめています。逃げ出してはいません。でも不安に押しつぶされそうでもあります。背後のおおきくなってゆく影がこの子をおおってしまったら、この子はあぶない。・・・精神的に病んでしまうかもしれない。そういう思春期のこわれそうな繊細な世界がここにはあるのですが、もしかしたら、このムンクの世界のほうが、ルノワール的充足感よりも、現代の私たちの気持ちにぴったりとくるかもしれません。・・より切実に「わかるなあ」と共感できるかもしれません」
森村は、「理解」よりは「共感」を大切にしているようだ。そしてその共感も「美しさ」の源泉の大きなポイントという主張。この絵の少女の影をそう読んだことがなかったので大いに共感したことも事実である。
オランダのモンドリアンの画(青と黄のコンポジション1929年)とアンリ・カルティエ=プレッソンの写真(トリエステ1933年)をならべて「美しさ」と「静けさ」について語っている。この二つの作品の特徴は水平と垂直の線が組み合わされたフォルムであることを含めて次のように説明する。
「・・もう一度垂直に突っ立った煙突を見てください。煙突のレンガの色に注目。白と黒のレンガが交互にきていますよね。白黒の二拍子なんです。・・左から右に並ぶ平屋の建物。外壁の白と扉の黒の二拍子・・・ほかにも、寝そべるおじさんのパンツに注目。なんとほそい白黒の縞模様になっている。・・この写真は水平・垂直と白黒の二拍子の骨格を持っている。おとなしいけど見えないところでシャキッとしているという感じ、それがこの写真の「よさ=美しさ」だと思うのです」
つまり、外観・見た目ではなく、事物の内部骨格というか、内面にせまる表現が「美しさ」の本質といっている。
また、メキシコの画家フリーダ・カーロを題材として、日本の美術教育の偏りについての警鐘をならしている。
「・・私がフリーダとの出会いで、まず第一に驚いたのは、自分があまりにもメキシコのことを知らなさすぎたということでした。ヨーロッパやアメリカの情報にばかり目がいって・・・「ああ、わたしは日本美術史や西洋美術史は学んできたけれど、これからは地球全体をみわたせる目を持った地球美術史が必要だ」と、・・・その驚きは、まったく異なる「美」がフリーダの世界にはあったという点でした。・・」
モナリザとフリーダの自画像とキャメロン・ディアスの写真をならべてその違いを森村流に説明している。まず「マユゲ」。時代と文化でこれほど「美」感覚の違いが出ているとの指摘。まあ、モナリザの薄マユ、フリーダの太マユ(というか、左右のマユがくっ付いて一本になっている)、そしてキャメロン・ディアスの細マユ。そして「肌の色」等。三者比較の対象の一人が何故キャメロン・ディアスかは別として、こうした指摘は、既定の「美」の構図を超えた視点であることに間違いはない。まあ、ヨーロッパと一口に言ってもその多様性を十分理解しているわけではないのだが、少なくとも日本と西欧といった視点外の広さを教える手法として子供たちにも分かりやすいとは思う。
世の中どこにも「美」があるという想いを「池辺群虫図」を紹介して最後の講義としている。ご存知、伊藤若冲が1760年代に描いたもので、一見「花鳥風月」といった風情と色使いの作品であるが、良く見ると題材はあまり一般的でない。
「葉っぱをよく見てください。虫が喰って、穴が開いたりしています。端っこがいたんで茶色く変色している葉っぱもありますね。ほかの生き物もいろいろ描かれています。セミ、チョウ、カエルというような生き物のほかに、クモが巣を張っています。トカゲやイモリやヘビもいます。ケムシもいたるところにひそんでいます。・・・」
このような池の周辺のけして、一つ一つをとると「おぞましい」と考えてしまう対象物に「美」を感じる若冲に森村は共感するという。
「「きれい」でなくても「美しい」、「ちっぽけ」でも「無限」の世界がある、みぢかなところに、すばらしい感動がある」
だから、普段の生活の中で、身近な世界で「美しい」ものを見つけられる感性を大切にというのが、本書で森村が言いたい一言なのだろう。
いくつかの、視点から「美しい」を語っているのだが、今までの森村のパフォーマンスを知る人間としては新たな森村泰昌を発見した部分もあり、楽しく読み終えたとともに、このシリーズを何冊か読んでみたいと思った。出版社の企画力も評価したい。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





