1Q84(Book 1・2)【村上春樹】
1Q84(Book 1・2)
| 書籍名 | 1Q84 |
|---|---|
| 著者名 | 村上春樹 |
| 出版社 | 新潮社(558p+506p) |
| 発刊日 | 2009.05.30 |
| 希望小売価格 | 各1,890円 |
| 書評日等 | - |
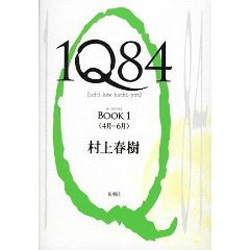
去年(編集部注:2008年)、ニューヨークに滞在していたとき、通っていた語学学校の会話クラスにイタリアから来ている学生Aがいた。アメリカに来て3年になるAは、ほぼ不自由なく英語をしゃべるけれど、授業に7割以上出席していないと学生ビザを維持できないので、そのためだけに学校に来ていた。流行の角ばった黒縁の眼鏡をかけ、髪を短くした伊達男のAは、レストランでウェイターの違法アルバイトをしながら労働ビザかグリーンカードを手に入れる機会を狙っていた。「ニューヨークにいられるなら何だってするよ」というのが口癖だった。会話クラスはAのような高レベルから僕のようにたどたどしい英語しかしゃべれない者まで、いろんなレベルの生徒が混在している。週2度の授業にAは必ず遅刻してきて窓際の席に座り、他の生徒が苦労してしゃべっているのを黙って聞いていることが多かった。何か自分が口を出したい話題になるといきなり多弁になり、とてもシニカルな意見を口にする。
Aは映画をよく見ていて、「ヴィスコンティとパゾリーニの幅のなかにある映画が好き」と言っていた。僕も週に1度はヴィレッジの映画館に通っていたから、クローネンバーグの新作は面白いぞ、こういうのもあるよ、と情報交換するようになった。
いつだったか授業中に小説の話になり、Aが村上春樹の『ノウルェイの森』を読んでいることが分かった。へえ、あのシニカルなAが村上春樹、しかもラブ・ストーリーをね、と意外だった。ミッドタウンの紀伊国屋書店に行けば彼の英訳本が何冊も平積みされていたけれど、外国人ばかり十人前後の小さなクラスで村上春樹の読者に出会うとは思っていなかった。Aが英語版で読んだのかイタリア語版で読んだのかは聞きそびれたけれど、そんな出会いがあるほどに村上春樹は広く読まれているんだな、と感じた。
授業のなかでAは僕に、「村上春樹が世界中で読まれているのはなぜだと思う?」と聞いてきた。僕はおおよそこんなふうに答えたと思う。
村上春樹の小説は1970年代以後の日本の都会を舞台にしている。70年代から80年代にかけて豊かになった日本は世界でも有数の消費社会つくりあげた。高度な消費社会、その象徴である都市に生きることには大きなプレッシャーがあって若い世代を傷つける一方、彼らは資本主義が提供するさまざまなアイテムを使いこなし日々の生活を快適に過ごしてもいる。村上春樹の小説は若い世代のそういう相反する心情をすくいあげ、それが先進国や新たに豊かになった国の若者に受け入れられたんだと思う。
むろんこんな整理された文章じゃなく、たどたどしい英語で説明したんだけどね。しかもほとんどの生徒が村上春樹を知らない教室で短く説明しなければならないので、ものすごく単純化してしまった。これでは村上春樹の小説をなにも説明したことにならないけれど、Aは納得したのかどうか、そんなもんかという表情で聞いていた。
村上春樹という名前からニューヨークのことを思い出してしまったけれど、『1Q84』だった。
『1Q84』というタイトルは、言うまでもなくジョージ・オーウェルの『1984』を下敷きにしている。『1984』は旧ソ連のスターリニズム体制に来るべき超管理社会を見た近未来小説だったけれど、『1Q84』は僕らが体験した1984年とは実はこういうものだったかもしれない、という虚構の近過去小説になっている。
空に二つの月が浮かぶ1Q84年に青豆(あおまめ)と天吾という二人の主人公が遭遇するのは、オウム真理教を思わせる「さきがけ」と呼ばれる宗教団体と、そのリーダーの犯罪である。「さきがけ」には分派として過激な武装集団があって、彼らは警察と銃撃戦を繰り広げた。架空の集団という形を取っているけれど、村上春樹が小説のなかで連合赤軍やオウム真理教といった存在について言及したのは初めてじゃないかな。
村上春樹はこれまで現実の社会的事件から遠いところで小説世界をつくってきたから(もっとも同世代から見ると、彼の初期作品は表面はそんな顔をしていないが全共闘小説とも読める、とbook naviの『アフターダーク』評で書いたことがある)、彼の小説を追ってきた者にはそのことだけでも感慨がある。
その意味で、『1Q84』は『羊をめぐる冒険』『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』といった現実と虚構を行き来する村上春樹の小説群の太い幹に属し、『ねじまき鳥クロニクル』でノモンハン戦争という歴史的事実を初めて小説に取り込んだ流れをふまえながら、彼が小説を書きはじめた1970年以後のわれわれの精神史を語ろうとした野心的な小説と言えるかもしれない。そこで考えられているのは、人間が抱えている根源的な暴力と性の暗黒面ということだろうか。
もっとも、『1Q84』はエッセーではなく小説だから、それらを普通の人文科学的な言葉で語っているわけではない。だからここから村上春樹が連合赤軍やオウム真理教をどう考えているかを取りだそうとすると拍子抜けする。彼の小説がいつもそうであるように、多義的なイメージが連鎖するアレゴリーとしてそれらを物語っているからだ。
でもそれだけの小むずかしい小説だったら、2巻あわせて200万部を超えようというベストセラーにはならない。これは同時に、『ノルウェイの森』系列に連なる男と女のラブ・ストーリーでもあるのだ。しかも小学校時代に手を握りあって別れた同級生が20年を経て惹かれあう極めつきの純愛物語である。
純愛小説でありながら、そのくせ村上春樹の小説には珍しくセクシャルな描写にも事欠かない。一方の主人公で女殺し屋の青豆は、「殺し」の仕事を終えたあと内側に鬱積したものを吐き出すようにバーで見知らぬ男(なぜかハゲ好み)に声をかけセックスを繰り返す。
もう一方の主人公で売れない小説家である天吾は、年上のガールフレンドだけでなく、自身がゴーストライターとして書き直しに手を貸した小説の作者、「胸が美しい17歳の美少女ふかえり(深キョン+サトエリ?)」ともセックスしてしまう。村上春樹の小説とは思えない頻度でセックス描写が出てくるんだけど、エロチシズムのかけらもないのが彼らしいというか。
物語は章ごとに青豆と天吾の三人称で交互に進められてゆく。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と同じ手法で、こちらは語り手が「僕」と「私」という内閉的な世界だったけれど、三人称の客観描写になった分、小説世界としては成熟しているように思う。
もっとも天吾は三人称になっているけれど、『風の歌を聴け』以来の主人公である「僕」、つまり何がしか作者自身が重ねられた人物と言っていいだろう。
売れない小説家で予備校教師として生計を立てている天吾は、週に1度会いにくる年上のガールフレンドとセックスし、「あとはひとりで部屋にこもって小説を書いたり、本を読んだり、音楽を聴いたり」する生活に「とくに不満をいだく」こともなく、「理想的な生活に近かった」とつぶやくキャラクター。これは村上春樹の小説に登場する何人もの「僕」と似た、生きる目標を持てずに時代の波にただ漂っている人間像を指し示している。
だから天吾系列の章は、1984年というバブルに向かって疾走している消費社会の只中で漂う主人公(天吾=「僕」)が、受け身のままいつしか「事件」に巻き込まれてゆくという、村上ファンならおなじみの物語として展開される。
天吾は知り合いの編集者から、ある企みを持ちかけられた。新人賞に応募してきた謎の美少女ふかえりの才能あふれるが未熟な作品「空気さなぎ」を天吾が書き直し、賞を取らせて文壇を震撼させようというのだ。この編集者は、現実に村上春樹とつきあいがありトラブルもあった編集者、故安原顕を連想させる。そんなモデル小説的な興味も読む者に持たせながら、天吾の章はリアリズム小説に近いタッチで進んでゆく。
さらに天吾の章でへえと思ったのは、これも村上春樹の小説では初めてと言っていいくらい、主人公の父親が大きな存在として登場したことだ。
痴呆になっている父親は旧満州からの引揚者で、戦後はNHKの集金人として父子家庭の天吾を育ててきた。天吾は、幼いころ「母親が父でない男に乳房を吸わせるのを傍で見ていた」という幻視に捉われている。自分はこの父親の子でありたくない、本当の父は別にいるのではないかという無意識の願望が引き寄せた「つくられた記憶」なのかもしれない。
そんな父親への嫌悪と和解が、天吾の章のサブ・テーマになっている。そういえば、村上春樹がエルサレム賞を受けたときの世界的に注目されたスピーチで、父親と彼の死に触れていたのを思い出す。いま考えれば、『ねじまき鳥クロニクル』でいきなり出てきたノモンハン戦争も、背後にあったのは父親というテーマだったのかもしれないな。
一方、青豆系列の章では、主人公の青豆は女殺し屋。しかも仕掛け人梅安ふうに細い針を使って首筋の一点を刺し自然死に見せかけて殺すという、こちらは設定からして荒唐無稽。青豆は、加害者の男に復讐する過激なフェミニスト(?)団体の元締めである老婦人から、少女をレイプした宗教団体「さきがけ」のリーダーを殺せという「指令」を受ける。
仕事の途上、首都高速の非常階段を下りた青豆が空を見上げると、月が二つ浮かんでいる。青豆は、自分が紛れ込んでしまった月が二つある非現実的な世界を1Q84年と名づける。青豆の章は、そんな幻想的なピカレスク・ロマンふうタッチで進行してゆく。
最初は互いに無関係に、しかも一方はリアリズム、他方は幻想的な世界を基調に語られてゆく2系列の物語が、やがて暗黒世界と交信する能力をもつ美少女ふかえりを媒介につながり、1984年と1Q84年が重なってゆく。そのあたりのストーリー・テリングのうまさと文章の力は圧倒的で、いやこれは興奮します。
殺し屋である青豆と、青豆から見れば少女をレイプした「さきがけ」(男女交合を即身成仏と見た密教立川流みたいな集団)のリーダー、2人の「犯罪者」が善と悪、正義と邪悪をめぐって問答するあたりはドストエフスキー的な観念小説の味わいもある。そういえば村上春樹は若いころ、フィッツジェラルドやチャンドラーばかりでなくドストエフスキーも耽読していたと、どこかで書いていた。
しかも2系列の物語が、全体としては青豆と天吾の20年越しのラブ・ストーリーになっていることが徐々に明らかになってくる。1984年に生きる天吾と1Q84年に生きる青豆は出会うことができるのか? 近過去小説のノスタルジーと幻想小説の観念性、セックス描写と現実への関心、リアリズムとピカレスク・ロマン、さまざまな要素をぶちこんで、しかもそれをラブ・ストーリーという衣でくるんでみせる。
「そう、1984年も1Q84年も、原理的には同じ成り立ちのものだ。君が世界を信じなければ、またそこに愛がなければ、すべてはまがい物に過ぎない」
殺そうとする青豆と、自ら殺されようとするリーダーの会話だ。傷ついた者と犯罪を犯した者しか登場しないこの物語が、にもかかわらず希望のほうへ反転してゆくのは、青豆と天吾が時空を超えて惹きあうラブ・ロマンスとして構想されているからだろう。
文章が明らかに変わっている。村上春樹の文章といえば、チャンドラーをはじめとするハードボイルドに学んだユーモアに満ちた卓抜な比喩にあふれたものというのが定説だった。そのお洒落な感覚が1980年代の空気に寄り添っていたことは確かだろう。でもこの小説では、そういう表現がないではないけれど後景に退いている。かわりに、着実で、噛みしめるような日本語でディテールの描写が丹念に積み重ねられてゆく。この小説が成熟していると感じられるのは、そのせいもあるに違いない。
だからだろうか? 物語の最後近く、天吾が「空気さなぎ」のなかに少女の姿をした青豆を見るあたりで僕が連想したのは、川端康成の『眠れる美女』だった。ラブ・ロマンスの希望の背後に、そんな永遠に交わらない2人の悲しみが張りついていると思えばいっそう味わい深い。
僕の好みから言えば、後半のBook2はもっと加速して結晶度をさらに高くしてほしいところだけれど、ひょっとしたらこれはBook3へとつづく助走なのかもしれないな。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





