一号線を北上せよ【沢木耕太郎著】
一号線を北上せよ
死者とともに旅する
| 書籍名 | 一号線を北上せよ |
|---|---|
| 著者名 | 沢木耕太郎 |
| 出版社 | 講談社(332p) |
| 発刊日 | 2003.2.17 |
| 希望小売価格 | 1,500円 |
| 書評日等 | - |
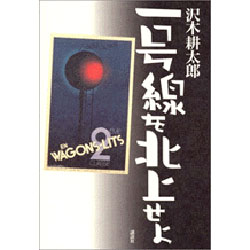
「一号線を北上せよ」というタイトルには、二重の意味が込められている。ひとつはホーチミンからハノイまで、ヴェトナム戦争のニュースや写真でなじみ深い国道一号線を北上するという、この本のハイライトともなっている物理的な旅のことである。
が、このタイトルにはもうひとつの意味がある。沢木はこんなふうに書いている。「「北上」すべき「一号線」はどこにもある。ここにもあるし、あそこにもある。私にもあれば、そう、あなたにもある」。それに加えて、沢木がここに収められた旅は常に「私の「夢見た旅」だった」と言っているように、一号線を北上するとは物理的な旅のことではなく、彼の思いのなかの「北上」という夢、「一号線」という夢のことなのである。
沢木は、その旅は「北上」ではなく「南下」であってもよいし、「一号線」ではなく「六六号線」であってもかまわないと言っているが、しかし彼は「一号線」を「北上」することを選んだ。そこに、沢木の旅の際だった個性が表れているように思える。
彼の言う「一号線」とは、僕なりに翻訳すれば、自分にとって最も大切な記憶、あるいは最も大切な夢のことだ。ここに収められた七つの旅は、そのほとんどが沢木の夢から始まる。そしてそれは、まっすぐに死者の記憶へとつながってゆく。
「解放前のサイゴン」に行きたかったという夢、あるいはロバート・キャパが生きたパリの街路やカフェをこの目で確かめたいという夢、42歳になった元チャンピオン、ジョージ・フォアマンが再び世界タイトルに挑む姿を見たいという夢、そして檀一雄が暮らしたポルトガルの寒村、サンタクルスへの夢……。
沢木を旅に誘うそれらの夢の背後には、その「妻と娘」とは知り合いながら遂に会えなかった近藤紘一、かつてフォアマンと死闘を繰り広げ、生者でありながら死者のごときモハメド・アリ、そして沢木が作品を書く過程で深く(死者でありながら生者のごとく)交わったロバート・キャパや檀一雄の記憶がある。
彼ら死者たちの記憶に衝き動かされる旅は、必然的に「北上」せざるをえない。「北上」とは、再び僕なりに翻訳すれば、死者への思いを深め、純化させることの謂であろう。北へ向かうとき、人は寒さに皮膚を外界から閉ざし、自らの思念にのみ向き合って、内部の対話を重ねていくしかない。
だから沢木の「北上」する旅は、近藤紘一やキャパや檀一雄の記憶へ近づくための儀式のようなものとなる。目的地サンタクルスへ直ちに向かうのをためらい、リスボン、ポルト、ナザレと強いられたように回り道をたどるのは、死者の記憶に対する儀礼としての動作なのだ。
この本は、「深夜特急」の続編として読者に期待されている(造本も宣伝も、そのように印象づけている)。が、沢木はそうではなく、この本は最初に意識的に書いた紀行文なのだと述べている。「深夜特急」は紀行ではなく「私」の旅だったが、この本で重要なのは「私」である前に「旅」なのだ、と。
そのことを踏まえて、しかし僕の読後の印象は、沢木は変わっていない、いや、変わろうとしても変われないのだ、というものだった。沢木の意識とは逆に、「私」の視線で染め上げられた文体は、いわば青春の文体であり、それは青春時代の旅を十数年後に記憶のなかで再構成した「深夜特急」と同じ香りを発して読者を魅了する。実をいえば、僕も沢木の文章に酔い、彼とともに「北上」する旅を楽しんだ。
沢木と同年である僕らの世代にとっては、沢木は若い世代の旅のバイブルと言われる「深夜特急」の著者というより、「テロルの決算」から「一瞬の夏」に至る見事なノンフィクションの書き手としての印象が強い。その後の「バーボン・ストリート」から「深夜特急」「檀」を経て小説にまで手を染めた彼の仕事は、頂点を極めた「私的ノンフィクション」から、もうひとつの場所へ転移するための長い遍歴であるように見える。
その遍歴は、常に文体のなかの「私」の場所に関わっている。現実の旅の記録というより記憶のなかの旅の記録であり、従って濃厚に「私」の充満する「深夜特急」と、作家の妻への聞き書きに基づき、「私」をできるかぎり無化して作家像を描こうとした「檀」を両極端として、沢木の作品は常に文体のなかの「私」の位置を探してきた。「一号線を北上せよ」も、まさにそうした遍歴の途上の一冊であり、結果は、またしても濃厚な「私」の旅だったのである。
閑話休題。「一〇一号線を南下してみた」というタイトルの本を考えてみる。幹線の「一号線」ではなく、枝線を意味する「一〇一号線」であり、「北上」ではなく「南下」であり、「せよ」という自分に対する命令形ではなく、もっと柔らかな姿勢を含むものとして。「南下」とは、寒さのなかで皮膚を閉じ、外部から遮断された自らの思念のテンションをのみ高める「北上」とは逆に、なま温かい空気のなかで皮膚がその緊張をゆるめ、自分の内側が外部に開かれてゆくといったことを含意している。
そのような旅を、僕は例えば鶴見良行の旅に見る。鶴見がそれまでのキャリアを捨てて、東南アジアのマングローブの沼地やナマコの住むマカッサル海峡、モルッカ海域への旅に出たのは、旅することによって自らを外に開き、そのことによって自分が変わっていくことをも意味していた。「マングローブの沼地で」や「ナマコの眼」は、ひと昔以上前に学術書ではあるが、旅の本として読んでもいまだにその新鮮さで僕らを魅惑し、誘惑する。
僕はこの「一号線を北上せよ」の文体に酔い、楽しんだ。しかし同時に、沢木耕太郎は死ぬまでこの濃厚な「私」の文体を続けるのだろうか、とも思った。その二律背反した思いは、50代半ばになっても沢木耕太郎の旅に惹かれ、その青春の文体に引き込まれる自分自身への嫌悪の故であるのかもしれなかった。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





