あんじゅう【宮部みゆき】
あんじゅう
| 書籍名 | あんじゅう |
|---|---|
| 著者名 | 宮部みゆき |
| 出版社 | 中央公論新社(563p) |
| 発刊日 | 2010.07 |
| 希望小売価格 | 1,890円 |
| 書評日 | 2010.09.13 |
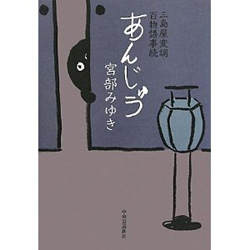
「三島屋変調百物語事続」と副題にあるように、2年前の「おそろしや」の続編だ。それにしても宮部の筆力の圧倒的な強さは何に由来しているのだろうかと思う。ジャンルの多様さだけでなく、そのボリュームも確かな実力に裏打ちされていることは十分承知しているものの、いつかその才能が枯渇するのではないかと心配するほどである。本書は、江戸は神田で袋物・小物を商う三島屋という商家を舞台としている。店の主人伊兵衛が世の中の変わった話を集めることを思い立ち、数えで18歳となった姪っ子「おちか」をその話の聞き手にするという筋立て。「聞いて聞き捨て、語って語り捨て」が話を集めるに際しての決まりごとになっているので、聞いたことを外で語ることもなければ、語るほうも何かを期待するわけではない。
例えば、なにか「物の怪」に困ったからといって上手い解決策が示されるということではない。そう割り切ってしまうと、語るほうも素直に語ることが出来て、結果として自分の心に澱んでいた想いや悩みから抜け出せることになる。教会の懺悔のような効果だろうか。一話一話は真剣に悩んだり、困ったりしている話を語るまで葛藤も面白く描かれているし、語ることによって自分の気持ちの落し処を見つけていく過程の表現も出色。所詮どんな「物の怪」や「化け物」も人間の感情が生み出して来たものだし、そこから抜け出ていくのも人間の知恵以外の何物でもないということだ。
「・・・三島屋に落ち着いて、半年が過ぎた。変わり百物語の聞き手という不思議な役目にも、『叔父さん、まだやるんですか』と混ぜっ返したりしたものの、実は興味を覚えつつあるおちかだった。人は、心という器に様々な話を隠し持っている。その器から溢れ出てくる言葉に触れることで、おちかはこれまで見たことのないものを、普通に暮らしていたなら、生涯見ることがないものを見せてもらってきた。・・・」
と、主人公の「おちか」自身の成長の描写から続編は始まる。ほかに登場するのは、おかみさんのお民、番頭の八十助、女中のおしま、丁稚の新太、「口入屋」の灯庵老人といったところ。こうした脇役に囲まれながら、年に似合わず人あしらいも上手く、聞き上手でもある。魅力ある人物としてこの娘は描かれている。
まず「お旱さん(おひでりさん)」という話。
上州のとある山里から来た平太という子供が番頭に連れられて三島屋を訪れる。ただ、平太は今まで自分の体験してきた話をすると大人たちに馬鹿にされたり怒られたりしていたこともあってなかなか話そうとしない。こんな時こそ「おちか」の腕の見せ所である。お菓子を出したり、優しく語りかけたりするとそろそろと平太が語りはじめる。
この山里では鉄砲水が多く、それを防ぐために神社を作り庄屋も農民もおまいりを怠らなかった。しかし、ある年に地震が起こり、川の流れが変わったことから鉄砲水も出なくなり、いつしか神社も荒れ果てて、誰一人神社を省みる人はいなくなった。そんなこともあり神社のヌシである「お旱さま」がお怒りになって、村では甕の水が枯れたり、池の水が干上がったりするようになった。そのヌシは女の子の姿をして平太の前に現れると「お前の身体を借りるよ」といって消えてしまう。
・・・平太は「お旱さま」とともに丁稚奉公で江戸に出てきた。しかし江戸に来て、平太の話が皆から馬鹿にされたり、戯言のように扱われることで「お旱さま」は怒ってしまっているようだ。台所の水がめは枯れるやら、花活けの水も無くなってしまうといった騒動が繰り返されたらしい。話の流れもあり三島屋でしばしこの平太を預かることとなったが、話を真剣に聞いてくれる三島屋の人たちに対して「お旱さま」はけして悪さをすることはなかった。さりとて丁稚奉公の筋を通すにはいつまでも預かっている訳にもいかない。「お旱さま」は水が好きとのことなので、主人の計らいから平太は深川の船宿で修行させることとなった。そして平太を修行に送り出したあとの三島屋ではこんな会話がされる。 「・・・・『平太とお旱さんはこれからもずうっと一緒にいるんでしょうか。いえ、一緒にいてもいいものなんでしょうかね。』人とヌシである。人と小さくても神様である。『いつかは別れることになるだろう。』と主人は言った。『あの子が育ち上がって、近くにいる、生身の女の赤い蹴出しに目を惹かれるような年頃になったらさ』神様というのは、人のそういう生臭さを嫌うだろうからね。この話の締めくくりは、まだうんと先のことになりそうだ。平太が一人前になり、彼の颯爽と操る船に三島屋のみんなで乗り込むときが来るまでは。・・・・」
次に本書のタイトルにもなっている「あんじゅう」とは、「暗獣」のこと。とある武家屋敷に隠居夫婦が住むことになった。その屋敷はお化けが出るといううわさが立ったこともあり長い間人が住んでいなかった。何カ月かたったある日、夕立の雷鳴とともにおかみさんが家の中をさっと走る黒い影を見た。気のせいかと思っていたが主人もその後、草履のような黒い物体を見る。何かがいるのだ。しかし、夫婦はそれを怖がることもなく二人の間ではこの生き物らしきものを「くろすけ」と名づけることにした。
「くろすけ」とこの夫婦の間には気持ちも通じ合うことが出来るようになる。あるとき、おかみさんがとろろ汁をつくっておいたところ「くろすけ」がいたずらをして頭からとろろ汁をかぶってしまったことがあった。驚いて物陰に隠れた「くろすけ」は痒いからかか細い泣き声が聞こえてくる。お上さんは子供に言い聞かせるようにまず井戸端にいって身体を洗うことを言いつけると、真っ黒なものはしおしおと動いて井戸端に出ていった。手桶に酢水を入れて庭先の手水鉢のそばに置いて「酢水を置いておくので身体を拭くのですよ」と優しく言って障子を閉めて座敷に戻り聞き耳を立てていると、「ペチャペチャ」と音がする。「くろすけ」が身体を洗っているらしい。こうして、夫婦と「くろすけ」の絆は強くなっていく。
あるとき、大きな物音がしてなにごとかと行ってみると、棚板が外れて木箱が転がっている。おかみさんの頭の上に木箱が落ちかかったときに「くろすけ」がとっさにお上さんに飛びついて助けてくれたとのこと。その「くろすけ」は元気なくうずくまっている。主人が「くろすけ」を抱きかかえると最初に出会ったとき比べるとずいぶん軽く、小さくなっていることに気づく。主人は考える。「くろすけ」は長年人が住んでいなかったこの屋敷の孤独が生み出したものなのだと。だから、この夫婦が住んで屋敷が孤独でなくなった今、「くろすけ」はいわば根を失ってしまったのだ。「人恋しい」という想いにとって人はそれを消す存在なのだ。皮肉である。「くろすけ」が久しぶりに出会った人であるこの「夫婦」は優しく、自分を守ってくれようとしている。しかし、人がいない暗闇だから自分は存在できる。そんな「暗獣」のジレンマがせつない話である。
どの話を取っても、洒落た、余韻のある「落ち」を付け加えれば立派な人情落語の一席になる。人間の感情に巣くう悪意や恨みといったものも主人公の「おちか」のフィルターを通して読者の心を揺する話になっている。子供向けにも仕立て直したいと思う。
そして、2年前の「おそろしや」では主人公のおちかは17歳であるが、本書では冒頭から数えの18歳となっている。この時代、数えの18-19歳ともなれば嫁入話がどんどん沸いてくる筈だ。次の作品ではおちかも二十歳になってしまう。もう三島屋のお嬢さんとして「聞き手」をしていることもなさそうだ。どんなことになるのやら楽しみなことである。まだ、残りは90話もある。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





