アメリカ 暴力の世紀【ジョン・ W・.ダワー】
アメリカ 暴力の世紀
| 書籍名 | アメリカ 暴力の世紀 |
|---|---|
| 著者名 | ジョン・ W・.ダワー |
| 出版社 | 岩波書店(204p) |
| 発刊日 | 2017.11.15 |
| 希望小売価格 | 1,944円 |
| 書評日 | 2018.02.21 |
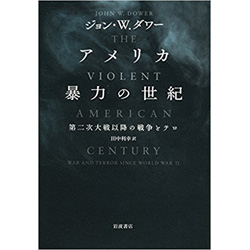
この一年間、トランプ政権の政策運営を見ていると「アメリカ 暴力の世紀」という本書のタイトルにどうしても今日的な意味を思い浮かべてしまうのだが、本書原文の最終稿は2016年9月で、オバマ政権の最終局面までのアメリカを考察の対象にしていることは確認しておきたい。もっとも、日本語版の「はじめに」の執筆時期は2017年8月ということもあり、トランプ政権に対する著者ダワーの辛辣な評価とともに日本政府の対応についても読み応えのある文章になっている。
本書のタイトルは、ヘンリー・ルースが1941年2月に発表した論評「アメリカの世紀」をもじって「暴力」という形容詞を加えたものだが、1941年といえばアメリカは経済恐慌から脱却し、第二次大戦を前にして経済的や軍事的にも自信にあふれた時代だ。その後、良し悪しは別としてアメリカは対抗できる国が無い状態で存在してきた。その間「パックス・アメリカーナ」といった大袈裟な「言葉」で語られてきたアメリカとは何なのかを、冷戦、ソ連の崩壊、湾岸戦争、9.11といった事件と時代を継続・関連した事象として詳細に分析している。その手法は国防総省、CIA、軍の現場、政府の広範な資料やデータの引用で徹底して裏付けられており巻末の引用リストも圧巻である。
第二次大戦とその戦後の過程において発生した後に大きな影響を与えた事象をダワーは二点取り上げている。第二次大戦は徹底した「総力戦」であり、アメリカを除いたすべての国々の主要都市が荒廃したことに加えて、核兵器という新しい破壊技術が開発されたこと。そして、かつての民主主義的な戦勝国が植民地を失い、複数の分断国家(朝鮮、ドイツ、中国、ベトナム)が生まれたことである。これらは大戦後も依然として政治的混迷が継続するという意味で、「遺物」が残ったという言い方をしているのだ。
米ソの二大超大国が対立していた「冷戦」時代(1945年~1991年)を多くの学者は「長く続いた平和期」と呼んでいることに対してダワーは強く反発している。確かに、世界規模の紛争の数と殺傷の数は減少したものの国内紛争等で多くの死者が出ているし、核の恐怖をダワーは「アメリカは正義感、勝利感の高揚とともに、深い恐怖と暗鬱に満ちた矛盾する側面が露わになって来た」と表現している。この恐怖感こそ、アメリカが核から脱却できず「中毒的」とまで言われている核保有量の増加だけでなく、核タブーを感じないリーダーが特定の紛争(朝鮮戦争、台湾と中国の紛争、キューバ危機、ベトナム戦争等)では核兵器の使用を考慮した事実があることや、人的・機械的ミスについては国防総省の調査から1950~1968までの間に少なくとも200件の核に係わる重大な事故があったとするデータを示して、この時期に「熱い戦争」が発生しなかったのは幸運と偶然でしかないと断じており、我々は危うい時代を過ごしていたことが良く判る。
次に、1991年のソ連崩壊とともに、アメリカは世界唯一の超大国となった。その結果、世界の全面支配は自分達の任務と信じて核兵器の廃絶どころかその破壊性能の進化に邁進していった。結果、諸外国(70ヶ国)で800以上の基地、15万人の兵員を配置し、国家軍事予算は世界の殆どの国の軍事予算を合計したものより大きいという実態は、超大国という立場そのものを抑止力に活用することなく、軍事力を強化し続けるという矛盾した戦略選択と言っていい。こうした正規軍としての軍事力だけでなく、「暗闇」的作戦、例えば代理戦争、武器輸出、テロなどを通して暴力行為を幇助してきた。それらはいつも「平和」「自由」「民主主義」の名の下に行われて来たという皮肉な言い方もダワーは忘れない。そして、9.11とそれに続く新しい暴力の時代が巡ってくる。
「アメリカ人は長い間戦争の恐怖の実感を物理的に持たなかったため、2001年のアルカイダの攻撃にどれほど異常ともいえる精神的ショックを受けたのか理解出来る。この自爆攻撃は日本軍による予告なしの真珠湾攻撃と太平洋戦争末期の神風特攻パイロットになぞらえた反応が現れた。これは誇張ではなくJ.W.ブッシュはそのようなヒステリーを現実の戦争政策にまで具体化した。」
9.11発生時「新しい戦争」という言葉がアメリカで語られたことについてもダワーの認識は厳しいものだ。それは、ベトナム戦争後にロバート・マクナマラ(‘61~68年国防長官)がその敗北について「敵の立場に身を置き、彼らの眼で我々自身を見つめ、彼らの決定と行動の背景にある考え方を理解するようにしなければならなかった」と発言していることに言及し、ゲリラやテロといった「非対称性」のある戦いにおいて、ベトナム戦争の敗北の経験を生かすことが出来なかったと断じ、9.11の対テロ戦争を開始するときに使われたアメリカ政府の公的な表現が、まるで1941年のリースの語った「アメリカの任務」と「進むべき道」を無断使用したかの様に聞こえるとダワーは指摘している。
戦後のアメリカにとってベトナム戦争の敗北は忘れてしまいたい事象として存在していたとしか思えない。評者がアメリカ資本の企業で働いていた時にベトナム戦争の傷病兵を一定率雇用する法律に従って、社内でも戦傷して腕を亡くした社員等と仕事をしたこともある。戦傷者への敬意と保護は十分感じられたものだが、「負け戦」から冷静に学ぶというのは難しかったのかもしれないし。同様に考えてみると日本においても第二次大戦の教訓をどこまで学べているのかは甚だ疑問ではある。
このテロとの戦いを通して「不安定連鎖の拡大反応」という言葉で表現された様に、21世紀の10年間で、核兵器に転用できるウラン保有国は46ヶ国、プルトニュウム保有国は13ヶ国にのぼり、非国家テロリストが核兵器を持つというリスクも加わった。このため、報復核攻撃だけに依存する抑止戦略は不十分であり、核兵器と非核兵器および防衛能力の三つを組み合わせつつ、「先制攻撃能力」を加えた戦略がアメリカの政策となったことは、世界がもう一歩終末に向けて足を踏み入れたことになるのだろう。
こうした不安定さが増加する中で2007年1月1日にアメリカの核戦略の権威者と言える4名(ヘンリー・キッシンジャー、ウィリアム・ペリー、ジョージ・シュルツ、サム・ナン)による「核兵器のない世界」と題し「人類史上で最も致命的なこの兵器が危険な人物たちの手に握られる可能性が非常に高まっている」と主張する論考が発表された。これはオバマの「グローバル・ゼロ」という核兵器廃絶スローガンに結びつくものだが、具体的に核のリスクが低下することもなく、アメリカはトランプを政治の舞台に上げてしまった。ダワーの本書におけるトランプに対するメッセージを見てみよう。
「今、多くのアメリカ人と世界の大部分がドナルド・トランプを不安の目で見ている。…彼は世界で最も強力な国家を指導するにふさわしい知性も気質も備えていないように見える。彼は読書もしない。物事の詳細を知ろうとする忍耐力もまったく持っていないし、物事の正確さや真実を尊重することもない。彼の注意力は薄弱で、英語の表現はとりわけ粗野である。…もっと具体的に言うなら、トランプの極端な言語表現と行動を好む性癖は、もともとのアメリカの気質なのである。…アメリカの軍事化と世界規模での非寛容性と暴力行使に積極的に加担してきた。このアメリカは偏狭な行為、人種偏見、被害妄想とヒステリーを生み出してきた。トランプのような扇動政治家はこうした状況でこそ活躍する」
こうした、アメリカにおける核戦略の変遷を辿ることは、アメリカそのものを理解するという意味で興味深く読んだ。しかし、その戦略は、第二次大戦後の日本の国家運営と表裏一体に近く、日本の抱えたリスクそのものでもあったはずだ。だからと言って、我が国は他国から独立して国家運営をすることは政治的、経済的にも現実的でないことは明治以降150年間変わることがない。他国との協調と協力は日本の限られた資源と国土を前提とする限り必然である。その点を捉えて、ダワーは日本の戦後の繁栄と現行憲法の密接な関係を大変重要なものと指摘している。
日本にとってアメリカは多かれ少なかれ関係を持ち続けなければならない相手であり、75年間という時間軸で歴史を理解し、未来を考える際にも多様な側面から考える切り口を提示しているのが本書である。この原稿を書いている朝刊の一面のトップ記事はアメリカの核戦略の変換が行われ、運用を拡大しやすい核の小型化を進めるという活字が躍っている。そしてこの新しい核戦略を「高く評価する」という日本政府コメントを読むにつけて「物事を詳細に知ろうとする忍耐力」を日本政府にも求めたいと思うのだ。 (内池 正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





