怒り(上・下)【吉田修一】
怒り(上・下)
| 書籍名 | 怒り(上・下) |
|---|---|
| 著者名 | 吉田修一 |
| 出版社 | 中央公論新社(上284、下260p) |
| 発刊日 | 2014.01.25 |
| 希望小売価格 | 1,296円 |
| 書評日 | 2014.04.15 |
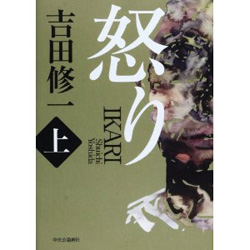
吉田修一には芥川賞を受けた『パークライフ』以来、都会に生きる男と女を主人公にした小説が多いけれど、『長崎乱楽坂』といった中上健次ふうなビルドゥングスロマンや『横道世之介』のようなユーモア青春小説、『太陽は動かない』や『路』みたいな企業小説と、ずいぶん多彩な作品をもっている。もっとも、どのジャンルの作品も典型的なジャンル小説でなく、いろんな枠組みを借りて結局は吉田修一の世界が展開されているわけだが。
もうひとつ、このところ吉田の小説で多いのが『悪人』『さよなら渓谷』といった犯罪小説だ。ここでも犯罪小説とはいえ、ミステリーのクライム・ノベルとは趣が異なる。犯人探しがテーマになっているわけではないし、『悪人』では主人公が殺人を犯した動機も心理もほとんど説明されない。主人公をとりまく人間たちの目や言葉を通して、かろうじて殺人犯の輪郭が浮かび上がるにすぎない。
新作『怒り』もまた犯罪小説の系統に属する。でもここでもまた、犯罪そのものが描かれるわけではない。その代わり犯罪の周辺に、互いにまったく無関係な数組のカップルが配置される。
八王子郊外の一軒家で若夫婦が惨殺され、浴室の壁に「怒」という血文字が残されていた。犯人は判明したが、彼は一年以上にわたって逃亡をつづけている──そんな短いプロローグの後に、三組の男と女(男)の出会いが同時進行する。
千葉県外房の港町には、新宿のソープランドで働いていたところを父親の洋平に連れ戻された愛子がいる。少し知能指数が低い愛子は、港町にふらりと現れ漁協の洋平のもとで働きはじめた田代と恋人同士になる。東京で広告代理店に勤める優馬は、会社にはゲイであることを隠して二重生活を送っている。新宿のサウナで拾った直人とゆきずりのセックスをするが、互いに気が合い、優馬は直人を自分のマンションに誘って同居することになる。高校生の泉はふしだらな母親の不始末で、母とともに沖縄の離島に流れつく。ボーイフレンドになった辰哉と出かけた無人島で、二人はキャンプしている田中と名乗るバックパッカーと知り合い、仲良くなる。
三組の男女に加えて、事件を捜査する八王子署の刑事・北見も重要な登場人物のひとり。独身の北見は公園で捨て猫をひろったことをきっかけに美佳と知り合う。北見は美佳と深い関係をもつようになるが、美佳は自分の過去を語ろうとしない。
そんな四組の男と女(男)の出会いと関係の深まりが語られてゆく。読む者はプロローグの犯罪を知っているから、このうちの誰かが殺人犯にちがいないとわかっている。ラブストーリーの名手であり、巧みなストーリーテラーでもある吉田修一に導かれて、読者は三組のカップルの行く末をはらはらしながら見守ることになる。やがてテレビで公開捜査番組が放映され、愛子も優馬も泉も、出会った恋人あるいは友人が殺人犯ではないかと疑いをもちはじめることから、物語が大きく動き出す。
この小説でいちばん多く出てくる言葉は「信ずる」あるいは「信じたい」という単語だ。
「洋平は今にも泣き出しそうな愛子の肩を撫でた。『信じてくれる?』と愛子がまた訊くので、『ああ、信じるから』と急かす。/愛子が一度呼吸して、『田代くんね、悪いことして逃げてるんじゃないの。嘘の名前を使ってるのも訳があるの』と言う。/『じゃあ、田代って名前も嘘なのか?』と洋平は訊いた。愛子が項垂れるように頷く。/洋平は全身から力が抜け、椅子に座り込んだ」
「次の瞬間、優馬の頭にある言葉が浮かんだ。/『お前のこと、信じていいんだよな?』/直人に伝えたかった簡単なことがこれだと気づく。しかし口にするにはさすがに重すぎる」
考えてみれば、人と人との出会いは不思議だ。ひと目惚れ(love at first sight)という言葉もあるように、人と人が出会った瞬間に惹かれあうことはとても多い。でもそのとき、お互いまだ相手がどんな存在なのか、どんな背景をもっている人間なのかを分かっていないのはしばしばだ。逆にいえば、自分にとって未知の存在だからこそ惹かれるという現象が生じる。手探りで相手を少しずつ知り、やがて相手を「信じる」ことでカップルが生まれる。そんなふうに互いが信頼することで生まれた関係に、殺人という犯罪が揺さぶりをかけてくる。「信じた」ものが信じられなくなる。読者には、三組の男女のうち二組は犯罪と関係ないことが分かっている。でも信じられなくなることで、どのカップルにも亀裂が生まれてくる。
愛子は不安にかられて自分から警察に電話してしまう。その一方で愛子は田代が姿をくらますことを予感して彼のバッグに現金を入れていた。
「顔を上げた愛子が、『お父ちゃん、田代くん帰ってこなかった。待ってたのに帰ってこなかったの』と繰り返す。『……私ね、田代くんのバッグにお金入れた。今朝、田代くんが出かける前に、こっそり四十万円。愛子が貯めてたお金、全部』/洋平は息を呑んだ。/愛子はもし田代が犯人なら逃がそうとしたのだ。だからこんな手の込んだことをしたのだ」
直人も優馬のマンションから姿を消す。三日後、警察からの電話で「大西直人さんという方をご存知ですか」と訊かれて慌てた優馬は、思わず「知りません」と電話を切ってしまう。その後で、自分が電話を切った行為について、また直人が殺人犯なのかどうかについて、果てしない悔恨と自問自答がはじまる。
ある登場人物は相手を信じられなかったために、大切なパートナーを失うことになる。別の登場人物は信じた相手に裏切られたために、もうひとつ別の殺人を犯してしまう。過去を明かさない美佳に「信じている」と告げた刑事の北見もまた、彼女が去っていくのを黙って見送るしかない。
『悪人』がそうだったように、ここでも殺人犯の動機や心理といった内面や、犯行の詳細は明らかにされない。犯人がなぜ「怒」の血文字を残したのかも、他人の目を通して語られるにすぎない。吉田修一が描きたかったのは犯罪そのものでなく、犯罪という触媒が社会という池に投げ込まれることによって生ずるいくつもの波紋の細部、波に揺られるいくつもの貌だったろう。
この小説に登場するカップルの誰も、相手を信じた者も信じられなかった者も、無傷ではすまない。結末で、登場人物はみな小説の発端よりもさらに深い孤独に沈むことになる。でも心優しい吉田修一は一組のカップルにだけ、傷ついた果てに温かな結末を用意した。小説を読む楽しみをたっぷり味わわせてくれる。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





