あ・ぷろぽ【山田 稔】
あ・ぷろぽ
| 書籍名 | あ・ぷろぽ |
|---|---|
| 著者名 | 山田 稔(山本光伸訳) |
| 出版社 | 平凡社(232p) |
| 発刊日 | 2003.6.9 |
| 希望小売価格 | 2200円 |
| 書評日等 | - |
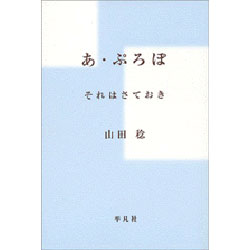
山田稔という名前をはじめて知ったのは20年ほど前のことになる。瀟洒な装幀の「コーマルタン界隈」(現在はみすず書房)という小説。おだやかでさりげない、しかし時に静かな狂気をはらみ、時に自分を突きはなしたユーモアのにじみでる文章にすっかりまいってしまった。
パリにひとりで暮らすことになった主人公が、顔を合わせることもないアパルトマンの隣人の姿を足音と気配から想像する。顔見知りになった街娼と、ふとしたことから彼女の部屋を訪れてぎこちない会話をかわす。
そんな孤独の日々のなかで、ともすれば精神のバランスを崩しそうになる主人公の心の揺れが、まるで自分の似姿のようにも思えた。パリという演劇的な舞台装置もあって、そのメランコリックな危うさが魅力の小説だった。
それ以来、本屋で山田稔の名前を見るたびに買いもとめるようになった。その多くは編集工房ノアという関西の小出版社から出ている。小説ばかりでなくエッセーや旅行記も含めて、忘れたころに山田稔の文章に出会えるのが、この20年、僕の読書の大きな楽しみになった。
最新刊の「あ・ぷろぽ」(フランス語で「ところで」といった意味)には、それぞれ数ページの短いエッセー54篇が集められている。
ここでは、70歳をこえた著者の日常や逝ってしまった友人の思い出、旅の記憶などが主に語られている。その背後からただよってくるのは、老いと死の匂いだ。短文とはいえ文章はいよいよふくよかに成熟し(などと言うのもおこがましいが)、かつての危うさが少なくなったぶん、深みをましたユーモラスな表情が好ましい。
たとえば「スーパーフレンド」と題されたエッセーは、著者が行きつけのスーパーマーケットで会う人々のスケッチ。
「(レジで相手のかごを)のぞく身はまたのぞかれる身。その日は家でひとりだったので、昼食はスーパーの弁当ですまそうと、それにこれは夕食用にとカンビール二本を加えて並んでいて、ふと後ろの人と目が合った。すると相手は嬉しそうに微笑んで、
「このお弁当とビールでお昼しやはるんどすか」
いいえ、ビールは晩に、と正そうとするのを待たず、
「よろしなあ。ひるのビールはおいしおすなあ。二本飲まはるの」」
「その人とはまた別の日にも一緒になった。私のかごにビールがないと知ると、
「今日はビール飲まはらへんの」
こんどは残念そうに、同情のまなざしで私の顔を見るのだ」
著者の住む京都の言葉、その東京弁とも大阪弁とも異なる、温かさと冷たさが微妙にブレンドされた味の複雑さが利いている。そんなふうに、何人かの「スーパーフレンド」の横顔が描かれるのだが、最後の「フレンド」はまるごと引用してしまおう。でないと、このおかしみが伝わらないような気がする。
「またある日のこと。
レジで並んでいるとき財布の中身が心配になってきて、スーパー用のがま口を開けて中をのぞく。千円札が一枚と硬貨。これでは足りそうにない。そのうち順番が来て、がま口を閉めるのを忘れたままレジの女性にその旨つげると、
「いちばん必要なものは?」
と問われ私はあわてる。そんなものあるのか、いちばん必要なものなんて。全部必要、それとも全部必要でない。おろおろしていると、すぐ後ろから女の声が言う。
「大丈夫、足りますよ」
何時の間にかがま口のなかをのぞき、かごの中身と見くらべていたのだ。そしてその人の予言通りにちょうど足りて、私は「いちばん必要」でないものまで買え、小銭が余る。
いや、おみごと。私は笑顔で後ろを振り向き頭を下げる」
「いちばん必要なものは?」と問われて、その問いを日々の営みのこととしてではなく、いわば形而上レベルの問いに重ねて受けとってしまい、うろたえる著者。内面での問いにうろたえながら、しかし外見は生活能力に欠ける男のぶざまな姿でしかない自分を、距離をおいてながめている著者。
そんなユーモアあふれるエッセー群のなかに、どきっとするようなエッセーも何げない顔をしてまぎれこんでいる。
晩酌の時間が来ても外が明るすぎるので、庭木に水をやりながら「濡れて生きかえる葉むら」や「脚のまわりに群がりながら交尾している」蚊に生を感じ、リラの木を植えてくれた友人が「「完全に気楽」な世界の住人」になってしまったことを思う「酒待つ間」。
「物置の奥に古い番傘を見つけた日の夜」、番傘をさして散歩に出、その傘にまつわる家出娘との思い出が稲妻のように胸に去来し、記憶のなかの娘の声と現実の野良猫の声とが重なって、気がつくと野良猫を拾いあげている「番傘」。
いずれも、じわりと胸に応える重みをもっている。また、茨木のり子の詩集「倚りかからず」を評して「どやしつけられたようだ。詩人は昂然としている」と述べた朝日新聞の書評に違和を感じ、「作者は昂然と言い放ったのではなく、みずからに言い聞かせるように小声でつぶやいたのであろう」という言い方のなかに、この人の生への姿勢が垣間見えたりもする。
「茨木のり子の詩集の成功に水を差そうというのではない。自立の精神は立派だと思う。ただその気概をこうもまともに、こうもわかりやすくでなく、もっと屈折し言いよどむ、しなやかな言葉で表現してほしい。「いちばん大切なこと」も、言い様次第で詩にもなれば道徳にもなる」
読んでいていちばん嬉しかったのは、最後にかつての「パリもの」を彷彿させる旅のエッセーが3篇収められていたことだ。
「私は美術館を敬遠して人通りの少ない裏街をさまよい歩き、疲れると静かなカフェで憩った。そこが、街のカフェが、私の美術館だった。 あきれるほど長い日の暮れ落ちるのを待つ間、私の食前酒は一杯ではとどまらなかった」
カフェのテーブルに座り、食前酒をなめながら暮れゆくパリの街を飽かずながめている著者の姿は、その甘さも苦さも含め、いかにもこの人にふさわしい。僕も食前酒を片手に、本棚の「コーマルタン界隈」を、何度目か楽しむために探しにいこう。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





