不適切な昭和【葛城明彦】
不適切な昭和
| 書籍名 | 不適切な昭和 |
|---|---|
| 著者名 | 葛城明彦 |
| 出版社 | 中央公論新社(232p) |
| 発刊日 | 2025.05.09 |
| 希望小売価格 | 990円 |
| 書評日 | 2025.09.18 |
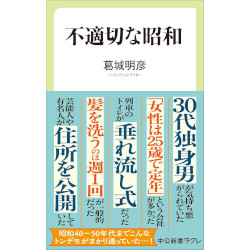
今年は昭和100年とか戦後80年と称して時代を振り返るメディア記事、テレビ番組が多い。一言で昭和と言っても社会的な視点で分けて見れば戦前・戦中の20年、戦後の混乱から高度経済成長をとげた30年、そして低成長とバブル崩壊にいたる15年に分けて考えられると思う。本書は「不適切な昭和」と題して、昭和40年代から50年代(1965年~1985年)を中心にトピックスを描いているのだが、昭和と現代の常識や文化の変化を作っているのはパソコン、携帯、スマホの普及であり、社会構造としては「一億総中流」から「格差社会」への変化が原因の中核と見ている。タイトルの「不適切」という言葉の通り、今から考えれば驚くような状況もあったが「三丁目の夕日」に描かれた様な昭和の良さもあるわけで一方的に「不適切」と決めつける必要もなかろうと考えるのは団塊の世代として昭和を生きてきた私だからこその感覚かも知れない。
昭和22年生まれの私の昭和観は小学校から大学時代(昭和29年から昭和45年)の東京の城北地域(巣鴨・滝野川・王子)での好奇心旺盛時代の生活体験によるものである。それ以降の就職(昭和45年)、結婚(昭和46年)、子供の誕生(昭和47年)といった時期の20年間は社会の変化に目を配る余裕もなく生きていた。
著者は年齢を開示していないが、本書を読む限りでは私より10才くらい若い人なのではないかと推察している。その年齢差からの意識ギャップもところどころで感じられるのも面白い点だ。本書では昭和を語る視点として、社会、学校、家庭・職場、交通機関、女性、メディア・芸能という六つの分野に分けて、今から考えれば違和感のある、社会常識が取り上げられているのだが、同時代人としてはそうだそうだと思う部分もあれば、まったく個人的には意識していなかった事柄もあり見方は様々と思う。ただ取り上げられている多様なテーマから自分自身の思い出の引き出しをどんどん開けていくという楽しさを満喫する読書になった。同時に雑学的にいっても「不適切」の中に含まれる「楽しさ」も感じながら若い人達にも読んでほしい。
本書では130程の不適切だった事柄が語られているが、その中から特に思い出深いものの記憶を掘り出してみた。当然「たばこ」が取り上げられている。今では考えられないが鉄道の列車、飛行機、飲食店、映画館など煙草はどこでも吸えた。かく言う私も学生時代に格好を付けてジャズ喫茶で洋モクのゲルベゾルテや缶入りピースを吸っていたが、サラリーマンになると缶ピーを持ち歩くわけにもいかずロングピースに代えて58歳まで吸い続けたが、禁煙したのは健康のためと言うよりは吸う場所が少なくイライラしたくないという理由である。
また、下水道が整備されておらず、工場汚水や下水を河川に流していたため「川の汚染・悪臭」がひどかった。経済成長と共に起きた隅田川、多摩川の汚染などの公害問題も昭和の特徴的なものだ。また、「バキューム・カー」もこの時代の排泄物汲み取りの象徴であるが、それ以前の私の幼稚園時代は各家庭の便所は汲み取り式で月に何回か汲み取りに来ていたのは、牛に肥桶を幾つも載せた大八車を引かせて、各戸に汲み取りに来ていた。私の住んでいた東京の下町でも普通の風景で身近で動物達が仕事をしていた時代である。
「町中がこどもだらけ」という点も確かに私が昭和29年に入学した区立小学校では教室が足りず、一学期は一年生を午前組と午後組に分けての所謂二部授業だった。二学期には新校舎も完成して通常時業になった。ベビーブームといわれた我々の世代の象徴的な思い出だ。一クラス55名で6クラスの学年だったが、同じ小学校が今は一学年一クラス30名で4クラスと言うから1/4ということになる。こんな状態なので「受験戦争」と言う言葉も必然的に生まれてきたと言える。ただ、当事者の私としては倍率に驚くこともなく、慣れてしまっていたというのが本音である。
「電車の中で赤ちゃんに授乳するお母さん」と著者が指摘している通り、山手線の中でも堂々とオッパイを出して授乳するお母さんは居た。ただその風景も昭和40年までで、著者の言う昭和50年の頃はもう見掛けなくなったと思うのだが。
また、「ラッシュ時間帯が弱肉強食の世界になっていた」というのもあの頃の国鉄の混雑を考えると尤もだ。ラッシュ時は「押し屋」と呼ばれた職員やバイトがホームに溢れる乗客を車内に押し込んでいた。乗車率300%と言われていた時代、確かに弱者はとてもラッシュ時は乗れなかったと思う。「駅にたん壷があった」とかいろいろ昔を思い出させてくれるが、今と全く違う構造は客車の乗降扉で、その開閉は手動だった。列車がホームを走り始めても乗客は「客車の扉を開けて飛び乗ることが出来た」。まさにちあきなおみの「喝采」の世界である。また、列車トイレの排便は線路にそのまま垂れ流しで撒き散らして走っていた。近辺のお宅はひどく迷惑だったと思う。「公害」ならぬ「黄害」と呼ばれていた。若い人が聞けば明らかに不適切だったと指摘するだろう。
「ラジオの深夜番組を聴いていた」というのは納得。高校生時代まではラジオは24時間放送ではなく、深夜午前2時頃には終了していた。勉強と称して机に向かってはいるもののトランジスターラジオでイヤホンをつけて聴いていた。ラジオ関東の「ポート・ジョッキー」、「ミッドナイト・ジャズ」、ニッポン放送の「星に唄おう」、ラジオ東京の「ミッドナイト・ストリート」は「今日から明日への曲がり角、ミッドナイト・ストリートです」で午後45分に始まり、「今日の話は昨日の続き、今日の続きはまた明日」と午前0時15分に終わる30分番組。語りと歌の番組を聴いていた。懐かしい思い出である。
「大学では学生運動が盛んだった」というのも団塊の世代でセクトに属さずノンポリ・ラデイカルとしては「盛ん」ではなく「当たり前」だった時代だった。4年間の内、1年間位は学校が封鎖されていたり、授業が実質行われていない期間が有ったと思う。
職場(のん気なようで案外地獄)については「終身雇用」「年功序列」「長時間労働」というキーワードは一般的にはそうだったと思うが、私は昭和45年に外資系のコンピーター会社に入社したこともあり、伝統的な日本企業とは風土の違う組織だった。「年功序列ではなく実力主義」だし、「終身雇用」を保証するものではないが、社員とその家族を会社全体のファミリー的な扱いで「就職」というよりも「就社」感が強かったと思う。ただ「長時間労働」は著者指摘の通り不適切な昭和そのものだった。都銀を担当し、朝から晩までお客様のシステムセンターで仕事をしていたし、年末・年始や連休はシステム更改の狙いの期間で休むこともできなかった。また、「セクハラがほったらかしだった頃」と言っているが、男女格差はない会社だったのであまり納得感はないし、女性活用を推進するために時として逆差別があったくらいである。そうした職場からは著者の言う「女性が女言葉を多用していた」とか「女性は25才が定年」といった感覚は全くなかった。
そうした職場の中で昭和を象徴するものは何かと考えると、部下の結婚式で頼まれ仲人を12組した事だと気付く。今となっては頼まれ仲人など死語だろう。昭和は遠くなりにけりである。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





