ジャズ昭和史【油井正一】
ジャズ昭和史
| 書籍名 | ジャズ昭和史 |
|---|---|
| 著者名 | 油井正一 |
| 出版社 | DU BOOKS(670p) |
| 発刊日 | 2013.08.09 |
| 希望小売価格 | 3,990円 |
| 書評日 | 2013.10.21 |
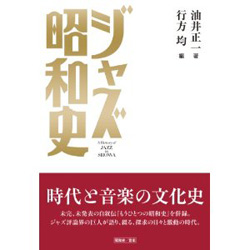
ジャズファンであれば油井正一の名前はジャズ専門誌のスイングジャーナル(SJ誌)やレコードのライナーノーツで目にし、ラジオの音楽番組で独特な語り口を耳にしてきた。評者が油井正一の文章や声に接したのは高校生の頃、半世紀前の話だ。その油井は1998年6月、享年79歳で世を去った。死後、彼が残した膨大なジャズに関する資料や原稿・草稿・ノートなどは母校である慶応義塾大学のアート・アーカイブスに収蔵され、その活動の成果も踏まえながら本書が作られている。
大きく二つの柱で構成されていて、ひとつはSJ誌の1987年2月号から1988年12月号にかけて連載されていた「ジャズ昭和史」の再録で、もう一つの柱は1990年ごろから執筆を始めたと言われている「自叙伝・もうひとつの昭和史」である。この「自叙伝」は評者も初見であった。これは出版社の依頼で書かれたものではないとのことであるが、未完の状態の原稿や草稿として残されていたものを編者行方がまとめたものである。その経緯は本書に詳しく述べられている。
さて、SJ誌のジャズ昭和史では「語り下ろす」という言い方がされている。それは、油井が語り、行方がそれを書きとめていくという手法なのだが、こうした表現方法をなぜ採用したのか評者は気になっていた。たまたま行方にそのあたりの経緯を聞く機会があった。答えは、油井の「生の語り口」を表現したかったとのこと。語り口の独特な味を残したいという意図はよくわかる。「語り部」というか「啓蒙家」としての発信力は秀逸であっただけに、本人も編集する側もそれを前面に出すという戦略を採ったということだろう。一時期、その語りの上手さにより、ラジオを中心とした音楽番組や情報番組に多く出演していた油井の面目躍如といったところである。
また、この連載を「個人的なジャズ昭和史」であると第一回で執拗に語っているのもポイントの一つである。日本のジャズ史の語り部として最適任者であると自他共に認識されていたと思うのだが、あくまで私見であると繰り返すところに油井の真面目さと謙虚さが現れている。同時に、編者行方の「Jazz史はあったがJazz受容史はなかった」という思いと、油井が歩んだ道こそ「日本におけるJazz受容史」そのものであるという認識が、この企画を成り立たせているのも事実である。
23回にわたる連載の内容は、戦前・戦中・戦後という各時代において、日本でジャズがどのように聴かれ、そして広がっていったかを自らの体験として語っている。そこから読み取れることは、限られた情報や音源しかない昭和十年ごろから、慶応の学生時代に映画とジャズに明け暮れていた生活だったことが濃密に語られていて、いつの時代も若者の興味の対象がジャズ(音楽)と映画(映像)のセットなのだと実感させられるとともに、その時期は、日本にジャズが紹介された黎明期でもあり、先人としての苦労と楽しさの両面を十二分に味わった時期だったということが良くわかる。
その時代特性としてはジャズに接しようとするとレコードというメディアに依存せざるを得なかった時代であるということだ。それだけに輸入された貴重なレコードを介してジャズと向き合うという状態は戦後の日本のジャズ喫茶を生み出した原点でもある。そして、戦後の駐留軍とともに怒涛のように入ってきた軽音楽・ジャズはその大衆化も推し進めつつ、以降1960年代半ばまでの日本におけるジャズは大きな展開をとげ、レコードとラジオというメディアに加えて、米国からの多くのミュージシャンが日本を訪れ直接彼らの音楽を体験できるようになっていった時代だ。この時期こそ、「啓蒙家」油井正一が多角的に活躍していた時代といえる。
1960年代半ば以降は、ジャズ表現も多様化し、新しい時代の表現者(プレイヤー)や多くの評論家が各々の立位置でジャズを語り始めて行った。最終の第23回(1988年12月号)の表題が「ジョン・コルトレーン以降」と題されているものの、ジョン・コルトレーンの1966年7月来日公演について語られ、1970年代前半のジャズ・シーンが多く語られているのも象徴的である。1970年代以降は「ジャズの不遇時代」という言い方を油井はしているが。それは、本来アメリカのジャズ・シーンの低迷を語っていると同時に、すでに日本においてもジャズが社会におけるビジビリティを失いつつあった時代でもある。そんな足音が聞こえてくるような最終回である。
「語り下ろし」とともに対談形式による回もあり、ジョージ川口、秋吉敏子、レイモンド・コンデといったジャズ・プレイヤー達、音楽業界人として、日本コロンビアやラジオ東京(今のTBS)開局とともに放送界に転進してジャズをはじめとした音楽番組制作に携わった石原康行、新宿のジャズ喫茶としてその名声を誇ったDIGの店主・写真家の中平穂積、ジャズ評論家仲間として牧芳雄、ジャズ・ファンの代表というか日本で初めて大学でジャズの講座を開催したときの慶応大学の学生代表者であった中村宏、といった人々との対話が掲載されている。こうしたメンバーの選択もまた興味深いところである。
戦前から戦後という時代背景の日本のジャズ・プレイヤーとしてジョージ川口、秋吉敏子、レイモンド・コンデという人選に異論は無いにしても、1965年末にバークレーから帰国した渡辺貞夫のその後の活躍と貢献を考えると対談相手として加えなかった理由も知りたい気がする。また、ジャズ評論家として、もし1988年の時点で植草甚一が存命であったら、牧に加えて植草とも対談をしたかったのではないかなど興味が湧くところである。そして、中村宏氏は1955年に慶応大学でのジャズ講座(全八回)を開催した責任者だが、この講座は油井,牧という慶応大学出身の評論家たちも企画段階から参加しており、大橋巨泉や福田一郎といった当時の若手・中堅の評論家たちも聞き手として講座に出席していたということからも、日本のジャズ史における大イベントであったことが想像できる。
それも慶応大学を核とするコミュニティーの協力成果といえる。こうした活動を通して中村氏は慶応軽音楽鑑賞会(KKK)を立ち上げ、NHKが所有していたレコードのディスコグラフィを作り、在京の各大学のジャズ鑑賞団体との交流などもリードしていったことなど、KKKが日本のジャズ受容史において果たした役割を油井が評価していたことが中村氏との対談に現れている。しかし、その伝統あるKKKも1980年代には実質休会状態にあったということも二人の間で語られている。このことは、ある大学のジャズ同好会が会員を集められずに衰退したという事実に止まらず、ジャズという音楽表現が多くの若者からの共感を得られなくなっていったことや、音楽表現の広がりによってジャズというジャンルの定義さえ難しくなっていったという状況が大きな要素であり、2010年にはスイングジャーナルの休刊という象徴的な事態を迎えることになる。
自叙伝については、油井の実業家としての姿を興味深く読んだ。油井家は福島県福島市の絹問屋として活躍していたと理解しているが、戦後の繊維産業の衰退と流通経路の再編成により、多くの問屋や商社が姿を消していった時代である。多かれ少なかれ油井に代表される戦中派世代が背負った共通の苦労でもあるのだが、戦争中は兵役に駆り出され、戦後は経済の混乱の中で生きていくという苦闘の連続である。しかし、そうした中でも油井正一は素封家に生まれ、高等教育を受けた知識階級としての闊達さと、若き日に映画やジャズといった先鋭的な文化に接してきた経験から、戦後の経済的・文化的な激変にも柔軟に対応出来たのではないかと推察できる。その「柔軟さ」と一方で「妥協しない信念」が油井の中で微妙に絡み合っている様がこの「自叙伝」から見て取れる。軽妙な油井の語り口だけに気を取られていると彼の本音を見間違えそうである。しかし、残念なことに、この自叙伝は未完である。まだ伝えたいことが何なのか。それを探る手立ての一つが慶応大の油井正一アーカイブスだろう。本書は読み手に対してそんな挑戦を仕掛けているような気がしてならない。
評者は1966年から1970年までの4年間、慶応軽音楽鑑賞会(KKK)に籍を置いていた。そんなこともあり、いささかバイヤスの掛かった読み方になっている。しかし、本書に表現されている時代の一部でも共有して過ごした人にとっては自分の経験や体験を加えながら各々が自分なりのジャズ受容史を作り、楽しむことが出来るはずだ。また、時空を共有したことのない、より若い世代の読者が「油井正一」と「ジャズ昭和史」を「語り下ろし」によって体感することによって、「油井正一」や「ジャズ」や「昭和」といった点で、何か新しい興味を持ってもらえれば本書としては大成功なのではないかと思っている。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





