醤油 (ものと人間の文化誌 180) 【吉田 元】
醤油 (ものと人間の文化誌 180)
| 書籍名 | 醤油 (ものと人間の文化誌 180) |
|---|---|
| 著者名 | 吉田 元 |
| 出版社 | 法政大学出版局(269p) |
| 発刊日 | 2018.03.09 |
| 希望小売価格 | 2,808円 |
| 書評日 | 2018.05.20 |
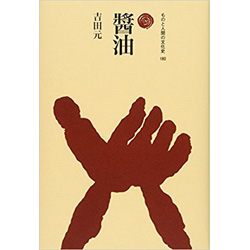
古代から現代まで日本における「醤油」の歴史を辿っている一冊。加えて、アジア各国における「醤油類」の製造についても俯瞰していて、広範囲な醤油文化を描いている。技術に重点を置いた内容なので、詳細な醗酵のメカニズムや製造プロセスの説明など、読み手の興味によって、選択的な読書をしても良いと思う。醤油の歴史についての好奇心を満たしてくれる十分な内容になっている。
いうまでもなく、醤油は日本で愛されて来た発酵調味料。その理由として、温暖湿潤な気候に支えられた農耕文化のわれわれ日本人の食生活は穀物中心の植物性タンパク質を大量に摂取するため。塩に頼った味付けが必要だった。過去においては、こうした日本型の食生活の欠陥として動物性タンパク質の摂取不足と塩分の過剰摂取が指摘されてきた。最近はその日本食は健康食として世界からもてはやされているというのも皮肉なものである。要すれば、何事につけても過剰摂取やバランスの崩れが食生活として問題が有るという事なのだろう。
日本農林規格(JAS)では「醤油」ではなく「しょうゆ」とひらがな表記されているが、大豆、小麦、食塩を主たる原料として麹菌を培養したものに食塩水を加えたものを醗酵・熟成させてえられた青澄な液体調味料と定められている。また、「醤油様調味料」として「魚醤」を含めた規格も定められている。こうした醤油類を石毛直道が提唱した「うまみ文化圏」という考え方で解説している。日本から朝鮮半島、中国大陸南部にかけての北東アジアは穀物を原料とした「穀醤圏」。一方、インドシナ半島、フィリピン、インドネシアなどの東南アジアの国々は魚を原料とした「魚醤圏」に色分けされている。「醤」の二大潮流の一つである「穀醤」の代表が醤油ということになる。
古代より中国からは様々な大豆醗酵食品が日本に伝えられたが、その中で日本人の嗜好に合う旨みのあるアミノ酸を多く含むものとして醤油が残った。室町・戦国時代には醤油づくりが始まり、奈良興福寺の「多聞院日誌」(1478~1610)には1565年に最初の醤油仕込みの記録があり、「本朝食鑑」(1697年)に記載されている醤油製造の原料、大豆、麦、塩、水の比率を比較して見ると、その比率は驚くほど似ていることが判る。醤油については極めて安定した製造法が確立していたと見ていいのだろう。
醤油の作り方の特徴として、微生物を活用した醗酵、圧搾のプロセス、火入れといわれる独特なプロセスがある。これは85度前後で30分ほど温めることによって、殺菌をし、酵素タンパクの活性を失なわせ、滓の除去をおこない、そして「火香」といわれる香ばしい香りがつき赤みのある色調に変化する。こうして醤油には300種以上の香り成分が含まれて完成する。
こうした「醤油」を消費者が選ぶポイントとして「醸造によって作られる、後味の良い、複雑な味の調和」という調査コメントが紹介されている。しかし、こう表現されること自体、醤油が近代工業化していく難しさそのものを表現している。すなわち、「醗酵のメカニズムを人工的に再現することの難しさ」を端的に表している。
現代の醤油は生産の84%という圧倒的な量を「濃口醤油」が占めていて、「うすくち醤油」「たまり醤油」「再仕込醤油」「しろ醤油」といったものがある。各々「うすくち醤油」は小麦の焦がし時間が短いことで色の淡い醤油だが、食塩濃度は濃口醤油(16%)に比べて19%と高い。「たまり醤油」は小麦を使わず、大豆と食塩だけで濃厚な醤油。照りが良いので煎餅や佃煮に使われる。「再仕込み醤油」は一度絞った醤油に麹を仕込むことで、香・味ともに濃くなる。「しろしょうゆ」は原料は殆ど小麦で、糖分が高く甘口で色調は白っぽく茶碗蒸しなどに使われる。
こうした、色々な特徴を持った醤油があるが、日常生活で全ての醤油を使い分けるという家庭は無いだろうと思うし、多くて二種類ぐらいなものではないか。江戸期になると生産状況は関東の濃口醤油、関西の淡口醤油という特徴も明確となり、現代においても関東と関西の嗜好の違いとして明確になっている。
産業と言う視点で見ると、醤油業界(醸造業界)は興味深い。醤油業を始めとして江戸幕府に於いては統制のための株仲間という制度があった。幕府や藩に冥加金を上納する見返りとして、「株仲間」として認められ製造・販売の権利を保障されていた。こうした業界は酒、度量衡、質屋、両替商などがあったと聞いている。維新後も、明治政府にとって有力な税収源として醤油も税収の一翼を担っていた。明治4年では、醤油醸造の免許料は一両一分、免許税は働く人一人につき三分、醸造税として毎年の販売金額の0.5%が課されていた。その後も醤油税は続き、明治18年に製造所一カ所につき5円、醸造石高の一石あたり1円の税金が課せられていた。こうした醤油税も大正15年に至って廃止されている。
製品としての変化を見ると、昭和初期に陸軍の野営や海軍軍艦で利用するために、携行の落差を確保するために醤油の粉末化が行われ、貴重な飲料水の節約の観点からは「無洗米」の開発も行われたのはこの時期と言われている。こうした技術は戦後のインスタント食品の開発の原点となったという指摘は、新たな視点として面白く読んだ。
最近は特に、家庭用醤油の消費が減少し、1985年から2015年で半分になったという。これは、外食の普及、減塩化の風潮、ドレッシングの普及。麺つゆやポン酢など、今までは家庭で作っていたものを製品購入することが普通になったことなどが消費低迷の流れを作っており、醤油メーカーは醤油自体の販売だけでなく、派生商品を増やしてきているのも大きな変化である。
変化の歴史で一番興味深いのは販売容器の変遷である。木の樽に始まり、陶器、ガラス瓶、キッコーマンの卓上瓶、ペットボトル、P.I.D.(Pouch in Dispenser)と言われる酸化防止効果のある真空ボトルと新しい技術を投入してきた。変化の要因は運搬、保存、利便性、新鮮な味の提供といった観点であるが、これだけの容器を変化させてきた調味料や飲料は他にはないと思うのだが。
本書の「ものと人間の文化史というシリーズ」は1968年に刊行が始まった。日本の食の文化を支えてきた「醤油」がこのシリーズの180番目の項目であり、50年目に刊行されたことにいささか釈然としない思いは否めなかった。それは、私の家が江戸末期から醸造業を家業としてきたからでもあるのだが。そうは言っても、現在は従兄とその息子が醸造業を継いでくれていて、私は代々の家業を継がなかったという我儘者であるので、醤油のことをどれだけ知っているのかと言えば、はなはだ頼りない知見でしかない。家業の「醸造業」についての理解と、新たな興味喚起のためには良い読書になった。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





