世界ひと皿紀行【岡根谷実里】
世界ひと皿紀行
| 書籍名 | 世界ひと皿紀行 |
|---|---|
| 著者名 | 岡根谷実里 |
| 出版社 | 山と渓谷社(200p) |
| 発刊日 | 2025.02.18 |
| 希望小売価格 | 2,200円 |
| 書評日 | 2025.05.18 |
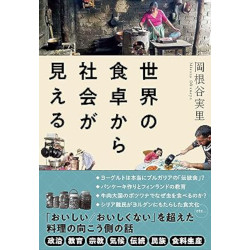
本書は各国のレストランで地元食を賞味して紹介するという一般的な料理本とは違って、著者は「世界の台所探検隊」と自称しているように、現地の村落や山村に足を運び、一般家庭に何泊もさせてもらって生活を共にし、食材の収穫に同行して家族と一緒に地元の伝統料理を作るという体験をしているからこそ、本書の副題である「24の物語」を書くことが出来るのだろう。ただこうした活動を実現させていくことはけして簡単なことではない。地縁・人縁を駆使しながら訪問する国の家庭を紹介してもらい、宿泊から調理までの協力がなければならない。こうした人との繋がりとともに著者の冒険心も相当なものであると思う。各々の家族の記憶と料理の記憶が重層化しているからこそ、「今まで食べた料理で一番美味しかった料理は何ですか」という質問にはなかなか答えられないと語っているのも良く判る。
本書はアジア、ヨーロッパ、中南米、オセアニアなど18ヶ国、24種の料理の物語で構成されている。取り上げられている食材だけでもベトナムの寺院で昔から作られていた代替肉とかノルウェーのトナカイの心臓のバスタやアイスランドの羊の頭や睾丸を使った料理など、調理に付き合っているだけでいくらでも物語が生まれてきそうである。けして旨い・不味いではなく、台所で一緒に料理を作ることで家族の喜びや悲しみの一端を知り、その国の伝統とか文化とともに揺れる社会を知る事も著者の狙っている視点である。
そうした風景から興味を持ったいくつかを取り上げてみる。ブルガリアのパプリカ料理では、母と娘が砂糖の量やあと何分煮込むかを大声で言い争う騒々しい台所で作り上げた一皿を前に、親子二人並んでテーブルについて「今年もおいしく出来たね」と笑いあっている姿から「我が家の味を引き継いでいく物語」として描いているのも面白い。
フィンランドで訪れた家の庭はそのまま自然の森に続いている。夫婦と子供二人の一家と森に入ってイチゴ、ブルーベリー、きのこなどをバケツ一杯摘んできて、これらをのせてピーラッカというパイを焼く。この国では「自然享受権」が国民にあって土地の所有者だけでなく誰もが森に入って森の恵みを取って良いというもの。こうして自らの手で採取して食に換える羨ましさを著者は伝えている。
メキシコでブニュエロスというお菓子を作ろうと老夫婦に誘われる。おばあさんは「母はクリスマスの時だけブニュエロスを作ってくれた」といった思い出話を話しながら小麦粉をねる。出来上がった生地を饅頭大に千切って寝かせたのちに、その生地を膝に乗せて全体を薄く伸ばしていく。それをおじいさんが受け取って油の鍋に投入。もう何十年もこの二人の息のあった共同作業を続けてきたのだろう。遊びに来ていた孫達は揚げたてを口にして「おばあちゃんのが世界一」と笑顔が溢れる。「レシピに書けない所に味の秘訣がある」という話だが、私としてはおじいちゃんも褒めてほしいと思ってしまう。
北東インドの山村を訪れた家は台所が家の中と外の二カ所にある。時間の掛かる煮込み料理や臭いの強い料理は外の台所を使うというのも醗酵文化圏ならではの台所構造である。いろいろな醗酵食品を家でつくっているが極め付きは納豆。日本では稲わらに包んで醗酵させるが、当地ではバナナの葉っぱにつつんで「アクニ(納豆)」を作る。臭いは日本の納豆よりもずっと強い。日本ではそのまま納豆を食べるが、インドでは燻製豚肉と煮込んだりして使う。こうしてゆっくりと煮込んだ豚肉の鍋を前にして「良い匂い」と著者が言うとお母さんは驚いたように「デリーのインド人は臭いって言うのよ」と、この鍋料理のおかげでここの家族と一挙に距離感が縮まった。「強烈な匂いの食は人を繋げるが、一方で分断も生む」とは至言である。
名前がすごい料理とは。中央アジアの高原の国キルギスの家庭料理。夕食にあと一品といってその家の母親が作ったのは「姑の舌」という料理。長なすを縦に薄く切っていく。形はまるで舌のよう。そのナスにマヨネーズに刻みニンニクを加えたソースを塗り、トマトを包んで食べる。予想外の生ニンニクの鋭い辛さとともにすっと食べてしまう。この辛さが「姑の言葉の様だ」ということで、この料理は「姑の舌」と名付けられている。ただこの家族は皆がこの料理が大好きで「みんなに歓迎される姑の舌は良い話だ」とこの物語は深い。
ポーランド内陸部の夏は暑く、冬は厳しい寒さ。滞在した家のお母さんが大きな寸胴鍋に2kgのザワークラフト、玉ねぎのみじん切り、ベーコン、豚肉、ソーセージなどを投入して煮込む。「ビゴス」という料理。三種の肉で味が深まり旨さが増す。この料理はクリスマスの後、「食べきれなかった肉が残っているからビゴスでも作るか」といったのりで作る料理の様だ。それだけに作った日も旨いのだが、ビゴスの入った巨大鍋を外のテラス(自然の冷蔵庫)に置いて、数日間楽しむのだが日々旨さが増していく。
気候や自然環境の違いは多くの食材を生み、その恵で命を繋いできた人類は固有の食文化を育んできた。知らない食材や調味料、調理方法など興味は深まるばかりである。こうした多様な食卓の一皿についての文章を読んでいると、ブリヤ・サヴァランの「美味礼讃(1825年)」の一節を思い出す。それは、「どんな物を食べているのかによって、君がどんな人間であるかを言い当てて見せる」というもの。しかし、それは同じ文化の下で暮らす人達同志の話でしかないという事にも気付かされる。あの時代、食に関するプライドも高かったフランス人の中でも高級役人であったサヴァランとしては極寒の地でトナカイの心臓を食べている人にまでは思い至らないのだろうなと思う。
本書に幾つかの料理のレシピが掲載されているが、その中の一品「ソパ・デ・アホ」というスペインの料理を作ってみた。料理名も笑ってしまうが、ソパはスープ、アホはニンニクで「ニンニク・スープ」である。ニンニクを炒め、バゲットを1cm各に切り、生ハムを刻んで加えて鶏ガラスープにパプリカ・パウダーを振って、最後に溶き卵を廻しいれると言うもの。ここに私なりの物語が有ればもっと美味いのかもしれないと思いつつ、物語は無くとも旨さは実感できた。
また、私は働いていた職場の数名の仲間とこの10年間程都内のレストランを訪ね歩いて29ヶ国の料理を楽しんできた。それが出来るのも東京という都市の持つ特殊性なのだろう。ただこうした企みでも未体験の食材・スパイス・調理法を堪能出来るものの、作っている人やその土地の気候風土までに思いを寄せることは限界がある。その意味からも本書のように料理を超えたところにある人々の生活までを捉えることは貴重な視点なのだろう。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





