その犬の名を誰も知らない【嘉悦 洋(監修 北村泰一)】
その犬の名を誰も知らない
| 書籍名 | その犬の名を誰も知らない |
|---|---|
| 著者名 | 嘉悦 洋(監修 北村泰一) |
| 出版社 | 小学館集英社プロダクション(344p) |
| 発刊日 | 2020.02.20 |
| 希望小売価格 | 1,650円 |
| 書評日 | 2020.05.16 |
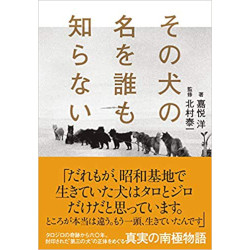
監修の北村泰一は1956年の南極観測第一次越冬隊員。当時25歳の京都大学大学院生でオーロラ観測を主任務にするとともに、犬ゾリの担当をした。昭和基地に15頭のカラフト犬を残し無念の帰国を余儀なくされたが、再度第三次越冬隊員として南極に行き「タロとジロ」に再会した人物である。現在89歳となる北村は第一次越冬隊の最後の生存者である。著者の嘉悦洋は西日本新聞社で社会部や科学分野の記者経験を持ちメディアの業界で生きてきた。
2018年に北村が健在であることを知り、「何故犬たちを置き去りにしたのか」「どのような思いで第三次越冬隊に志願したのか」「タロとジロ以外の犬はどうなったのか」「タロとジロは何故生き延びられたのか」等について北村自身への取材が実現した。この対話の中で、北村からタロとジロ以外の第三の犬が昭和基地に生存して居たという話を聞き、その犬を突き止めることに著者の視点は移っていったという。本書は60年という時間を戻し、南極体験を振り返りながら、第三の犬を解明のための北村と嘉悦の共同作業の記録である。
1956年末の南極観測船宗谷の出港のニュースは小学校3年生だった私も良く覚えている。国の期待を背負い、敗戦国として新たな発展を世界に示すイベントでもあった。南極と言う言葉の持つ挑戦の意味は同年5月の日本隊によるマナスル初登頂とともに子供心を揺さぶるには十分であった。しかし、第二次越冬隊の断念により、15頭のカラフト犬を昭和基地に置いて帰国せざるを得なかった事態に、国内で轟轟たる非難の声が上がったのを思い出す。メス犬のシロ子と8頭の仔犬たちを全て救出してきたという話もかき消してしまう程のバッシングだった。
だからこそ、その一年後に北村が昭和基地でタロとジロの生存を確認出来たときには皆が驚きとともに歓喜したということが強烈な記憶として残っている。逆に言うとそれしか記憶がないと言ってもいいのかもしれない。それだけに、懐かしい記憶を蘇らせてくれるとともに、カラフト犬の性質や南極越冬隊の活動を詳細に理解した上で謎解きに挑戦する楽しさを味わえる一冊である。
本書の前半は、日本の南極観測参加が認められ、その準備活動から北村の第一次越冬体験が書かれている。雪上車だけでなく、犬ゾリを利用すると言う決定に基づき、北海道内から20数頭のカラフト犬のオスの成犬が訓練の為に集められた。そして、タロとジロと名付けられた生後3ヶ月の仔犬も南極で犬ゾリ犬として育成させたいとの思いで選抜されている。この若さが謎解きの一つのヒントになる。
国内で訓練を重ねてはいるものの、未知の南極大陸で遭遇する困難な状況に対応しながら、越冬中に四度の犬ソリによる内陸調査が実施されたがタロとジロはまだまだ二軍であった。内陸調査は往復435km27日間という行程と聞くと、隊員と犬たちの一蓮托生の観測だったことが良く判る。一年間の越冬活動を経て、第二次越冬隊の到着を待つことになる。
第二次越冬隊を乗せた宗谷は1958年の初め、ブリザードの影響を受けて氷原に閉じ込められたまま流され140kmに迫っていた昭和基地から遠のくばかりであった。こうした状況下で、まず北村を始めとする第一次隊員が宗谷に収容されることになり、オスの成犬は首輪を穴一つきつく締めて首抜けをしない様に繋いだうえで、第二次先遣隊3名の隊員に引き継ついだ。
その間、宗谷の救援に駆けつけた米国のバートン・アイランド号の艦長から、氷状の悪化から、至急外海に離脱すべしとの勧告を受ける。第二次先遣隊の三人も昭和基地を撤収し、その後も天候は回復しないまま第二次越冬は断念したことから、15頭のオスのカラフト犬は昭和基地に残されることになった。
帰国した隊員たちを迎えたのは第一次越冬の成功よりも、カラフト犬を残して帰国したことへの激しいバッシングだった。犬ゾリ係でもあった北村は犬たちの首抜けを避けるために首輪をきつく締め第二次隊に引き継いだことに、カラフト犬が生き残るチャンスを奪ってしまったと激しく後悔したという。そして、もう一度南極に行き雪に埋もれた15頭を見つけてやる事をけじめとして第三次越冬隊への志願をするという流れは、もはや研究者という立場を越えて、彼を突き動かしていたと言える。
こうして、北村は第三次越冬隊員として参加し、宗谷からヘリコプターで昭和基地に向かった第一便の隊員から、動き回る二つの黒い点を発見したと報告を受けて昭和基地に向かう。そして、タロとジロとの歓喜の再会を果たす。一方、北村たちは雪の下に埋もれているカラフト犬たちを捜索し、ひと月近く経ったときやっと、一頭の首輪を見つけ、それを中心に探索し一頭の遺体を見つける。犬たちは4m程離して繋がれていたが、彼らは小さな群(2-3頭)をつくるように首輪や遺体が残されていた。結果遺体発見7頭、不明6頭、生存2頭と判明した。これで、北村の犬たちに対する落としどころを見つけられたと言える。
そして、主題の第三の犬の解明になる。北村が超高層地球物理学の研究に追われ、南極に係わることが少なくなっていた1982年に第九次隊員と話す機会を持った。そこで、1968年に昭和基地で一頭のカラフト犬の遺骸が発見されていたという事実を知らされる。この年は第四次越冬隊員で行方不明となった福島紳隊員の遺体が発見された年である。「第九次観測隊夏隊報告」には福島隊員の遺体発見の報告は詳細にあるが、カラフト犬遺体発見の記述は一切ない。また、当時の新聞を中心としたメディアの報道にもこの犬の遺体発見は無かった。その犬は不明6頭の内の誰なのかを解明することは遅々として進まなかったものの、嘉悦という協力者を得て真相解明を再開させる。
膨大な公式記録を読み解きながら、第八次越冬隊報告の中に「今年の夏は昭和基地の気温が極めて高く、融雪現象が激しかった。そのため第一次隊が残したカラフト犬の遺骸すら発見されている」という唯一の記載を見つける。そして、各地に散らばる第九次隊員への聞き取りを続け、「発見場所はカラフト犬の係留地近く」「大きくはない体格」「少なくとも黒色でない体毛」といった断片的な情報を得ながら、6頭の中から第三の犬の候補を4頭に絞り込んで行った。
タロ・ジロが食べ物をどこで得ていたのかについては、首輪が抜けなかった5頭の遺体は全てきれいに残っていたこともあり、一時期流布された共食説は否定された。北村が考えたのは、昭和基地の近くの海水域の氷原につくられた食糧貯蔵庫である。そこは一度海水が流入した事故が有り、海水に浸かってしまった肉類は残置されていた。また、犬ゾリで内陸探査の際に一定距離に作っていた食糧デポがある。これらを犬たちは理解していたはずだ。しかし、タロ・ジロという幼く経験の浅く、方向感覚の未熟な犬だけでは、それらを利用するには限界が有る。そのためには保護本能とリーダーシップを持ったベテラン犬の力が必要だったと考え、北村と嘉悦は第三の犬はリキというリーダー犬であるという結論にたどり着く。
首輪を抜け、鎖の束縛から逃れ自由になったタロ・ジロ以外の成犬は基地から逃れたいと考えて北海道を目指したのかもしれない。しかし、タロとジロは幼い時に南極に来たため昭和基地こそがかれらの故郷だったので動かなかった。一方リキは、タロとジロが彼を頼ったこともあり、彼らとの共同戦線を張ったのではないか。そして、食糧のある場所にも十分訓練された能力を駆使して到達していたに違いない。加えて、リキが昭和基地に踏みとどまったのは人間が戻ってくるのを待っていたのではないか。犬には死の概念がないため、人を待ち続けることが苦痛でないという。しかし、第三次越冬隊が昭和基地に到着する前にリキは息絶えた。当時のカラフト犬の寿命は7~8歳と言われていたが、昭和基地に置き去りにされた時点で7歳だったリキとしては最後まで力をふり絞った結果だったのだろう。
次の北村の言葉が切ない心境を表している。
「北村は小さく息を吐き、『タロとジロに再会したあの時に、リキはすぐそばに埋もれていたんですね。待ち続けていたのに・・・』といって私をみつめた」
犬ゾリを引くと言う集団行動の訓練の重要性、リーダー犬の不可欠さ、極限環境でも小さなグループで生き延びる努力をすることなどは人間の世界とよく似ている。個々の特性を生かしながら協力する姿はプロジェクトのあり方とそっくりだ。
北村は南極で活躍したすべての犬たちが頑張り死んでいったことを知ってもらいたいとの思いを語っているが、それは人間と犬たちの信頼関係の証でもある。使役犬としての犬たちの忠実さはまさに相互の信頼関係と人間の愛情で成り立っていると思う。そして、その関係の延長に家族の一員としての犬たちが居る。人間と犬との深い世界は極限で良く判る。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





