戦後腹ぺこ時代のシャッター音【赤瀬川原平】
戦後腹ぺこ時代のシャッター音
| 書籍名 | 戦後腹ぺこ時代のシャッター音 |
|---|---|
| 著者名 | 赤瀬川原平 |
| 出版社 | 岩波書店(215p) |
| 発刊日 | 2007.9 |
| 希望小売価格 | 1680 円(税込み) |
| 書評日等 | - |
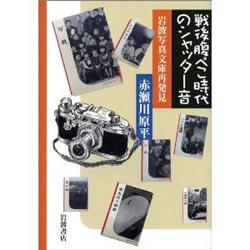
岩波写真文庫は1950年に創刊され、約8年間で286冊が刊行された。その中から24冊を選び「岩波写真文庫再訪」という副題を持つ本書が出た。この24冊を題材として当時の日本を語るというか、当時の赤瀬川自身を語るというのが本書の内容である。同時に10冊の岩波写真文庫が復刻版として岩波から出ている。岩波書店もなかなか商売上手なところを見せている。
1950年というと第二次大戦後5年間が経過しているのだが、その時代と写真との関係をこう表現している。
「・・落ち着いたとはいえ、人々は写真映像に飢えていた。メディアでまず手っ取り早いのは、活字による言葉だ。でも言葉はどうしても文学性に支えられている。そこを抜けてのリアルというのはやはり写真映像だ。・・・それをリアルに受け取ることになったのは、例の天皇陛下とマッカーサー元帥の併立写真だ。・・・戦後の日本は雨後の筍みたいに、カメラ産業がにょきにょきと生えてきた。とくに二眼レフは構造が簡単で造れば売れるので、板橋区を中心とする町工場でがんがん造っていた。四畳半メーカーといわれて、カメラ名はAからZまでズラリと並んだ、という話もある。・・・・」
赤瀬川は昭和12年生まれ、評者は昭和22年生まれ。この時代差は岩波写真文庫に対する感覚の違いや社会背景に対する意識の違いを生んでいると思う。私のような、生粋の団塊の世代は、本書でも取り上げられている「一年生-143」の世代で、読者以前に被写体そのものであったわけだ。カメラ産業が板橋区や北区を中心に町工場で造られていたというのも、北区の小学校に通っていた私には、身近な環境であった。壊れている「絞り」の部品を町工場のオジさんにもらって宝物のように持っていたり、学校帰りに町工場でレンズの研磨作業を飽きずにずっと見ていたのもその頃である。
家の本棚にはなぜか写真文庫がズラリと並んでいたことを思い出す。その印象は、一冊一冊がしっかりとした重量を感じさせるものであったことである。わら半紙のようなペラペラの雑誌や本が氾濫する中で、いかにも紙質の良さを表すような重さが格別であった。そして、モノクロームの写真が持つリアルさに迫力を感じていた。当時の小学生からすると、その迫力は、月刊冒険王の小松崎茂の細密描写絵か岩波写真文庫かと言ったところだろうか。
そして今、何十年も目にしていなかった岩波写真文庫が赤瀬川の読み解きとともに掲載写真を加えて紹介されているのだが、まざまざと思い出せる写真がその中にも幾つもあった。「南氷洋の捕鯨-3」「汽車-21」「石炭-49」「造船-67」「戦争と日本人-101」などはその代表で、子供の頃に飽きずにページをめくっていたものである。一方、あの名取洋之助が撮った「アメリカ人-5」や、名取洋之助監修、木村伊兵衛撮影の「写眞-8」については、後知恵として岩波写真文庫の一冊として見聞したことはあるが、当時の印象はまったくない。
このように岩波写真文庫は、かなり身近に存在していたものではあるが、小学生だったこともあり、一冊全てに感動というよりも、一冊の中のある一枚の写真が強烈に印象に残っているといったほうが正しいようだ。
赤瀬川はそうした写真の威力を表現している。
「いまは何ごとも情報の時代だから、鯨は大きい、地球上で最大、という情報だけ知ったらもうそんなに驚きもしないが、昔は具体の時代なので、鯨の巨大さを写真や絵図で知って実感的に驚いていた。・・・・実際に捕鯨船上での解体写真を目の当たりにすると、本当にこんな生き物が海の中にいるんだと、目が釘付けになる。それが写真の力の原始というか、真髄である。・・・・」
白ながす鯨が母船に引き上げられて解体される写真では、鯨の大きさもさることながら白ながす鯨の体表の筋の深さや太さに大感動していたものである。「汽車」が発行された昭和26年は蒸気機関車が依然として現役でガンガン走っていた時代である。国鉄でも私鉄でもごく普通に蒸気機関車は使われていたし、東海道線の完全電化は五年あとの昭和31年である。その時点で「汽車」を写真文庫の対象とした編集者の選定眼は大変興味がある。例えば「造船-67」は造船の工程とか、進水前の巨大なスクリューなど、普段目に出来ない部分を見せているだけに、インパクトは大きくなるのは当たり前だが、汽車はいくらでも目の前にある巨大機械だっただけに蒸気機関車の原理まで図解している徹底さについて、文庫編集者の意図をききたくなってしまうのだ。
「戦争と日本人-あるカメラマンの記録(101)」は朝日新聞の報道カメラマンの景山正雄の戦時中から戦後に撮影されたものである。この表紙写真、戦友の遺骨を抱いて帰国する軍人の隊列を撮影したものだが、子供心によく覚えている。ある種の怖さを覚えながら見ていたのだと思う。しかし、米軍基地の鉄条網の前に立つ子供の写真は、これだけインパクトのあるものなのに記憶にまったくない。そのキャプションを赤瀬川が紹介している。日本の歴史の通過点としての戦後とはいえ、時代を切り取ったリアルさとしての写真の力を感じさせる一枚である。
「戦後の米軍基地の鉄条網の前で、着物姿で花を売る少女。しかしキャプションには、じつは女の着物を着た男の子で、こうしないと花が売れない、という実情報告。ここからもう戦後はなまなましくはじまっている。」(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





