司馬江漢「東海道五十三次」の真実【對中如雲】
司馬江漢「東海道五十三次」の真実
| 書籍名 | 司馬江漢「東海道五十三次」の真実 |
|---|---|
| 著者名 | 對中如雲 |
| 出版社 | 祥伝社(307p) |
| 発刊日 | 2020.09.30 |
| 希望小売価格 | 1,980円 |
| 書評日 | 2021.04.18 |
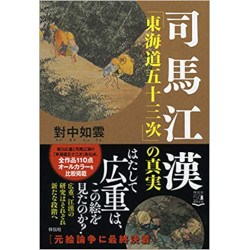
東海道五十三次と言えば広重というのがまあ一般的な感覚だろう。以前、旧東海道を歩き続けていた時に宿場に差し掛かると広重の版画の絵柄を思い出し、あの時代の雰囲気を感じ取ったり、面影を探したりするのも楽しみの一つだった。それだけに、広重の「東海道五十三次」には元絵があり、司馬江漢という絵師が書いたという話には驚いたものである。司馬江漢(1747~1818)とは江戸後期の絵師として浮世絵、中国画、銅版画(エッチング)、油絵と多様な画風の作品を残し、同時に地動説を日本で初めて文献に取り上げるなど自然科学者としても活躍した人物である。
30年前、著者の對中(当時伊豆高原美術館館長)のところに、江漢の「東海道五十三次」と題された五十五枚の画からなる画帖の鑑定依頼が有ったことが発端である。最初にその画を見た時の印象を「洋画とも日本画とも言えぬ見慣れぬ画風で、東海道の道筋が写真的に描かれており、絵柄は広重の「東海道五十三次」に類似していた」と著者は書いている。そして、1995年に江漢「東海道五十三次」が広重版画の元絵であるという説を発表した結果、「広重の五十三次は盗作」という刺激的な見出しをつけてマスコミが取り上げたこともあり、冷静な議論がなされた様には思えなかったと思うのは私だけだろうか。その後も著者の研究は続き、技術的な分析結果などを踏まえて本書では「元絵論争に最終決着」というサブタイトルを付けている様に、「仮説」から「真実」へと一歩前進させるための一冊である。
本書の前半は「図版解説」と題して、二人の作品(五十五枚)を宿場毎に見開きページに並べて詳細な説明している。ざっと見ただけでも、過半の絵柄は酷似しているのは一目瞭然であり、初めて見る人はその相似性に驚くはずである。江漢の五十五枚の絵は縦長の肉筆画。遠近法で陰影を施した洋風画で、自ら調合した絵具を使った水彩画。順番は広重とは逆で、京都から東海道を下り江戸までを描いていている。江漢自身はこれらの画に「日本勝景色富士」と名付けており、「東海道五十三次」と名付けたのは後の所有者である。生涯三回東海道を往復している江漢にとって最後の旅である文化9年(1812年)の旅程のスケッチが元になって、文化10年(1813)から文化15年(1818)に作成されたと推定されている。一方、広重の「東海道五十三次」は天保4年(1833)に始まり、好評だったこともあり翌年には全五十五枚の浮世絵がセットで刊行されている。
偽物が多いと言われる江漢の絵だけに、「東海道五十三次」が彼の真作であることを次の様に示している。
遠近法を駆使した構図など西洋画の技法を活用していたのは広重以前では江漢だけである。広重の版画より江漢の絵は実景に忠実であり、江漢の絵を元絵にして広重の版画はつくれるが、広重の版画を元にして江漢の絵を描くことはできない。
また、黄色絵具は50年単位程で新しい材質の絵具が開発されているため時代検証の指標にされているが、江漢の絵で使われている黄色の絵具を分析した結果は鉛と錫を含む「レッドティン・イエロー」が検出された。この黄色絵具は18世紀半ばにヨーロッパで使用ピークを迎えたものだが、それが日本にもたらされたとすると江漢の時代に合致する。サインや印などを含めた幾つかの考証が本書のポイントの一つである。
次に、江漢が活用した西欧の絵画技法や科学的成果の知見について紹介している。まず、江漢は日本で初めて油絵(蝋画)を描いただけでなく、銅版画(エッチング)を天明3年(1783)に制作しており作品は数点現存しているとのこと。しかし、エッチング制作に欠かせない硝酸は、ヨーロッパから長崎経由で入手するしかなかったが、懇意であった幕府御殿医の桂川甫周経由で手に入れたか、オランダ人の江戸宿泊所である日本橋長崎屋で入手した可能性もあると指摘している。江漢は長崎の出島や日本橋長崎屋への出入りをしていたが、それは平賀源内に同伴することから始まったようである。江漢にとって日本橋長崎屋は新しい科学技術や思想に接することの出来る重要な場所であり、多くの文献や道具を手に入れた場所でもあった。
江漢が作画の為にもっとも活用した道具は「カメラオブスキュラ」と呼ばれる写真鏡で、一眼レフカメラからシャッターや絞りを除いたようなもので「箱の中に硝子の鏡を仕掛け、山水人物の映像を写し、画ける器」と言われている。これはダヴィンチが「モナリザ」の背景を描くのに使ったとか、フェルメールが使っていたと言われるもので、点描や遠近法にその絵の特徴が出ると言う。「真を写さざれば絵画にあらず」という考えの江漢の作画を支えた技術であったことは間違いない。著者はこうした江漢を次の様に表現している。
「江戸時代に「カメラオブスキュラ」の実用性に注目した一人の絵師がいた。男は自然科学者の目を持ち、技術者の腕を持っていた。その絵師は自らそれを作り、東海道の宿場風景、そして富士を再現するのに、それをフル活用して五十五枚の画帖にした。そして、「我が国始りて無き画法なり」と豪語した。・・・・オランダ自然主義絵画の科学性と静謐さ、中国画の神妙、狩野派の風雅、浮世絵の持つ大衆性、それらを集大成したもの・・・それが江漢「東海道五十三次」なのである」
二人の「東海道五十三次」の大きな違いがあるとすると、広重の版画は庶民が喜ぶ娯楽作品であり、まずは売る事を目的にして作られている。一方、江漢は作品を公開する意図はなく、それだけに寓意性を表現していると著者は見ている。例えば、宮宿では、江漢は勤皇思想の江漢は尾張徳川家の祀場である熱田神宮を描かずに神明造りの神社(伊勢神宮の外宮)を精密に描いている。こうした表現の狙いを著者は多面的に分析して見せているのも面白いポイントだ。
平賀源内、伊能忠敬、間宮林蔵とも交流を持ち、東海道の旅の中で大名、旗本、勅使だけが使える宿場の本陣に泊まっていることも、江漢がただの町絵師では説明がつかないという指摘ももっともである。江漢の墓所は巣鴨の慈眼寺であるが、この寺は水戸徳川の菩提寺でもあり、以前の本堂の天井画は江漢が描いていたという。こうした水戸藩との深い関係(水戸藩隠密説)を始め、京都公家の中山愛親を始め開明派大名達との交流があったという江漢の活動の根底は「自分の祖国がヨーロッパと比較して、あまりに遅れていることにため息が出るような思い」に始まる「憂国」こそ、すべてのキーワードではなかったかというのが著者の考えである。
江漢を変わり者の絵師として捉えていては真実にたどり着かないという思いが著者には強い。科学者としてまた思想家として江漢を捉える必要性を語っている。
「上天使将軍、下士農工商に至るまで、皆もって人間なり」(春波楼筆記)という江漢の平等論は福沢の「学問のすすめ」の60年前のことである。ドナルド・キーンに「歴史上の人物で一人だけ会えるなら、司馬江漢を選ぶかもしれない」と言わしめた男だ。江漢という人物の全貌はまだまだ明かされていないのだろう。また、江漢自身が隠密だったとしたら隠していることが有るのかもしれない。人間としてまだまだいろいろな視点で深堀して行く余地があるのだろう。
一方、元絵が江漢の画帖だったとしても、広重が表現した「東海道五十三次」の宿場風景や人物たちの輝きは不変である。私は広重の「東海道五十三次」が好きであることは、本書読了後も変わらない。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





