総力戦のなかの日本政治【源川真希】
総力戦のなかの日本政治
| 書籍名 | 総力戦のなかの日本政治 |
|---|---|
| 著者名 | 源川真希 |
| 出版社 | 吉川弘文館(253p) |
| 発刊日 | 2017.03.02 |
| 希望小売価格 | 3,024円 |
| 書評日 | 2017.08.20 |
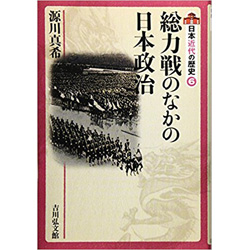
本書は吉川弘文館の「日本近代の歴史」シリーズの最終第6巻。1937年の盧溝橋事件から1945年の第二次大戦敗戦までの10年間に満たない期間を対象としているのだが、この激動の時代は近代の最後であるとともに、次に続く現代への屈折点になっていることから、現代からあの時代をどう読み解くべきなのかという提起でもある。執筆者の源川は1961年(昭和36年)生れ。21世紀の現代から戦前・戦中を語っている。
「歴史」とは語る人が生きた時代と語る時期の二つの要素によって異なる意味を持つと云う。その違いを三つのカテゴリーに分類している。戦争体験者によって1955年頃までに書かれた「体験的通史」、戦争体験者による高度成長期に書かれた「検証的通史」、戦後生まれの執筆者による世紀転換期に書かれた「記憶的通史」という見方である。本書に限らず現代においては、語る者も聞く者も双方ともに戦争体験を持たない人がほとんどである。そうした違いが有るからこそ執筆者の源川は近代、特に戦中を語ることに相対性があることを否定していない。
「歴史は良くも悪くも国民のアイデンティティのよりどころになりうる。近現代史はしばしば政治的な争点になり国際関係における交渉の駆け引き材料にもなりがち……そうであれば、まず、我々は史料に則して語らなければならない」
「史料に則して」と言っても、客観性を保つのはそう簡単なことではない。史料選択の妥当性に始まり、史料という真実の断片から全貌を俯瞰することの危険性を常に考えておかなければならないからだ。本書の特徴としてその史料の一つが、東京帝国大学の法学部の教官でデモクラシー理論研究者だった矢部貞二(1902年~1967年)の日記・史料である。矢部は近衛新体制のブレーンでもあり、新体制運動期の政治の動きを始めとして、戦時体制に組み込まれていく大学の様子、都市生活者として目に映った日々の事柄を書き留めているのだが、それらを活用して総力戦と政治そして社会を源川は描き出している。
1930年代から1940年代にかけて先進各国で構築された社会体制は、階級社会・封建社会から工業化社会へ移行する時代であった。ドイツ・イタリア・日本のファシズムとアメリカのニューディールは共に資本主義の危機への対応策として出現した政治体制であるが、第二次大戦での敵対する関係をもってファシズムとニューディールは対立的に捉えられてきた。しかし、総力戦体制のなかで国民を戦争に動員し、国家による国民支配の貫徹という意味ではファシズムもニューディールも等しく強圧的であった。このように、各国の社会改革構想の諸制度は立案時には戦争を前提としていなかったものの、第二次世界大戦への道程の中で戦時目的に読み替えられていくことが少なくなかったとの見解は総力戦論として広く語られているところである。
ただ、特に日本においては、極めて短い時間軸で社会変革を追求しつつ、各国との戦争に打ち勝つための国家戦略は同時並行的に進んでいったということだろう。1937年とは第一次近衛内閣は「国民精神総動員委員会」を発足させ上位下達型の運動を開始した年である。そして、中国戦線での南京陥落を祝う提灯行列のため日本の各都市で市民は駆り出されたのが1937年12月12日。既存の政党や活動家たちの多くは社会変革の活動方針を変えることなく、社会大衆党を初め婦選獲得同盟の市川房枝なども戦争協力を表明していった時代だ。
一方、その三日後の12月15日に雑誌「労農」の同人、学者、弁護士、日本無産党の関係者など440名がいわゆる人民戦線編成を企てたとして全国で一斉に検挙された。思想弾圧として共産党以外の政治信条の人々が対象になった初めてのケースである。以後、大政翼賛会に結びつく「魂の統一」が徐々に進んで行く契機となった事象が着々と進んでいたことが判る。
1940年7月に成立した第二次近衛内閣は9月の日独伊三国同盟の締結を迎え、国家指導意思の一元化と全国民の総力を終結させる「新体制=国民組織」の確立を目指した。当初は近衛もブレーン矢部貞二も新党設立の思惑が有ったものの、政党となると治安警察法のいうところの政治結社となり軍人・官僚・教員などが加われないことから国民組織として設計された。1940年10月に大政翼賛会が発足するが、総裁は内閣総理大臣、中央本部の下に道府県・郡・市町村に支部を置き、役員には官僚、貴衆両議員、軍人、ジャーナリストなどが加わった。こうして国家レベルの総力戦体制が確立された。政党でない国民組織としての大政翼賛会は国会議員選挙でも推薦候補を指名して多くの推薦候補が圧倒的多数で当選することになる。
この大東亜戦争の目的・理念として、開戦の詔勅では「自存自衛」、帝国国策遂行要領ではこれに「大東亜の新秩序建設」が加えられた。大東亜共栄圏の構想はアジアにおける旧宗主国からの独立運動を支援することで各国からの期待を集めた一面もあるが、総力戦下では各国の位置づけは日本への物資資源供給地であり、日本占領地における皇民化政策、労働力動員など進められている中では、逆に日本の支配に抵抗運動も起こり抗日に変化していったということである。例えばビルマの独立運動のリーダーであったアウンサンらを支援したが、戦争末期には日本に対する武装闘争に転じた。戦時総力戦における資源確保という現実と「共栄」という理念のギャップを糊塗することは出来なかったということだ。
「総力戦が社会を変えたことは事実。当時の知識人達の問題意識は総力戦への依拠は社会改革のための一種の迂回戦術の面を示している。……もちろん、それが破滅的な結果につながるのだが、そもそも1930年代の社会改革構想や国家による諸制度の構築も立案時には戦争を前提としていなかったものが戦争目的に読み替えられていく。……もともとは資本主義的経済秩序の問題を克服ための処方箋として提起されたものが読み替えられて総力戦に転轍されていった」
こうした、戦術としての妥当性にも関わらず、戦略や国家運営の観点からは破滅的な失敗として国民に記憶された時代である。そのためもあり、戦後初の内閣総理大臣(皇族東久邇宮稔彦)は敗戦処理内閣として例外とすると、以降1955年までの総理大臣は戦時中に反翼賛体制を標榜していたか、自由主義的な立場を取っていた政治家が務めていることが判る。幣原喜重郎、吉田茂、片山哲、芦田均、鳩山一郎、石橋湛山らの名前が続く。1955年に至って戦中翼賛体制の中枢にいた岸信介が総理大臣に就任する。1945年とともに、この1955年も現代の私たちはその意味を議論する必要があるのだろうと思う。
私たちは歴史を学んだ結果、時代を象徴する事件や事象を数多く知識として蓄積し、それらの相関関係を歴史のストーリーとして理解している。それは教科書的な歴史理解としては正しいのだろう。しかし、もう一つ私たちの歴史に向かう姿勢として、自分自身の体験だけでなく、両親や祖父母といった人々の生き様も戦前・戦中・戦後の歴史に裏付けて考えることも最近多くなった。子供の頃、夏休みに母の実家に遊びに行くと少しとっつきにくそうな祖父がいつも掛け軸を前に座っていた。その弁護士だった祖父が死去したとき小学生だった私には、彼が1937年に人民戦線事件に連座して検挙されたとは知る由もなかった。 (内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





