思索紀行【立花隆】
思索紀行
| 書籍名 | 思索紀行 |
|---|---|
| 著者名 | 立花隆 |
| 出版社 | 書籍情報社(512p) |
| 発刊日 | 2004.10.10 |
| 希望小売価格 | 1600円+税 |
| 書評日等 | - |
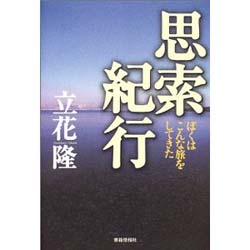
序章「世界の認識は「旅」から始まる」のなかで、立花隆はフラメンコの「ドゥエンデ」と呼ばれる瞬間について書いている。
フラメンコのギタリストと歌い手とダンサーがかけ合いをしながら時間とともにどんどん調子を上げてゆき、次々にバトンタッチして入魂の演奏を披露してゆくうちに舞台と客席が一体となり、あるとき、「神がかった」としか表現できない一瞬が訪れる。それを「ドゥエンデ」(原義は魔物にのりうつられること)と言う。
タブラオ(フラメンコ酒場)でプレイヤーが「ドゥエンデ」に達するのは、まず間違いなく観光客が帰って真夜中を過ぎてから。だから、その瞬間に立ち会うにはじっくりと時間をかけ、その夜はフラメンコにとことんつきあう覚悟をしなければならない。
彼はまた、もうひとつの「ドゥエンデ」体験について触れている。マドリッドの西北にあるエル・エスコリアル修道院。黄金期のスペインの富をつぎこんだ、しかし装飾のいっさいないこの修道院を1日歩きまわってくたくたになり、無人の大聖堂に座り込んでいたとき、いきなり大音響のパイプオルガンが鳴り出した。バッハの「大フーガ」だった。
「突然なぜか涙が出てきた。涙は出はじめると、とめどなく流れた。自分がなぜそのとき泣いたのか、説明しろといわれてもできない。……悲しくて泣いたのではない。なんらかの理由で心が乱れていたというわけでもない。ただ自然だった。日常性をこえたところで起きた突然の感動、エモーションのほとばしりとでもいったらいいだろうか」
そうした「ドゥエンデ」の瞬間に出会い、日常の規範から解き放たれたワンランク上の認識レベルを体験することが旅なのだ、と立花は言う。そのためには、まず自分の肉体をその場に運んで、その空間に身を置かなければならない。どれだけ情報があふれていようとも、それだけは変わらない。
「この世は、ヴァーチャルな認識装置を通したのでは決してとらえることのできないもので満ち満ちている。自分の肉体に付属した「ワンセットの感覚装置(それが私自身だ)」からなる「リアルな現実」認識装置をそこまでもっていかないと成立しない認識というものがある。……一言でいうなら、この世界を本当に認識しようと思ったら、かならず生身の旅が必要になるということだ」
そんな旅の方法論に貫かれ、いくつもの「ドゥエンデ」体験を記した文章が、ここには収められている。もっとも、タイトルに「紀行」とあり、「僕はこんな旅をしてきた」とサブタイトルがついているけれど、これは普通に考えられる旅の本ではない。
「型にはまった紀行文ほどくだらないものはない」と本人も書いているように、ここには旅の時間や空間に即した文章はほとんど登場しない。むしろ旅を契機として生まれた「認識」と「思索」の結果が、長大なレポートとして提出されている。
序論につづいて「無人島の思索」「「ガルガンチュア風」暴飲暴食の旅」「キリスト教芸術への旅」「ヨーロッパ反核無銭旅行」「パレスチナ報告」「ニューヨーク研究」の6章からなるこの本は、大部分が1970~80年代に雑誌に掲載されたものだ。
特に1974年に発表された「パレスチナ報告」は、長期取材にもとづいて国連によるイスラエル・パレスチナ分割決議に始まるパレスチナ問題の基礎を、政治・民族・宗教・文化などさまざまな側面から論じて、いま読んでもまったく色あせていない。どころか、パレスチナ問題に関して、その後も日本人の書いたもので立花レポートを超えるものにお目にかかった記憶はない。アフガニスタン、イラク戦争やイスラム過激派によるテロの根源がどこにあるかを、はっきりと指し示してくれる。
もうひとつ興味深かったのは、「ヨーロッパ反核無銭旅行」と題されたインタビュー。これは1960年、立花が大学2年のとき、友人と2人で原爆関係の映画を上映しながらヨーロッパ各地を半年ちかく歩きまわった旅を、当時の日記を見ながら語ったものだ。
当時は、立花が在籍していた東大の教師でさえも、海外渡航した経験者はほとんどいない時代だった。立花青年は、ともかく外国に行ってみたいという思いから、原爆反対をアピールする映画をもって各地で上映するというアイディアを思いつく。とはいえ、その段階では組織も資金も人脈もない「夢物語」のような話だった。
彼は一緒に動いてくれそうな友人と「委員会」をデッチあげ、映画会社と交渉し、原水禁大会で外国の参加者にアピールし、カンパを求めて資金集めに奔走する。
「とりあえず第一歩を踏み出してみる。それだけの話なんです。あとはその場その場の状況のなかで、どれだけバタつくかということだけですよ。人間、水のなかに放り込まれたら、必死になって泳いで向こう岸にたどり着くでしょう。それと同じですよ」
そのようにして「夢物語」を現実のものにし、ヨーロッパでは、支援者から支援者へと手渡されるようにして貧乏旅行でロンドン、パリ、ローマなど16都市を回った。
1960年といえば、日米安保改定反対闘争が空前の盛り上がりを見せたとき。立花青年は大学1年のときから自治会委員として反対闘争に参加していたが、樺美智子の死を頂点とする5月から6月の過程にはヨーロッパにいて参加していない。
「さまざまの人々に出会って、いろんな会話を交わしているうちに、おかしいのは日本の学生運動のほうだと気がつくわけです。世界が見えていないし、歴史が見えていない……学生運動にかぎったことではなくで、日本の社会全体、日本人全体がそうなのだということがわかってくるわけです」
「日本の社会というのは、基本的にいまでも、数百年つづいた鎖国時代の延長としてあり、意識がぜんぜん開かれていない。外国の思想や文化にしても、翻訳でわかったつもりになっているだけで、じつはどこか本質において根本的な理解が欠けているということがわかってくるわけです」
「純化されたモデル」ではなく、具体的事実とひとりひとりの人間から物ごとを考えてゆくこと。そう思いいたったこの旅の体験が、やがてジャーナリスト立花隆の誕生につながっていくことは言うまでもない。
飽くことのない好奇心、その場へ身を置く現場主義、徹底した事前調査と取材、ディテールと全体をつなぐ論理的な構想力。後に築きあげる立花の方法の萌芽がこの旅にはあり、それ以外にもジャーナリストとして脂の乗った時期のいくつもの果実が、この本には収められている。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





