司馬遼太郎 東北をゆく【赤坂憲雄】
司馬遼太郎 東北をゆく
| 書籍名 | 司馬遼太郎 東北をゆく |
|---|---|
| 著者名 | 赤坂憲雄 |
| 出版社 | 人文書院(232p) |
| 発刊日 | 2015.01.30 |
| 希望小売価格 | 2,160円 |
| 書評日 | 2015.03.16 |
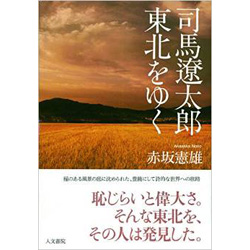
「街道をゆく」と題して司馬遼太郎は昭和46年から25年間にわたり日本国内だけでなく、海外を含めて、膨大な紀行文を週刊朝日に連載してきた。それは、広範な知識と好奇心に支えられた知的体験と発見の旅だったに違いない。本書はその中の東北の部分に焦点を当てて、「東北」と「司馬遼太郎」の双方を再確認するという試みである。対象となった旅は「陸奥のみち」「羽州街道」「仙台・石巻」「秋田県散歩」「白河・会津のみち」「北のまほろば」である。それを読み解いているのは赤坂憲雄。民俗学者である彼は、長く東北学と称して、フィールドワークを主体とする新しい視点の東北地域文化の確立にエネルギーを注いできた人間だが、3.11の後は地域に寄り添いながら復興の活動を活発に行うとともに、政府の「東日本大震災復興構想会議」の委員として名を連ね、現在は学習院大学教授・福島県立博物館館長を務めている。
赤坂が「わたしは多分、司馬遼太郎のまっすぐな読者ではない。肌合いがはっきり違う」と言っているように、「東北」を考えるヒントとして二人の異なった視点からの理解が提示され、結果として深まりのある東北論となっているところが面白い。また、司馬は関西の出身であり、ある年齢までは「箱根の関」以東については無知であったことを極めて率直に正直に語っている一方、訪れた土地・土地で東北に対するシンパシーをこれでもかと表現しており、赤坂の言葉を借りれば、まさに「たじろぐほど」の至上のシンパシーを発露しているその源泉を確認していく楽しみもある。
司馬は「東北の風土からは詩人が群がり出てくるという印象が基礎となっている」と語っているのだが、その感覚について赤坂はこう述べている。
「そこで幾度となく言及されるのは芭蕉とその『奥の細道』であり、東北の近代を代表する石川啄木や宮沢憲治、斎藤茂吉といった詩人たちではなかった。・・・二十世紀の末近く『街道をゆく』によって歴史紀行という文学ジャンルを創始したかに見える司馬が、実は極めて忠実な歌仙の旅人としての古風な貌をもっていたことを指摘しておくのもいい」
例えば、福島県の中通り(白河市・郡山市・福島市)から会津に向かう旅では、平安期の「みちのくブーム」の端緒として源融(みなもとのとおる)の「陸奥のしのぶもちずり(信夫捩摺)誰ゆゑに乱れんと思ふわれならなくに」(古今和歌集)と、下って能因法師の「都をば霞とともにたちしかど秋風ぞ吹く白川の関」(後拾遺和歌集)という二つの和歌を取り上げつつ旅を続けている。この点を赤坂は「都と奥州の間にはまなざしの非対称性がくっきりと存在したのである。司馬はもちろんこのことに十分自覚的であった。都びとにとっては、奥州の遙かさが、その隔絶といっていい距離こそが詩の源泉であり、詩そのものであり得た」という見方は平安期における東北(みちのく)の位置づけとして述べている。
さらに時代は下って「奥の細道」では、単なる距離感に根ざした「詩的風景」ではなくなっていく。「風流の初めやおくの田植うた」という白川の関を越えたところでつくられた芭蕉の句について司馬の感覚をこう読み解いている。
「この句を司馬は気になっていたらしい。白河以南と変わらぬ稲の風景を見出して芭蕉の心は揺さぶられ、風流を感じた。白河の関という境界を越えてつながっている、文化の秘められた相続と言ってよい」。ここで赤坂は、稲作農耕文化こそ東北を語るときに歴史・文化・風土の点から司馬としての大きなテーマがあったとしているのだ。つまり、日本の上代天皇制は、弥生式農耕が西から東へと広がっていくにつれて、それと表裏一体になって自然に伸びていった「宗教的な存在」であり、より的確に言えば「農業の権威的象徴」というべき存在であったという、稲作至上主義が厳然として存在した。
一方、岩手の野辺地区の風景に接して司馬はこうした稲作至上主義を批判的にこう語っている「この風景をさびしいとか、際涯(さいはて)と感ずる感覚は、われわれが二千年という長期間弥生式農耕という暖地生産で過ごしてきたことからきた百姓式の感覚であるに違いない。もし、フィンランド人やハンガリー人がこの大地を最初に発見したとすれば、かれらはこの大空間に放牧することを考えて狂喜したであろう」。そして、戊辰戦争後の明治期にその文化を転換出来なかったことに対して悔やんでいるのである。「いまさら振り返っても仕方のないことだが、東北という、つまり白河以南の米作地帯という別原理の思想をもつて有史以来の東北経営をやり変えてしまうという構想が明治初年に思いつかなかったものだろうか」
そして、秋田の八郎潟では昭和の農政を嘆くのだ。八郎潟を干拓して水田地帯とする国家プロジェクトの開始時点(終戦直後)では、有史以来の「米作万能の時代」が過ぎ去るとはだれも考えていなかった。皮肉にも、昭和40年代に米を持て余すようになり「食菅赤字」に悩む時代になってその完成を迎えた。このように司馬が歴史として「東北が水田稲作にしばられてきたことへの同情と批判を幾度となく語る」ことに赤坂は共感しつつも、そうした永き米作への苦闘の結果、3.11によって突き付けられた現実は、営々として潟を埋め立て作られて来た海岸近くの水田が津波に飲み込まれ水没して潟に戻っていく光景を見せつけられるという厳しさだったことを語っている。
「戊辰戦争については司馬は繰り返し、勝者となった薩摩や長州から一方的に幕末・維新の歴史が語り継がれて来たことへ批判的な留保を行ってきた」として、赤坂は、司馬の東北への思い入れの根っこはこの「義憤」がからんでいたという見方をしている。それは、もう一段論を進めると司馬の思想の根底にある「正義嫌い」「イデオロギー嫌い」であるとも解釈している。
「東北の中で日本人離れをした人物を輩出してきた。内藤湖南、大槻文彦、金田一京助、・・など。こうした知における未踏の曠野の開拓者たちを生んだのは何故か。それはたぶんこの地に『朝敵』という言葉が影を落としていることと無縁ではない。『人民の敵』といった言葉と同じように、正義体系(イデオロギー)が製造した言葉である。それゆえ、イデオロギーの流行が去ってしまえばたちまち意味すら忘れられる。水戸学という正義体系こそが、朱子学の尊王攘夷を濃密に相続しつつ、それを尺度として『朝敵』という言葉を創りだしたのだ。そう司馬は述べている。『朝敵』と名指しされた東北の孤高の精神たちが、未踏の曠野へと向かわざるを得なかったことには、避けがたい必然があったに違いない。正義を掲げる体系とイデオロギーと言う言葉の繋がりに注意を向けなければならない。そこに司馬遼太郎という思想を読み解くカギの一つが隠されているはずだ」
「なにから書き始めていいのか判らないほどに、この藩についての思いが私の中で濃い」とまで語る司馬が会津を訪れる意味は重かったようだ。山形出身の井上ひさしは司馬遼太郎に対して「会津は東北じゃない」と言ったという。赤坂はこの発言の真意は判らないとしつつも、1590年代末に近江日野の蒲生氏郷が92万石の会津に近江から商人や職人を引き連れて入ったことなどから、他の東北の地と違った「東北民俗性が希薄」であるという意味なのか、気候・地勢的には越後にも近いという意味なのか。いずれにしても幕末の京都守護職であった城主の松平容保は時の孝明天皇から厚い信頼を得て内密の宸翰を受け取り、その守秘の密約を生涯かけて守り通したにも関わらず会津藩は「朝敵」と名指しされて、明治維新という革命の生贄となった。藩士と家族は陸奥の斗南に移され塗炭の苦しみを味わうことになる。
こうして、「戊辰戦争は西方の勝利に終ったものの、明治新政府はその首都を東京に置いたことから、明治以降は東の時代といっていい」とする司馬の言葉に赤坂はこう答える「東北はそういう意味合いでの『東』ではない。第三の一点である。・・・そうした力み方が東北にはある。これはひょっとすると『東北人のひそかな楽しみの一つである自虐性』あるいは『高度な文学性から出た自家製の幻想』かもしれない」と。
仙台に本社を持つ有力な地方紙として「河北新報」がある。この名は長州の侍が会津に攻めあがるとき、侮蔑的に「白河以北、一山百文」と言い放った言葉を取って名付けられたものだ。これも東北人の「密かな楽しみの自虐性」と「力みとしての負けん気」のなせる技かも知れない。毎月の福島に向かう新幹線の中で本書を読みながら、司馬遼太郎と赤坂憲雄と共に、もう一人の読者たる自分がいて鼎談をしているような気分の読書であった。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





