世界のすべての七月【ティム・オブライエン】
世界のすべての七月
| 書籍名 | 世界のすべての七月 |
|---|---|
| 著者名 | ティム・オブライエン |
| 出版社 | 文藝春秋(480p) |
| 発刊日 | 2004.3.15 |
| 希望小売価格 | 2095円+税 |
| 書評日等 | 村上春樹訳 |
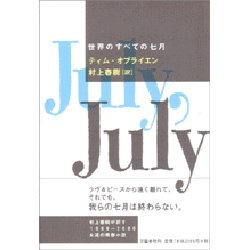
「あとがき」で、訳者の村上春樹はこう書いている。「僕も実作者として、いつか六〇年代に青春を送った世代の、長大なクロニクルのようなものを書くことができればと考えている」。村上がひとことで要約してみせたように、ティム・オブライエンの新作は、「ヴェトナム世代」の過去と現在が交錯する、同世代の読者にはいろんな意味でおもしろい長編小説だ。
2000年7月、ミネソタ州ミネアポリスで、1969年に当地の大学を卒業した学生の30年ぶりの同窓会が開かれた。この小説の主人公は、そこに集まった10人余りの男たち、女たち。同窓会で30年ぶりに顔を会わせた彼らの現在と、それぞれに秘められた過去とがフラッシュバックしながら、群像ドラマが進んでいく。
ヴェトナムで片足を失ったが事業で成功した、ヤク中のデイヴィッド。彼の「ドリーム・ガール」で、デイヴィッドとの結婚と離婚を経験したマーラ。徴兵カードを焼いてカナダに逃亡し、今は金物チェーンを経営しているビリー。ビリーとの駆け落ちの約束を破って彼の親友と結婚し、裕福な生活を送っている共和党支持者のドロシー。
平和運動のリーダーで今は弁護士のエイミー(離婚経験あり)。卒業アルバムでトップレスになり、2人の夫と二重生活を送っているセクシーなスプーク。スプークと男女の関係を夢見ながら30年間友達関係の、心臓病を抱えた肥満体のマーヴ。
こう紹介すれば、それだけで60年代に青春を送った世代の30年後の姿が思い浮かぶだろう。
デイヴィッドは、ダンスに興じているかつての妻、マーラを見つけて顔を背けてしまう(「というのは彼はマーラを激しく求めていたからだ」)。ビリーとドロシーは、30年前の「裏切り」について、ぎこちない会話を交わしている。エイミーは、離婚した者同士でひたすら飲みながら、同級生のゴシップを種にシニカルな会話に耽っている。銀色のミニスカートのスプークは、今夜こそと期待するマーヴの膝の上に座って彼を挑発している。
彼らは、それぞれの過去と現在を抱え、それぞれの立場から30年を振り返ってつぶやく。
「私たちの両親――時代遅れのとんかち頭の連中、なーんにもきれいさっぱりわかっていないやつら。でも連中にも、ひとつだけわかっていたことがあった。それはね、私たちが結局はどうなるかっていうことよ。なんのかんの言ったところで、私たちが行き着く先は、あいつらにはしっかり見えていたのよ」と、ため息をつく、かつての平和運動のリーダー。
デイヴィッドは、ヴェトナムで失った片足をいまだに感じ、失った足に痛みを覚えることすらある。「幻覚痛、もうそこにはないものが与える苦痛。失った片脚のまぼろしを今でもときどき感じる」
デイヴィッドと離婚したマーラは、再婚し、妊娠し、流産し、精神の安定を失い、再び離婚してひとりになった。「自分がまたひとりぼっちで、例の薄闇の中に戻っているのを知った。とくに幸福というのでもなく、とくに惨めというのでもない。自分はそういう風にしか生きられないのだ。そんな気がした」
ビリーの愛を裏切って郊外の高級住宅地に住み、乳ガンで、あまり高くない5年後生存率を宣告されているドロシーは言う。「私がいらいらさせられるのは、みんながいまだに、六〇年代にべったりしがみついていることなの。誰もがみんな、そのことで罪悪感みたいなものを感じているわけ。幸福になるのがいやなの。成長するまいと思っているの。正直な話、今という時代のいったいどこがいけないわけ?私たちはもう大人なのよ。安楽な暮らしをして、どこがいけないの?」
主人公のひとりがつぶやくように、登場人物たちはみな「誰もがそれぞれに痛みを感じ、それぞれにちょっとした傷やへこみやらを抱え込んでいる」。そして30年前の自分と現在の自分の像のズレをうまく受け入れることができずにいる。そんな主人公たちに感情移入するでもなく、逆に突き放すでもなく、ティム・オブライエンはいわば時間を主人公とした年代記作者の目で彼らを見つめている。
ヤク中のデイヴィッドが思い出すヴェトナムの、マジック・リアリズム風な幻覚。肥満体のマーブが、惚れた女に覆面作家だと嘘をついたことに発する、ロアルド・ダールのような一章。さらにデイヴィッドとドロシーが人工の脚と乳房を見せあうグロテスクなシーンなどが差しはさまれ、作者は物語をセンチメンタルに起承転結させてしまうことなく読者を楽しませてくれる。
そして彼らを相対化するように、より若い世代の警官に、「世界はナンセンスな回り方をしています。ひとつ事実として言えるのは、誰が非難してもしなくても、それと無関係に世界は回り続けるっていうことだ」とも言わせている。
2日間の同窓会が終わって、新たなカップルが生まれている。元の鞘に戻るカップルがある。男と女の関係に発展しそうな友達関係がある。新たな希望と失意が生まれ、相変わらず酒びたりのグチと孤独もある。そんな男たち女たちを、幽体離脱して自分の身体を上からながめているようなティム・オブライエンの底にあるのは、彼らへの愛と言うしかない感情だろう。
村上春樹がうまく訳したように「世界のすべての七月(原題“July, July”)」とは、主人公たちだけのことでなく、世界中の同じ世代に向けたメッセージと読むことができる。その通り、私も、この小説を読んで深く揺すぶられた。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





