ケルト人の夢【マリオ・バルガス=リョサ】
ケルト人の夢
| 書籍名 | ケルト人の夢 |
|---|---|
| 著者名 | マリオ・バルガス=リョサ |
| 出版社 | 岩波書店(538p) |
| 発刊日 | 2021.10.27 |
| 希望小売価格 | 3,960円 |
| 書評日 | 2022.02.17 |
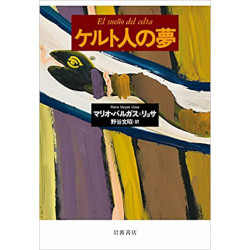
小説を読む愉しみのひとつに、「いま・ここ」を離れた過去・未来の異空間に拉致され、いっとき登場人物になりきって喜び怒り哀しみ楽しむ経験を与えてくれることがある。子どもなら誰も冒険ものや探偵小説、あるいは少女小説でそんな我を忘れる全身体験をしているけれど、大人になってからそうしたカタルシスを味わわせてくれる小説にめったにお目にかからない。その稀な小説に出会った。マリオ・バルガス=リョサの『ケルト人の夢』。
時は20世紀初頭。舞台はアフリカのコンゴと南米のアマゾン、そしてアイルランド。西洋列強による植民地支配が地球規模で展開されていた時代だ。主人公は実在の人物で、イギリスの外交官ロジャー・ケイスメント。アイルランド(ケルト人)の血を引く彼は、英国領事として赴任したコンゴとアマゾンでヨーロッパ人による先住民の残酷な支配を告発して歴史を動かす役割を果たした。が、後にアイルランドの英国からの独立運動に参加して反逆者となり、捕えられて絞首刑となる。
言うまでもなくバルガス=リョサは1970年代に世界に衝撃を与えたラテン・アメリカ文学ブームを牽引したひとり。ペルー出身で、後にスペイン国籍を取得している。本書は彼がノーベル文学賞を受けた2010年に刊行された。綿密な取材による事実に基づきつつ奔放な想像力でディテールを埋めた、なんともスケールの大きな小説だ。
物語はロジャーが英国領事時代のコンゴ(あるいはアマゾン)と、アイルランド独立派のイースター蜂起にからんで逮捕された獄中とが同時進行する。
当時、コンゴはベルギーの、というよりベルギー国王レオポルド二世が個人所有する植民地だった。国王は「文明と、キリスト教と、自由貿易」をもたらすために兵士や民兵を送り込んだが、ヨーロッパ中から集められた彼らにはごろつきやならず者、犯罪者、一攫千金を狙う冒険者が多かった。彼らは「村落を焼き、略奪を行ない、先住民を撃ち殺し、鞭で打ち据え」といった所業を行く先々で繰りひろげた。若きロジャーはアフリカを文明化するという理想を信じて国王のために働いていたが、やがてその過酷な現実を知ることになる。後に英国領事としてコンゴに赴任したロジャーは、政府に虐待のレポートを提出するためコンゴ川を遡って村々を訪れる。バルガス=リョサの筆は、まるで読者がコンゴ(あるいはアマゾンの密林)の現場に立ち会ってでもいるようなリアリティに満ちている。
「瞼を閉じると、目のくらむようなつむじ風のなかに、背中、尻、脚に小さな毒ヘビに似た赤い傷痕が残る黒檀のような体が、繰り返し現れる。子どもや老人の切断された腕の傷口、残っているのは皮膚と頭蓋骨だけでまるで生気も、脂肪も、筋肉も抜き取られてやつれ果てた、死体のような顔。痛みよりも、そんな目に遭ったことがひきおこした深い自失を表すうつろな目あるいはしかめっ面だけ。それはいつも同じで、ロジャー・ケイスメントがノートと鉛筆とカメラを持って足を踏み入れたすべての村落や片田舎で何度となく繰り返されてきた光景だった」
この現実はコンゴの次に赴任したアマゾンでも変わらなかった。「自分がだんだん正気を失いつつある気がするよ」、と彼はアイルランドの従妹に手紙を書いている。やがてロジャーのなかで、ひとつの疑問が浮かんでくる。「コンゴと同じくアイルランドも植民地ではないか?…イギリス人はアイルランドを侵略したのではなかったか」。このときからロジャーは、大英帝国の外交官として働きながらアイルランド独立を夢みる、矛盾に引き裂かれた男として生きることになる。
小説のなかで同時進行する獄中は、その十数年後。既に第一次大戦が始まっている。アイルランド独立派はイギリスに対して蜂起を計画し、ロジャーは独立派として英国の敵国ドイツから武器を故国に送ろうとして失敗、逮捕された。アフリカやアマゾンのすさまじい搾取を告発した有名人で元英国外交官のロジャーをどう扱うか、英国政府は揺れている。獄中の彼を従妹や独立派の友人や神父が訪れる。彼らとの、そして看守「シェリフ」との対話がロジャーの過去と現在を浮き彫りにする。
独房の「現在」でロジャーは、死刑判決が下った彼に恩赦の請願が認められるか否か、生と死の狭間で揺れている。一方、回想のなかに現れるアイルランドや家族の記憶は美しい。なかでも印象に残るのは、カトリックだった母の肖像。彼女は「ほっそりした体つきの女性で、歩くというよりは空中を漂うかのようであり、目と髪の色は明るく、滑らかきわまりない手が自分の巻き毛に絡んだり入浴中にその手で自分の体が愛撫されたりすると、彼は幸福な気持ちに満たされた」。
この母をはじめとして、なんとも個性的な人物が次々に登場するのもこの小説の魅力のひとつ。高名なアフリカ探検家で「(先住民の)知能は君や私よりワニやカバに近い」と公言するスタンリー。割り当てられた量のゴム樹液を持ってこなかった先住民を「気晴らしのために」石油の染み込んだ大袋に詰め火を放つ遊びに興ずるゴム農園のチーフ、ビクトル・マセド。はじめロジャーを売国奴と軽蔑するが、やがて心を開いて息子を失った悲しみを告白する看守の「シェリフ」(本書の登場人物はほとんど実在するが、これはバルガス=リョサが創作した人物らしい)。
なかでも心に残るのは、同性愛の性向をもつロジャーの前に現れるノルウェーの金髪の美青年、アイヴァント・クリステンセンだろう。ニューヨークの路上で出会い、一目で気に入ったロジャーは彼を「ヴァイキングの神」と呼び、助手としてアイルランド独立派の会合に同行する。が、アイヴァントは裏でイギリスの諜報機関に通じ、ロジャーの行動はすべて筒抜けになっていた。それがロジャー逮捕の原因となる。
ロジャーは20世紀初頭に苛烈な植民地支配を告発して世界史を動かした人物だけど、バルガス=リョサは彼を英雄としてだけ描いていない。むしろ彼の弱みや判断の間違いをも含めて、ロジャー・ケイスメントという矛盾に満ちた人間の丸ごとの姿に迫っている。
僕たちはこの長大な小説を読みながら、緑濃い密林と瀑布の風景に見惚れ、拷問機にかけられる先住民の身になって恐怖し、航行不能の川を遡るため船体を先住民に牽かせて山越えする光景に驚嘆し(映画『フィッツカラルド』!)、殺されかねない奥地のゴム農園で残虐な白人チーフとひとり対峙するロジャーにはらはらし、独立という「ケルト人の夢」に邁進すると同時に「美貌のヴァイキング」に惹かれてゆく姿に人間が否応なく選んでしまう選択を思う。
ロジャー・ケイスメントの存在は長らく歴史のなかに埋もれていたらしい。同性愛が強いタブーだった当時、ロジャーがアフリカやアマゾンで若い先住民に声をかけたことを記した秘密日記をイギリス情報部が断片的に宣伝に利用したことは、アイルランド人をも困惑させた。彼は墓碑も十字架もないままロンドンに埋葬され、彼の遺骸がアイルランドの地に帰るのは性意識に世界的な変化があった1960年代を待たなければならなかった。
そんな「英雄と殉教者は抽象的な典型でも完璧さの見本でもなく、矛盾と対照、弱さと偉大さからなる一人の人間」の姿を、この小説は余すところなく味わわせてくれる。年末から正月をはさんで一カ月、まるで歴史のなかに自分が紛れ込んだような読書だった。
蛇足。読後、友人と、これ映画で見たいよね、という話になった。あれこれ名前を挙げた末に決まったのは、こんな「夢の映画」。
主役のロジャー・ケイスメントにベネディクト・カンバーバッチ。
ロジャーが告発する虐待の責任者ペルー・アマゾン・カンパニー社主にハビエル・バルデム。
ロジャーが惑う美青年アイヴァントにティモシー・シャラメ。
回想シーンの母にアイルランド系のシアーシャ・ローナン。
そして監督には『アギーレ 神の怒り』『フィッツカラルド』とアマゾン舞台の映画2本を撮った御大ウェルナー・ヘルツォーク。
どんなもんでしょう? 見たいなあ。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





