会社はこれからどうなるのか【岩井克人】
会社はこれからどうなるのか
| 書籍名 | 会社はこれからどうなるのか |
|---|---|
| 著者名 | 岩井克人 |
| 出版社 | 平凡社(342p) |
| 発刊日 | 2003.2.23 |
| 希望小売価格 | 1600円 |
| 書評日等 | - |
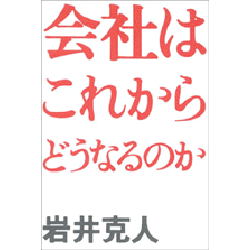
今年の第2回小林秀雄賞を受けた本である。昭和の文芸批評の大御所である小林秀雄の名前を冠した賞と、先端的な思想にも敏感な経済学者である岩井克人、そして「会社はこれからどうなるのか」という実用書ふうなタイトルの三つが、どうにもすんなりと結びつかず、収まりが悪い。その収まりの悪さがこの本のユニークなところだと言ったら、強引にすぎるだろうか。
この本の読者の多くが、リストラとデフレの不安のなかで、タイトルにあるように会社というものがこれからどうなってしまうのかという興味で手に取り、それに対するなんらかの答えを期待していることは明らかだろう。
でも、岩井は冒頭から、「この本は出来合いの答えを用意しているわけではありません」と言いきってしまう。そして実際、多くの実用的経済書がそうであるように、ちょっとだけ目新しいコンセプトと回答を示して、いっとき読者を納得させる(ような錯覚を起こさせる)ことを、いっさいしていない。
そのかわりに岩井がこの本でやっていることは、いま、この国の資本主義と企業がおかれている状況を歴史的パースペクティブのなかで、あるいは近代哲学のパースペクティブのなかで原理的に考えなおしてみることだ。
岩井がここで語っている問題は、二つの問いにまとめることができる。
(1)「グローバル化」の基準になっているアメリカ型の会社は、本当に世界基準なのか。
(2)「特殊」といわれる日本の会社のあり方の本質は何なのか。
結論を言ってしまえば、(1)に対する著者の答えは「NO」である。
いまのアメリカ型の会社のあり方をひとことで言えば、会社とは株主のものであるという「株主主権」論だと岩井は言う。
20世紀前半、企業の「所有と経営の分離」が言われたけれど、1970年代のレーガン時代から、株主が経営者から主権を取り戻す動きがはっきりしてきた。具体的には、経営者の報酬を「株式オプション」にした、つまり経営者の報酬が株価に連動するようにしたことだ。経営者が企業の株価を高めて自分の利益を追求することは、自動的に株主の利益を追求することになる。要するに経営者を株主にしてしまったわけだ。
その結果がエンロンやワールドコムの事件であったことは言うまでもない。経営者は巨額の粉飾決算をして株価を釣りあげ、信じがたいほどの報酬を受け取っていた。倒産に当たっては株を売り逃げ、一方、外部の株主や従業員が持つ株式は紙屑となり、社員は職も失った。
「経営者は外部の株主よりはるかに詳しい内部情報をもっています。それでいて、アメリカ型のコーポレート・ガバナンス(会社統治機構)においては、経営者はアダム・スミスのいう「自己愛」を発揮することを奨励されているのです。その経営者に大量の株式オプションを与えてしまうことーーそれは、まさに不正行為への招待状以外の何ものでもありません」
では、ポスト産業資本主義の時代に、どんな会社のあり方が求められているのか、と問う前に、岩井は(2)の設問に答えてゆく。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と浮かれていた1980年代、日本的な企業経営が持ち上げられたことがあった。当時の議論も踏まえ、岩井は日本的な企業のあり方をひとことで言えば「会社共同体」論だという。
・株主の利益より会社の成長・存続を目的とする(実際、日本企業の自己資本利益率はアメリカに比べ一貫して低い)。つまり株主主権ではない。
・従業員の会社への帰属意識が高く、その企業でしか通用しない知識・能力(「組織特殊的人的資産」)を蓄積してきた。
・系列企業が株式を持ち合ってM&Aを防いできた。その結果、「一家」意識が高まり、本来は株主を意味する「社員」が従業員を意味するようになった。
日本的会社は、会社の本来の持ち主である株主よりも、外部の契約者にすぎない従業員とその家族、系列の人々にやさしいあり方だといえばいいのか。そんな「共同体」的な日本の会社は、明治以降の重化学工業を中心とした後期の産業資本主義に適応した(適応しすぎた)あり方だと岩井は言う。そこにはまた、戦前の財閥の前身である江戸時代の商家の「家」のあり方が影を落としている。
これは「特殊」な会社のあり方なのか。いや、そうではない、と岩井は断言する。「会社という制度そのもののなかに、資本主義的企業のひとつの形態として、日本的な会社を生みだす仕掛けが仕込まれている」、つまり「逸脱ではなく、ひとつの普遍にほかならない」というのだ。
彼の言うように、日本的な会社が「特殊」ではなく「ひとつの普遍」だとすれば、先のふたつの設問につづいて、当然に次のような問いが出てくる。
(3)日本的会社はポスト産業資本主義の時代にも生き残れるのか。
この問いに対する岩井の議論をまとめれば、「NO, BUT」ということになるだろうか。株式持ち合いで企業を守り、終身雇用、年功賃金、企業別組合で熟練労働者・技術者を養成してきた日本的会社は、グローバル化、IT革命、金融革命にさらされる21世紀に、そのまま生き残ることはできない。
では、岩井の言うポスト産業資本主義時代の会社のあり方とは、どんなものか。
・価値を生みだすのは「有形資産(モノ)」よりも「知識資産」である(例えばマイクロソフト社の市場総価値のうち、有形資産は1割未満、9割以上が知識資産である)。
・「知識資産」は、それを持っているヒトと切り離すことができない。つまり金で買えるモノよりも、金で買えないヒトのなかの知識や能力のほうが価値を持つ。
・大規模な工場が必要ではなく、金融革命により資金も簡単に調達できるから、古典的なオーナー企業が復活してくる(シリコン・ヴァレー・モデル)。
・知的財産権(情報をタダでコピーすることを禁ずる制度)が整備される。それによって、情報がモノと同じように商品として売り買いされるようになる。
・「知識資産」を持った「組織特殊的な人的資産」が大きな意味を持つようになる。彼らがつくる共同体的な会社組織がM&A を防ぐ役割を果たす。
こうして挙げてくると、先ほど挙げた日本的会社のシステムと共通した部分があることに気づく。
「日本型の資本主義とは、株式の持ち合いを通じて外部の株主によるホールド・アップ(乗っ取り)を排除し、熟練労働者や工業技術者や専門経営者による組織特殊的な人的資産の蓄積をうながすことを、その最大の特徴としていたのです。その意味で、日本的経営はポスト産業資本主義的な企業を、少なくとも部分的には先取りしていたというわけです」
著者も最初に断っているように、これは「実用的」な本ではない。ここで展開されている議論に対しては、現実に進行しているのはそんなことではない、という反論も出てくるだろう。実際にアメリカで起こっているのは、それとは反対の一層の「株主主権」化だという声もありそうだ。
僕の印象でも、この議論には現実を冷徹に分析した結果というより、未来へ向けた岩井のメッセージが多分に含まれているのではないか、という気もする。だから僕には、この議論が正しいのか間違っているのか判断がつかない。でも、彼がここで試みようとしているのは、グローバル化=アメリカ化という現実とは別の、ありうるかもしれないもう一つの企業のあり方を原理的に提示することなのだということは分かる。
ここではトピック的な部分を紹介したけれど、この本の面白さはそこだけではない。株式会社=法人という、モノでもありヒトでもある組織の成立をローマ時代にさかのぼり、法人はもともと倫理性を求められる公共的な性格をもつことを論じた歴史的議論や、近代哲学の基礎に照らして法人がどんな意味を持っているかを論じた原理的な部分こそが、この本のオリジナリティーだろう。
明日の「実用」には役立たないけれど、そうした歴史的・原理的部分に面白さを感ずる読者にとっては十分に「実用的」な本なのだ。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





