金閣を焼かなければならぬ【内海 健】
金閣を焼かなければならぬ
| 書籍名 | 金閣を焼かなければならぬ |
|---|---|
| 著者名 | 内海 健 |
| 出版社 | 河出書房新社(228p) |
| 発刊日 | 2020.06.20 |
| 希望小売価格 | 2,640円 |
| 書評日 | 2021.01.17 |
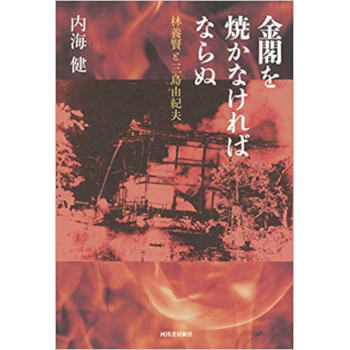
タイトルの「金閣を焼かなければならぬ」とは、小説『金閣寺』のなかで、主人公溝口が苦悩と彷徨の果てに「突然私にうかんで来た想念」として三島由紀夫が書き記した言葉だ。本書には「林養賢と三島由紀夫」とサブタイトルがつけられている。林養賢は1950年に金閣に火を放った、この寺で修行する21歳の青年僧。三島は、事件に想を得てその6年後に『金閣寺』を発表した。
精神科医である著者は後書きで、医者になったあと『金閣寺』を読み返して「犯人は未発の分裂症であり、それ以外にはありえぬと直感した」と書く。後にこの事件を調べはじめて、判決が確定し服役した後に養賢が分裂病を発症したことを知る。以来、「この二人の男のことについて書き残さねば」と思い、それから二十数年後に本書が刊行された。
内海は『「分裂病」の消滅』『さまよえる自己』などの著書をもつ精神科の研究者で臨床医。現在は東京芸術大学の教授・保健管理センター長を務めている。だからこれは精神科医の目でもって林養賢が起こした事件と三島の小説を解読した、なんともスリリングな本になっている。なお分裂病は現在では統合失調症と呼ばれるが、内海は、分裂病と呼ばれた当時のこの病をとりまく雰囲気を肌で知ってもらうために、あえて分裂病の名を採用したと書いている。
本書の前半では、林養賢の内面と行動が追跡される。事件を起こすまで、養賢には犯行を予兆させるような言動はまったく見られなかった。が、関係者の証言によると、養賢はその1年ほど前から憂鬱にとらわれていた。知的青年が憂鬱にとらわれるのは近代社会で一般的な現象だが、症状が現れる前の分裂病の前駆期に見られることもあるという。また同時に周囲から性格が変わったように見られ、大学の成績が急降下したのも分裂症の前兆であり、これらのことから内海はこの時期の養賢が前駆期にあったのは間違いないと判断している。
分裂病の前駆期にある者がたどる一般的な経過は、「内包された狂気」が社会や他者といったフレームにぶつかって幻覚や妄想といった「症状」を呈し、そこではじめて分裂病と診断される。ところが、稀に特殊な状況や偶然の重なりによっていくつものフレームをすりぬけ、病気が顕在化する前に「狂気のポテンシャルは極大にまで充満し、不意にカタストロフへとなだれ込む」ことがある。その典型が自殺や殺人だが、そうした行為には動機がない。「徹底的に『無動機』である」と内海は記す。養賢もそうだった。
犯行後、養賢は放火した理由を問われて「無意味にやりました」と答えている。だが人は、ある行為にいたった原因や理由が明らかにされなければ心理的に納得しがたい(という病をもつ)。事件の因果関係を明らかにする起訴状は「美に対する嫉妬、美しい金閣と共に死にたかった」と養賢の陳述を記している。もっとも彼は、その動機も「本当といえば本当、本当でないといえば本当でない」と述べているのだが。
分裂病前駆期の養賢が示した「狂気のポテンシャル」について、内海はさらに「超越論的他者」「存在の励起」といった言葉を使って密かな病の進行を解読しているが、そこに分け入るとややこしくなるので、ここでは触れない。結論として内海は、日常的な意味の連鎖から切り離された養賢が、己のなかの自分ではない何者かから「何かをなさねばならぬ」という督促を受けて焦燥し、「動機や理由によって回収できないところに迷い出てしまった」結果が金閣への放火だったと書く。
一方、公判で明らかにされた「美に対する嫉妬」という言葉に恐らくインスパイアされたのが三島由紀夫だった。本書の後半では、小説『金閣寺』とそれを書いた三島の精神のあり方が解読される。
内海は、三島に生涯にわたって憑りついた宿痾は「離隔」だったと言う。平たく言えば現実感の希薄さ、日常的な現実に対し生きているリアリティを感じられないということだろう。多彩な現実を経験する前に言語表現を学び早熟な文学少年として出発した三島にとってリアリティは言語空間のなかにのみあり、現実は色褪せたものとしか映らなかった。
内海によれば、『金閣寺』は現実に対し「離隔」を感じて生きざるをえない主人公溝口が金閣放火という犯罪に至る道行を描いた、意識空間のなかの小説である。金閣はその「離隔」を象徴するものとして現れる。
三島は執筆に当たって事件の記録を丹念に調べ、起こった出来事は忠実に踏襲しているが、事を起こした養賢本人には思い入れや関心をほとんどもっていない。とはいえ、養賢も三島と共通する「離隔」を現実に対し感じていたから、「彼らが邂逅するポイントがあるとすれば、まずはそこになる」。その一点で二人は接近したのだが、養賢の内面に無関心だった三島の手になる主人公溝口の「離隔」は、現実の犯罪者・養賢のそれでなく作者・三島のものとなっている。
養賢の金閣放火が動機なき狂気の激発だったように、小説『金閣寺』においても動機は書かれていない。書かれているとすれば、貧困や怨恨といった対人的社会的なものでなく、意識内部で完結した動機である。三島を苦しめてきた「離隔」とは、内海によれば「ナルシシズム的宇宙に内包されている現実感の希薄さであり、その世界の外への通路が閉塞していることである」。その内的宇宙を内海は球体に見立て、「ナルシシズムの球体」と呼ぶ。「金閣はこの球体そのものである。その伽藍の中に溝口=三島は捉え込まれている」。その閉塞を突破するためには、「金閣を焼かなければならない」。
実際にはジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』やカフカの『審判』を引きながら、もっと精密な議論が展開されているけれど、大筋を取り出すとそういうことになる。そして内海はこう結論づける。「養賢が兇行のあと、うわごとのようにその行為を名指した『美への嫉妬』、三島はこの事後の表象から入り、兇行の真理に裏側から到達した」。「自分自身のナルシシズム的世界の究極を志向することにより、対極にいる養賢に、行為の一点で邂逅し、真実を穿ったのである」
小生は世に数多ある三島論や『金閣寺』論を読んだことがないので、内海のこの解読がこれまでの三島理解の中でどんな場所を占め、どのように評価されるのか、まったく分からない。でも内海の論が、連綿と積み重ねられた文学世界の三島評価でなく、その外の世界から来た視点と方法で書かれていることは確かだろう。といって小生、精神医学についても素人なので、その世界からの評価も分からないのだが。
内海は、分裂病という病に接するときは「メタフィジカルな感性とでもいうべきものが要請される」と書いている。常識的な意味での了解が及ばないところから患者に接しなければならないのだから、その言葉は理解できる。その「メタフィジカルな感性」は、分裂病を理解する鍵として「超越論的他者」「存在の励起」といった言葉を使っていることからもうかがえる。しかも、こうした言葉が単に学術的な概念でなく、深い専門知と長い経験が縒りあわさったものとして出されていることで、読む者に深い納得をもたらす。内海が「三島の妖刀のごとき筆の恐ろしさ」と書く、そのまごうかたなき傑作(本書に触発され40年ぶりに読み返した)の秘密を垣間見たと実感できる年末年始の読書だった。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





