黒い瞳のブロンド【ベンジャミン・ブラック】
黒い瞳のブロンド
| 書籍名 | 黒い瞳のブロンド |
|---|---|
| 著者名 | ベンジャミン・ブラック |
| 出版社 | 早川ポケット・ミステリ(352p) |
| 発刊日 | 2014.10.10 |
| 希望小売価格 | 2,052円 |
| 書評日 | 2017.10.22 |
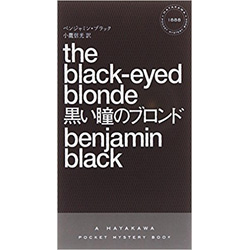
書店で早川ポケット・ミステリの棚を見ていたら、「私立探偵フィリップ・マーロウ シリーズ最新作」という帯が目についた。といってもレイモンド・チャンドラーはとっくの昔に亡くなっているから、チャンドラーの新作ということはありえない。かつてロバート・パーカーが、チャンドラーの未完のマーロウもの『プードル・スプリングス物語』を書き継いだことがあるから、その類いだろうと見当をつけた。でも、ベンジャミン・ブラックという作家は知らないし、読んだこともない。
「あとがき」を見たらイギリスの作家、ジョン・バンヴィルの別名義だという。ジョン・バンヴィルという人の小説も読んだことがないけど、『海に帰る日』という作品でブッカー賞を得ているから(このときカズオ・イシグロ『わたしを離さないで』も候補になっていた)力のある小説家なんだろう。タイトルも魅力的。最近、ハードボイルドにはご無沙汰だったこともあって、ついレジへ持っていってしまった。
巻末の「著者ノート」によると、チャンドラーは自分の資料ファイルのなかに、将来書くことになるかもしれない小説のタイトルのリストを保存していた。「黒い瞳のブロンド(The Black-eyed Blonde)」は、そのひとつだったという。
『黒い瞳のブロンド』、ひとことで言えば名作『ロング・グッドバイ』の続編だった。『ロング・グッドバイ』の主役であるテリー・レノックスや富豪の娘で魅力的なリンダ・ローリング(彼女は『プードル・スプリングス物語』ではマーロウと結婚している)が再び登場する。常連の脇役、保安官事務所殺人課のバーニー・オールズやロス市警の刑事ジョー・グリーンも出てきてマーロウと辛辣なジョークをたたきあう。マーロウとテリーがギムレットを飲む酒場<ヴィクターズ>とそのバーテンダーも登場する。マーロウもののスター勢ぞろいといった趣き。
物語の展開も、ハードボイルドの定型を忠実になぞっている。裏町のマーロウの事務所に、赤いアルファ・ロメオに乗った魅力的な人妻クレア(黒い瞳のブロンド)がやってきて、失踪した愛人を見つけてほしいと依頼する。マーロウが調査に動きまわると、その動きが誘拐や銃弾や死体を呼び出してしまう。マーロウはファム・ファタール(黒い瞳のブロンド)に誘いをかけられ、その魅力に抵抗できない。やがて黒幕が登場する……。
『ロング・グッドバイ』同様、ロスの上流社会を舞台にしたクライム小説だ。クレアは、宝石の有名ブランドで富を得、大邸宅に住んでいる老女の娘。娘の亭主は飲んだくれるだけの無能。マーロウが調査をつづけると、クレアが行方を探すよう依頼した愛人は、どうみても上流階級の黒い瞳のブロンドが惚れるような男ではなく、ただのチンピラ。どこか、おかしい。──このあたり人物配置や展開は、『ロング・グッドバイ』だけでなく、『高い窓』や『さよなら、愛しい人』とも似ている。というより、ブラックは意識してチャンドラーを踏襲してるんだろう。
本書がチャンドラーのマーロウではなくブラックのマーロウになっているのは、テイストの違いがあるから。ブラックのマーロウはイギリス風味とでもいうか。なにしろブラックは、マーロウものの舞台であるロサンゼルスに行ったことがないというのだ。
ハードボイルドはじめミステリーが成功するかどうかは、良き風俗小説になっているかどうかが大切、というのは僕の仮説。登場人物の服装や小物、街の風俗といったディテールが細かく書きこまれていてこそ、小説に艶が出る。ロスという都市を知らないブラックは、だからイギリス風味で勝負している。
そのひとつは、マーロウに衒学趣味を持たせたこと。チャンドラーのマーロウは辛辣なジョークを連発して相手を煙に巻いたり警句のようなものを口にはするけれど、根は行動派に描かれている。でもブラックのマーロウは「哲学的思索」が好きな「思考型探偵」と自称している。もっとも、高尚な哲学を口にするわけでなく、たとえば「どうしてビールのひと口目は二口目より常に旨いのか」と質問し衒学的な答えを楽しむといった程度なのだが。
「たぶん、温度がその答えなのだろう。二口めのビールがひと口目より生温かくなっているというのではなく、初めの冷んやりとした感触を覚えている口が、あらかじめ二口目の感触を予期して待ちかまえてしまうので、快楽の法則の数値の低下を伴って、驚きの要素が欠落してしまうのだ」
チャンドラーのマーロウなら、こんなことは口にしない。そしてブラックのマーロウは、英国風パブに入って「ローストビーフ・サンドイッチと英国ビールの大ジョッキ」を注文する。僕の記憶するかぎり、チャンドラーのマーロウがこういう注文をしたことはない、はずだ。
もうひとつは、イギリス風味というよりアイルランド風味。これはチャンドラー自身がアイルランド系である事実を踏まえているかもしれない。マーロウが刑事のジョーと会うのは「つくりもののアイリッシュ酒場」。プラスチックのシャムロック(アイルランドの国花)が飾ってあり、壁にはジョン・ウェインとモーリン・オハラ(アイルランドを舞台にした『静かなる男』の主演俳優)の写真が貼られている。ふたりはアイリッシュ・ウィスキーでなくビールを飲む。
また、宝石で富を得た富豪の老女はアイルランド移民で、夫はアイルランド独立戦争で戦死したことになっている。初対面のマーロウは、こんな感想を抱く。「タフなばあさんだ。おそらく冷酷非情で、使用人の給料を値切り、その気になれば人に私を殺させることもできるだろう。とは言いながら、彼女にはつい好意を抱かざるをえない何かが備わっていた。不屈の精神だ」
「タフでなければ生きていけない。優しくなれなければ生きている資格がない」(『プレイバック』)とはマーロウの名セリフだが、都会の光と闇、両方の世界に生きるマーロウの硬骨ぶりはブラック版でももちろん健在だ。
もっとも、こんなふうにチャンドラーのマーロウとブラックのマーロウを比較して喜ぶなんてのは、ごくひとにぎりのファンのすること。ハードボイルドというジャンル自体が小説でも映画でもやせ細っている今、この小説を楽しめるのはごく少数だろう。マーロウものを読んだことのない人には、本書は1950年代のモノクロ映画を見ているような古臭い探偵小説としか感じられないはずだ。そんな小説を翻訳し、ポケット・ミステリの一冊として刊行したあたりに編集者の心意気を感ずる。
「ハードボイルドは男のハーレクイン・ロマンス」と喝破した斎藤美奈子さんを待つまでもなく、今ではこういう古典的なハードボイルド自体、パスティーシュかパロディとしてしか成立しない。でも、ファンとしてはファム・ファタールとマーロウの時代がかったやりとりに、「政治的に正しくない」男目線の物語と知りつつ心ときめかす。そんなギルティ・プレジャーに身をひたして3晩楽しみました。
ただひとつ残念だったのは、『ロング・グッドバイ』で小説に香気を与えていたマーロウとテリー・レノックスの友情物語が、『黒い瞳のブロンド』ではテリーがただの悪党に成りさがってしまって友情が成立しなかったこと。だからマーロウは最後に<ヴィクターズ>へ行ってもギムレットを注文しないで終わる。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





