誤植文学アンソロジー 校正者のいる風景【高橋輝次 編】
誤植文学アンソロジー 校正者のいる風景
| 書籍名 | 誤植文学アンソロジー 校正者のいる風景 |
|---|---|
| 著者名 | 高橋輝次 編 |
| 出版社 | 論創社(230p) |
| 発刊日 | 2015.12 |
| 希望小売価格 | 2,160円 |
| 書評日 | 2016.03.17 |
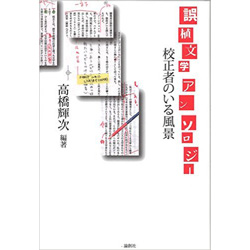
本書はタイトル通り、「校正」という仕事とそれに携わる人間たちをテーマとした、小説編とエッセイ編、各々8つの作品から構成されている。文章のプロとして禄を食んでいる人たちの文章だけに業界の状況や校正に携わる人々の姿、校正の仕事などが詳細に描かれている。戦前の作品を含めて年代的には幅広く選択されていて、このテーマに取り組んできた編者の努力というか執着心が見えてくる一冊だ。小説では校正者の仕事ぶりや人物像を主題に描かれたものが多く、エッセイは校正の仕事と誤植について語られていることを考えると、タイトルの「校正者のいる風景」は小説編を「誤植文学」はエッセイ編を、イメージしたように思える。
取り上げられている作品の内、佐多稲子、吉村昭、杉本苑子、杉浦民平といった作家以外は、はじめて文章に接する方々のものであった。本書のような、アンソロジーという形態では編者の視野の広がりが重要な要素であるだけに、読者として初見のものに出合うこと自体も楽しみの一つと言えるのだろう。それにしても、評者のような出版業界の門外漢としては「著者が居て、本が手元にある」という出版プロセスの頭と尻尾しか認識できていないだけに、全体のプロセスの中で編集者とか校正者をはじめとした多くの人々の、仕事の内容や成果物、必要な技術・資質などについては判っていないというのが正直なところである。
そんなこともあり、「校正」という仕事に対するイメージや先入観が有るわけもなく、本書を読む限りの理解では、「校正」が上手くいかなければ「誤植」として書籍が世に出てしまうというプレッシャーが強い職業だけに、登場する人物は多少の誇張があったにしても職人気質の執着型の人間が多いというニュアンスは否定のしようもないようだ。色々な校正者が描かれているが、特に「文学」と「校正者」の係わりにおいて面白く読んだ。小説家を目指しながらその志を達成できない人、出版界という小説家の周辺にある場所に身を置いて地道・緻密な仕事に没頭している人、孤独な仕事だけに対人関係は不器用で思い込みが強く自らにも厳しすぎる人など、どこか挫折と影のある人物像が描写されている。
「四十の坂を越えながら、便々として校正の朱筆をはしらせている行間さんにも、作家志望という果敢(はか)ない夢があった。……校正係なら校正係で好い。決して恥ずべきじゃない。文化面に働く一員である自覚とともに真剣にやるべきだ……『文学』はお前の怠惰な生活の口実にすぎないのだ」(河内仙介・行間さん・昭和17年)
「実に怖るべきは文学というものの仕業である。ということは彼が決して心に夢みていたような小説家にもならず、二十年あまりもの間をかくの如く他人の書いた小説をただひたすら校正している現在が証明している」(和田芳恵・祝煙・昭和17年)
こうした厳しい仕事の中で追い詰められていく校正者も鬼気迫るテーマとして取り上げられている。編者の高橋も「情けないことだが、私も自分の担当した本に誤植が見つかると冷や汗をかくのとは対照的に、自分が読む他社の本の中に誤植を見つけると思わず一寸うれしい感情がわき起こる」と正直な気持ちを語っている。そうしたプレッシャーから起こってくる人格の歪みを徹底して描いている文章を読み進んでいると「校正恐るべし(後生畏るべし)」という杉本苑子の言い方も説得力が増してくるし、「校正とはマイナスを『ゼロの地点』に引き上げる仕事である」という小池昌代の言葉にある通り、間違いは無くて当たり前という、はなはだ達成感の得にくい仕事であることも良く判る。
「校正している作品が私自身の評価ではどうしても没書にした方がいいと思うのに、出資者に対する義務とかにしばられてのせなければならなくなった時、その校正をしていると嘔吐をもよおすような本能的嫌悪感を感ずる」(田中隆尚・爐邊の校正・昭和56年)
「三山は厳格で鳴る校正者だった。……そのいささか円満さの欠く人格を揶揄して『赤魔』というあだ名が奉られるようになった。……いかなる本でも、三山は内容を読んで楽しむことがもはやできなくなってきた。…他社の本に誤植を見つけるとえもいわれぬ快感を味わうことができた」(倉阪鬼一郎・赤魔・平成11年)
「校正」をはじめとして「編集」や活字を拾う「文選」、レイアウト指定に従って活字を組み上げる「植字」といった仕事について、本書を通して多少なりとも理解することが出来たものの、それは、戦前から戦後の伝統的な活字文化の中のプロセスということも判る。出版の仕事が大きく変化したのは、活字からコンピューターによる原稿作成やレイアウトの自動処理などが当たり前になってきた1970年代半ばからである。これは社会全体としては生産性向上や効率化の享受であったものの、反面、そこでは均一化が追求されていった。従って、情報技術の進展は出版の世界でも、仕事の進め方やプロフェッショナルの在り方もまったく変えてしまった。「校正」という分野に焦点をあてた小説が過去の職人的な仕事として表現される時代になってしまったのも時代の流れとしか言いようがない。
「なんといってもわれわれは石炭と蒸気機関車時代の人間だ……パソコンに向かって仕事をしている若い人達を『新幹線世代』とつぶやく職人がいる」(川崎彰彦・芙蓉荘の自宅校正者・昭和59年)
技術の進歩は手仕事としてのプロフェショナルを駆逐していく。一方、この編集・校正という領域で育てられてきた人とその技術は、出版産業という観点からだけでなく、ある種の文化としてとらえる余地を我々は持てるのだろうか。それとも、編者の高橋が言うように「コンピューター時代の新しい校正の小説はどんなものが現れるのだろうか」という新たな環境の違いに期待をかけるのだろうか。
手法は変わっても人間は間違いを犯す。今までに数えきれない誤植があり、その悲喜こもごもは察するに余りある。作家も編集者もそして校正者が一番心を痛めたに違いない。本当の話かどうか判らないが、こんな誤植が紹介されている。笑ってしまうとともにホッとするエピソードだ。
「ミスコーベを募集した時のチラシで応募書類条件の中に『上半身写真』とすべきところを『下半身写真』と誤植してしまった」(宮崎修二・植字校正老若問答)
学生時代の昭和40年代半ばに、とある出版社で国語辞典の第二版作成用に追加語句の説明文案を作るバイトをした。当時は活版なので、新しい語句の追加や、既存語句の削除・説明字数削減など、ページを跨った組版の変更を最小化するための作業が行われていた。バイトなので、その作業の全貌を知ることは無かったが、「手作業」と「工夫」と「遊び心」で本が作られていた最期の時代だったとすると貴重な体験をさせてもらったと感謝しつつ、今となっては懐かしい思い出である。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





