木村伊兵衛のパリ【木村伊兵衛】
木村伊兵衛のパリ
| 書籍名 | 木村伊兵衛のパリ |
|---|---|
| 著者名 | 木村伊兵衛 |
| 出版社 | 朝日新聞社(287p) |
| 発刊日 | 2006.7 |
| 希望小売価格 | 1470円(税込み) |
| 書評日等 | - |
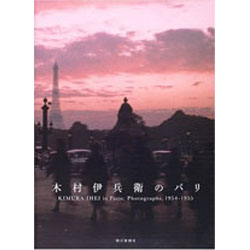
1954-55年にカラー・フィルムで写されたパリ。その色調はフィルムの特性か、レンズの特性か、あの時代のパリの色あいか。はたまた木村伊兵衛の気持ちを映した発色なのか。多少鮮明さを欠くものの繊細な色調の写真を見ていると、鑑賞する側の捉え方に自由度を許容する懐が深い作品が多い。
1954年にはニコンSとライカM3を使いフィルムはコダックとフジのカラー・フィルム。1955年はライカM3とフジのカラー・フィルムで撮影されたもの。フジのカラー・フィルムは昼光でASA10とのことで、写真を撮る側の制約の大きさは想像に難くない。この渡仏時の作品はいろいろな形で公表・出版されてきているが、今回はその作品を一気に写真集としたものである。
カラー写真の位置づけはコマーシャルやポートレートのためのツールという考え方がまだまだ強かったと言われていた中で、パリという素材を前にして、あえてこのカラー・フィルムを使うという挑戦や、現在に比べて外貨規制は厳しく、民間人の海外渡航は原則不可能であった時代に渡仏するという挑戦。そうした取り組みに木村の意気込みの強さを感じるのである。結果として170点のカラー作品を成果として残したわけで、木村の力量を実感できる写真集であると同時に1947年生れの評者にとっては同時代的の感性としては捉えることの出来ない時代であり場所であるにもかかわらず、なぜか皮膚感覚として納得感の残る作品が多いのもこの写真集の特徴である。
「夕景のコンコルド広場」という写真。本書のカバー写真にも使われているものだ。薄い紫色の空と雲の交錯、黒くそそり立つオベリスク、遠く靄にかすむエッフェル塔、運転マナーの悪そうな自動車群、歩く人々。煤けたような薄暗さが見る人に不安感さえ与える写真。その中で、車や人の動きを辛うじて捉えているのも、一日の光の最後の瞬間を表現しているのも使用されたカラー・フィルムの特性が十分に出ている。フィルムの限界を知りつつ、それでもこの夕景を撮ろうとした木村の写真家としての強い意志が感じられる一枚だと思う。
「楽屋裏のモデル達」という作品は、5-6名の人物が画面に存在している為、いささか雑駁な印象も感じる。ただ、ASA値が低いため絞りは開放に近くして撮ったためだろうか焦点深度は浅く中央の婦人の表情は切り出したようにシャープにとらえられている。この作品はイメージとしてはモノクロームとの印象さえ残るのだが、それだけ周囲の色を押しのけて黒いドレスの中央の婦人が強い存在感として表現されているということ。カラーでありながら黒いドレスの女性を際立たせるこの作品はカラー写真としての完成度の高さを感じさせられる。この写真集の中で金子隆一が言っている「プラスアルファとしてのカラー写真」を体言している一枚だ。
木村にとって1954-55年という時期にパリに行くという意味はどんなものだったのだろうか。カルティエ・ブレッソンやロベール・ドアノー等を始めとする世界の名だたる写真家たちとの交流や、そこでの触発も貴重な体験だっただろう。それは想像するだけでも同時代性の圧倒的な力を感じてしまう。また、カラー・フィルムという新しいツールの利用。こうした挑戦的な渡仏の結果は、10年・20年・30年と時間が経過する中で、作品の評価を確実に高めてきたのではないか。「木村伊兵衛ヨーロッパ撮影日記抄」という文章にこんなことが書かれている。
「・・・カラー・フィルムを富士にしたのは、コダックの強い色彩が私にはなじめないからなのです。富士のパステルカラーのような色彩がどうしても自然の感じがしてなりません。ヨーロッパに来てみて、今までコダックでとったカラーとはちょっと違ったしぶさを感じています。フジ・カラーがうまくゆくと、ヨーロッパの色を出すのにいいのではないかと考えております。・・・」
写真表現における、カラーへの確たる思いが木村によって語られている。その意味で本書に載せられている写真たちは木村の確信から生れたものであることが良くわかる。
多くの芸術家をひきつけるパリは独特な場所である。今橋映子が名づけた「パリ写真」とさえ言われるジャンルを持つ都市である。個人的にはパリに1970年代、1980年代、1990年代と十年毎に仕事で訪れたことがあるが、その間、あまり変化を感じさせない都市空間であったと記憶している。新しいオフィス街がデファンス(1970年)に作られたり、ルーブル美術館の中庭にガラス張りのピラミッド(1989年)をつくるなどの象徴的な変化はあったのだが、都市としての外観的な変化の幅は他の都市に比較して非常に限定されたものであったと思う。
1970年代の初めに初めてパリを訪れたとき泊まったホテルは建物の古さもさることながら、エレベーターの扉もガシャガシャと乗った人が自分で手で閉めるものだった。そうした古さが残るパリという都市および生活者に対し芸術家達がひきつけられるにしても、それは物理的な都市空間というよりも、木村の被写体たる、生活する人達やその生活臭が創作意欲をかきたてるのだろう。この写真集を見ていると、パリでの木村の開放された感覚が見える。異文化に接し、それに対する素直な興味がシャッター・チャンスを生んでいるように思う。たまたま、今年(2006年)の二月、1938年に出版された「Japan Through a LEICA / Ihee Kimura」が国書刊行会から復刻されている。そして、七月末に本書「木村伊兵衛のパリ」が出版された。
この二つの写真集を並べて見ていると「Japan Through a LEICA」が捉えている日本人の姿は木村自身が被写体の次の動きを想像しながらシャッターを押している。そこには、ある種の計算がきっちりとされていると思う。一方、本書の作品は計算以前に木村が面白いと思った時がシャッターチャンスであったと思えて仕方がない。どちらの写真も魅力的であるが、より自由で「素」の木村をこの写真集で見ることができる。
先日、仕事を終えて帰宅すると封書が届いていた。「木村伊兵衛のパリ - 空間デザイン:コンスタンティン・グルチッチ」というExhibitionの案内状だった。銀座のMaison Hermesで行われるという。本写真集のタイトルである「木村伊兵衛のパリ」を感じつつ同時に「パリの木村伊兵衛」も考えてこの書評を書いたのだが、HermesのExhibitionでまた違った木村伊兵衛を発見できるのかもしれない。 (正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





