海路としての<尖閣諸島>【山田慶兒】
海路としての<尖閣諸島>
| 書籍名 | 海路としての<尖閣諸島> |
|---|---|
| 著者名 | 山田慶兒 |
| 出版社 | 編集グループSURE(160p) |
| 発刊日 | 2013.11.03 |
| 希望小売価格 | 2,450円 |
| 書評日 | 2013.12.15 |
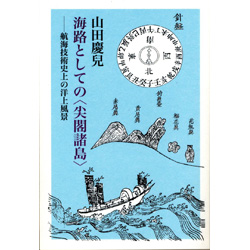
サブタイトルには「航海技術史上の洋上風景」とある。著者の山田慶兒は東アジア科学史の専門家。『中国医学はいかにつくられたか』や大佛次郎賞を受けた『黒い言葉の空間』などの著書がある。学問の世界で高い評価を受ける専門家が現実の政治問題、しかも尖閣諸島という日中間で炎上しているホットなテーマを取り上げたのが本書である。航海技術史という窓から見ると、尖閣諸島にはどんな風景が広がっているのか。
尖閣諸島が初めて文献に現れるのは中国の明代で、例えば『順風相送』には「釣魚嶼(魚釣島)」「黄尾嶼(久場島)」「赤尾嶼(大正島)」と記されている。『順風相送』というのは東アジアの海洋を航海するための指南書だ。こうした指南書は船乗りたちの間で書き写され、伝えられたハウ・ツー書で、彼らは必要に応じて手を加え、自分だけの冊子をつくった。それは自分だけのものであると同時に、仲間から伝えられ、仲間に伝えもする船乗りの共有財産でもあった。
この指南書に尖閣諸島が取り上げられるのは、明国の福建と琉球王国の間に航路(福琉航路)が開かれていたからだ。琉球は毎年のように明に進貢使を送って朝貢した。明もまた琉球に冊封使と呼ばれる使節を送った。その往来のために、福琉航路はいわば「定期航路」のようになっていた。福建から琉球への往路は台湾北岸から尖閣諸島を経て島づたいに琉球へ行き、復路は東シナ海を突っ切って一気に中国大陸を目指す。指南書に従って海上で実際に航路を指示するのは火長(航海長)で、火長は船戸(船長)に次ぐ地位にあった。
この時代、遠洋航海は天文航法と羅針盤航法が併用されていた。天文航法は星の位置や角度を測りながら進路を決める。羅針盤航法は羅針盤が示す方位を頼りに進路を決める。羅針盤航法の場合、航行の道標となるのが島々で、だから航路上の島にはすべて名前がつけられた。清代の『指南広義』にはこう書かれている。
「福州から琉球へ行くには、東沙山の外で船出して、単辰(注・東南東)針を用いること十更(一更は六十里)、鶏籠頭(台湾北方の島)へ行き、…乙卯(東東南東)並びに単卯(東)針を用いること十更、釣魚台へ行き、北を過り、…単卯針を用いること十更、黄尾嶼の北を過り、甲卯(東東北東)針を用いること十更、赤尾嶼へ行き、乙卯針を用いること六更、枯美島(久米島)の北を過り、…甲卯及び甲寅(東北東)で収めて琉球那覇港に入れば、大吉」
ところで、なんの目印もない海上で航行した距離をどう測るんだろう? 船には必ず一定の歩幅と時間で歩くことを訓練された水夫がいた。船首から水中に木片を投げ入れると同時に、水夫は後方へ流れる木片と平行して船尾に向かって歩いていく。水夫が船尾に着いたとき木片がどこにあるかで、その間に動いた距離が出る。もちろん風の具合や海流、波の有無によって船の航行距離は大きく変わるから計器で計ったような正確なものではないが、おおよそのことはわかる。また時間は砂時計によって計られていた。
そんなことも含め遠洋航海の技術は、おそらくイスラムの航海者から鄭和時代の中国の航海者に伝えられ、福琉航路のように新しい航路が開かれると指南書に情報が追加され伝承されていった。「いつの時代も遠洋航海者は一種の国際的階級であった。世界の海を駆け巡り、さまざまな国に寄港し、その交流を通して知識と技術を共有していたのである」と山田は書く。
記録によると、清国が琉球に送る船の舵手は琉球船の舵手に指南書を提供していた。また清が琉球に使節を送るのは2~30年に一度だったが琉球は毎年のように清に朝貢していたから、琉球の船乗りのほうが福琉航路に精通していた。琉球の船乗りが清国の冊封船に乗り込んで舵を取ることもあったという。彼らはそれぞれの国に属する以前に、遠洋航海の技術者としての一体感を持っていた。
このような技術を無効にしたのは、18世紀の鏡六分儀の発明である。二枚の反射鏡によって星の高度を測定し、そこから緯度と経度を割り出すことができるようになった。以後、海上の島々は航海に不可欠な道標ではなく、岩礁や浅瀬の目印にすぎなくなった。
尖閣諸島が再び人々の意識に上るのは近代になってからである。もっとも人々の目を引いたのは島そのものというより周辺の海で、漁業のための生物資源や鉱物資源だった。「資源を獲得し利用するにはまず島嶼を物理的に占有しなければならない。こうして所有・領土・国家といった観念がはじめてこの海域に持ちこまれることになる」。
1984(明治27)年、日本人実業家が尖閣諸島を探検し、翌85年、政府はこの無人島を領土に編入した。以後、国際法上の「先占の法理」──植民地獲得競争の時代にできたもので、無主の土地について最初に支配した国家の領有権を認める──によって日本は尖閣諸島を「固有の領土」としてきた。
こうした歴史的な事実を踏まえて、現在の尖閣問題を著者はどう考えているのか。そのことに触れる前に、別の立場からはこの問題がどう見えるかを紹介しておこう。元外務省国際情報局長・孫崎享の『日本の国境問題』(ちくま新書)はリアル・ポリティクスとして領土問題を冷静に論じた、その立場からは説得力のある本だ。孫崎は日本と中国双方が尖閣諸島の領有権を主張していることについて、こう述べている。
「先占の法理」について。「19世紀以前には、獏としてであっても中国の管轄圏内に入っていた尖閣諸島に対して、『これは“無主の地”を領有する“先占”にあたる』の論理がどこまで説得力があるか疑問である」。「領有権の問題はそもそも存在しない」という日本政府の見解に対して。「①中国は尖閣諸島を自国領とみなしている。②米国は1996年以降一貫して『尖閣諸島で日中のいずれの立場も支持しない』としている。③国際的に見ると、尖閣諸島は紛争地域であることがほぼ定着している。……こうして見ると、やはり国際的に『領有権の問題はそもそも存在しない』とするのは無理がある」。その上で孫崎は、日本政府は「棚上げ」に合意したことはないと言う、しかし中国には尖閣諸島を軍事力で奪取しようとするグループ(軍。「棚上げ」を放棄したい)と紛争を避けたいグループ(鄧小平以来の「棚上げ」論を維持したい)があるのだから、後者との協力関係を強めるべきであると述べている。
山田慶兒はこうしたリアル・ポリティクスの立場から遠く離れている。そもそも植民地獲得競争の時代に早いもの勝ちを認め、強者同士が共存するためのルールである「先占の法理」そのものを、「いずれ人類が乗り越えてゆかねばならない国際法の原理」とする。
「(領土問題を解決する道の)ひとつは、すべての当事国が領有権を放棄し、共同管理体制に移行することである。漁業権や地下資源の採掘権の問題は、そのうえでじっくり話し合って解決すればよい。それは国際法に新しい原理を導入するだけでなく、なによりも台湾をふくむ日中恒久平和への強固な一歩を踏み出すことになるだろう」
巻末の座談会で、山田はこの提案を「私の夢物語です」と言っている。確かに「先占の法理」を死守しようとする日本政府(外務省「尖閣諸島に関するQ&A」)も、それを力で覆そうとしている中国政府も、こんな考えは非現実的な夢想にすぎないと一顧だにしないだろう。
でも歴史を百年単位で見れば、近代の国民国家はたかだかここ数百年の特殊な産物にすぎない。「先占の法理」もそのひとつで、その法理に従って「合法的に」植民地分割されたアフリカが、第二次大戦後次々に独立し、いまそのことの正統性を疑う者はいない。多くの民族がいても国家と呼べるものがなかったアフリカと、尖閣諸島のような無人島では問題の性質が多少異なるけれど、「先占の法理」の根元に亀裂が生じていることだけは疑いようがない。
過去の歴史を見れば、百年単位の大きな変化も最初はほんな小さなひび割れから生ずることが多い。その徴候に敏感になり、大きな歴史の流れのなかでそれが何を意味するかを考えるのは、「現実的」な立場からは一見非現実的に見えるかもしれない。でも山田が描き出した遠洋航海者たちのゆったりした一体感と国際性は、ガタが来はじめた近代国家に生きる僕たちに、歴史には別の風景が存在したことを垣間見せてくれた。そのことを忘れることはできない。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





