開店休業【吉本隆明・ハルノ宵子】
開店休業
| 書籍名 | 開店休業 |
|---|---|
| 著者名 | 吉本隆明・ハルノ宵子 |
| 出版社 | プレジデント社(260p) |
| 発刊日 | 2013.04.23 |
| 希望小売価格 | 1,575円 |
| 書評日 | 2013.06.22 |
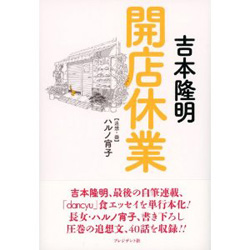
吉本隆明が死んで一年が経つ。当日テレビ・ニュースを見て「吉本リュウメイが死んだ」と家人に呟きながら、時代の変化を「誰かの死」という事象でしか体感しなくなっている自分に気づいたことを思い出す。吉本隆明に影響を受けた事は何かと問われても特段なにがある訳でもないのだが、「言語にとって美とは何か・第一巻」、「共同幻想論」の二冊は評者の使い慣れた本棚の一角に永らく陣取ってきているし、埴谷雄高の「虚空」とともに、なんとなく神棚のお札のような感じである。今年5月になって、立て続けに、「吉本」本が出版された。高橋源一郎と加藤典洋による「吉本隆明がぼくたちに遺したもの」岩波書店刊と本書「開店休業」である。
思想家の業績は二つの側面がある。一つは本人が語り、書き綴ることで自らの思想を表現している時代、いわば「本人の時代」と、死後に残された著作や記録から思想家の意味を読み解いていく、「素材としての時代」だ。吉本隆明もいよいよ「素材としての時代」に突入したのだが、彼の著作の読み手による理解の正否は別として、もはや本人は反論の機会がないだけに、「素材の時代」では思想家の功罪両面を語る人が多くなるのは必然であるし、評価の振幅も大きくなっていくのだろう。
本書は「Dancyu」に2007年1月号から40回に亘って連載された、食に関するエッセイを収めたもの。加えて、吉本の長女であるハルノ宵子が各エッセイに対応して文章を書いている。それは家族の視点からの追想であり、それだけに嫌が応でも家庭人・吉本隆明をより鮮明に浮かび上がらせる効果を出している。40回のエッセイは、伝統行事とそれにまつわる食べ物、食材の好き嫌い、血糖値をコントロールするための家族との確執、両親の思い出などが日常の自分史という感覚で書き綴られている。
「Dancyu」といえば男の料理本として確たる市場を築いた先駆的雑誌であるが、当時の担当編集者の回想によれば、連載開始時はすでに吉本の自筆の文章は世にほとんど発表されておらず、当然聞き書き形式になると想像して依頼に行ったという。
「返ってきた言葉は『書く』というものでした。びっくりしたというか、戸惑ったというか難解な原稿が来たらどうしようと自筆の原稿を快諾していただきながら、なんだか不安でいっぱいだった」
食べ物雑誌であることを考えれば、吉本が原稿を書くとなると、話の中身の難解さ、表現の難解さ、など編集者としての心配は当然だろう。そうした心配が杞憂であったことは本書を読んでみれば良く判る。吉本も雑誌の特性を十分理解して書いているとしても、そこまで擦り寄らなくてもと思ってしまうぐらいの平易な文章になっている。雑誌連載時と違い、単行本になって一気に通読すると気になるのは、吉本の現在と過去とを行きつ戻りつしている文章や、根津の煎餅屋の話や、月島に三浦屋の肉フライ、巣鴨地蔵どおりの塩大福、など複数回出て来る事象も多い。吉本自身が時を反芻しているように思えるのも、彼にとって料理の味というのは絶対的なものではなく、相対的なものと考えていたことにも起因するようだ。
「わたしの勝手な判断だが、料理の味は味そのものではなく、味にまつわる思い出や思い込みなど味にまとわりついている想像力に左右されるところが大きいと思う・・・少なくとも少年期や少女期は食べ物について言えば、二度やってくる気がしている。一度は父母の味付けをうまいうまいと信じて食べるものとして。もう一度は自分たちの子供時代に味わった食べ物の味が本当だったのか、懐かしさを確かめる者として」
本書の面白さは、吉本の食のエッセイということもさりながら、家族だけが知る吉本の日常をハルノが巧みに表現しているところにあると言える。例えば、吉本が戦後すぐに椰子油から石鹸原料の硬化油の作り方を朝鮮系の会社に教える内職をした際にキムチを初めて食べて美味い物だったという記述に対して、
「父のこのエピソードだけは初耳だった。思わず『ウッソだろー!!!』と声を出してツッ込んでしまったほどだ。キムチはおそらく父の最も苦手とする味のはずだ、まず父はニンニクがダメだ。・・また、魚介が発酵したアミノ酸風味も”得体の知れない味”のはずだ。・・酸味がまただめだった」
こうした好き嫌いについては家族しか判らないところであるし、別の項では「魚」が嫌いとも言っていることを考えると、吉本の偏食はかなりのものだったことが判る。とは言っても食べることに関する執着は強く、それだけに血糖値のコントロールには苦労していた様子が随所に表現されている。「落ちていたレシート」と題されたハルノの文章、
「食べる父と止める母の戦いは熾烈を極めた。・・・完璧主義の母のことだ、常軌を逸した形で計算し尽された一日1800Kcal以内にするメニュー・パターンを記入したカードを作っていた。・・・ある日キッチンにレシートが落ちていた。『上野精養軒ビアガーデン』生ビール1,ミックスピザ1,焼き鳥1,フライドポテト1。「凮月堂」生ビール1,豆腐グラタン1,スペシャルサンド1-------といった具合だった。いずれも一名様。レシートには父の夕方の散歩の時間帯が記されていた。この”間食”だけで、一日の総摂取カロリーを超えている。キャパクラのマッチが落ちているより恐ろしい結末となった。当然のことながら母はブチ切れ、その後一切の炊事を放棄し、以後二度と台所に立つことは無かった」
また、妙に分析的な文章もある。東工大卒の吉本らしく、お茶・果汁・ジュース・紅茶・コーラ等を、冷蔵庫で冷す、常温になったところで飲む、常温のまま蓋をして翌日飲む、というケースで各々の味の変化について延々と書いている。あまり客観的とも思えないものであるが、その締めくくりは吉本らしいものである。
「このことで自己主張したいという見識もない。それでは無意味だと言われたら、そんなことは無いよと答える。一人のシンカーは思想家であるかどうかはわからないが、思想者であることは確かで、無意味なことに耐えることを身上にしている者を指している。場合によっては職業とすることもありえる」
この開き直り風の言葉に対するハルノの意見は、
「基本理系・・・言い換えるならオタクなのだ。・・・ある一線を越えた瞬間から意地をかなぐり捨て、限りなく自分を許す------というのも、父の珍妙な特質だと思う」
かように家族の視線は厳しい、しかし同時に限りなく優しい。日々、身体能力や記憶力が薄れていく父親が旅立っていく姿を予感するハルノは最後にこう書いている。
「父の前に立つと、『すまないが氷の入った水を一杯くれないか』と父は言った。その言い方がこれまでの父とは違って、あまりにもニュートラルだったので、私は驚き、・・・ミネラルウォーターにロックアイスを入れて父に差し出した。父は『ああ・・うまい!! うまいなぁ』と飲み干すと這って寝に行った。・・・私は人間のこれほどまでに含みの無い言い方を聞いたことが無い。歩き疲れた旅の僧が村に差し掛かり、はじめて出会った村人に『すまんが水を一杯所望したい』と言う・・・そんな言い方なのだ。そこには懇願も、媚も、威圧も、取引もない・・・もう家族のもとには帰ってこないのだという予感だけがあった。父は一介の僧となって旅に出てしまったのだ」
是非、吉本の「家族のゆくえ」2006年とともにこの「開店休業」を読んでみてほしい。吉本の家族観と現実の家族としてのハルノ宵子の言葉の相乗効果によって、吉本の思想と行動の連動を見せてくれる。介護をし尽くしたであろうハルノの文章は思想者たる吉本を看取った爽やかささえ感じられるのは救いである。タイトルの「開店休業」の意味は「Dancyu」編集長があとがきに書いている。多分、吉本隆明も満足するタイトルだろう。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





