検証 バブル失政【軽部謙介】
検証 バブル失政
| 書籍名 | 検証 バブル失政 |
|---|---|
| 著者名 | 軽部謙介 |
| 出版社 | 岩波書店(432p) |
| 発刊日 | 2015.09.26 |
| 希望小売価格 | 3,024円 |
| 書評日 | 2015.11.19 |
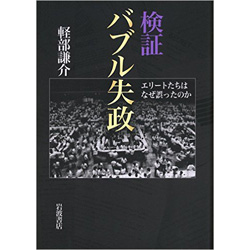
本書は1986年から1991年の所謂バブル期における、日本銀行・大蔵省・政府・そして海外を視野に公文書、未公開資料(オーラルヒストリー、手記)、直接のインタビュー等を通して「なぜバブル経済が生じ、崩れたのか」「誰が何を行い、または行わなかったのか」を時系列的かつ詳細にまとめたものだ。
著者の軽部謙介は1980年代後半に時事通信の大蔵省担当の記者だった経歴である。その意味ではその期間の現場に立ち会っていたという人間である。団塊の世代にとっては、バブル経済の発生から崩壊に至る時代はそれぞれの個人史を持っているはずだ。しかし、著者も「『これはバブルだ』と確信して毎日を過ごしていたわけでなく、狂乱や金満を正当化するさまざまな理屈を疑う事なく受け入れ、経済の底流で何が起こっているのかなどは視野の外だった」と書いているように、評者にとっても、金融機関の巨大システム開発プロジェクトのメーカー側の責任者として日夜翻弄されていた時期であり、投資目的の「株」や「土地」を持っていたわけでもないのでバブル経済の高揚感を実感することもなく、差し迫った危機感は希薄だったと記憶している。どちらかと言えば、バブル崩壊後の苦労のほうが生々しく記憶に残っているのだ。
本書は極めて精緻で多くの当事者たちの証言を集めていることもあり、読者としては時として論点の細部に迷い込みがちであった。
バブルの生成の原因と言われている「金融緩和の長期化」という観点から1985年の「プラザ合意」によって円やマルク高への誘導策として先進国間の国際収支不均衡を是正するための為替調整が決定されたところから本書は始まる。この円高によって日本の輸出産業は不況に苦しむ一方、急激な円高に対応するための当時の日米の政府間の交渉、日銀内部の意見対立などを含めて、数次に渉る公定歩合引き下げによる「金融緩和」の経緯と内需の拡大に進む姿を検証している。
次のポイントは1987年以降の日米間の経済摩擦に伴い日本脅威論が高まりを見せ始めたなか、所謂「BIS( Bank for International Settlements)」の「バーゼル合意」によって「金融機関の自己資本規制比率」が決定される。BISとしては当初、株の含み益を自己資本に組み込むことを一切認めない方針であったことを考えると、大蔵省の踏ん張りで45%とはいえ自己資本に算入可能とした妥協案によって邦銀が国際市場から退場させられるという最悪の事態を回避できたものの、それはリスクを内在したままになったということでもある。また、「ブラック・マンデー」を乗り切った後、公定歩合引き上げを1989年5月まで行わなかった日銀の金融緩和の継続の判断についても著者は批判的な目を向けている。この「金融機関の自己資本規制比率」と「金融緩和の継続」こそが生成されつつあったバブル拡大の背中を押して、まさにピークに向かって疾走していたという見方である。
1989年には日銀総裁は大蔵OBの澄田から日銀プロパーの三重野に交代し、政策を転じて公定歩合の上昇に舵を切った。年末の株価は市場最高値を付けたものの、年明けには株価は下落に転じた。一方、地価は引き続き上昇し続けたことから大蔵省は遅ればせながら「金融機関の不動産関連融資規制・総量規制」を発動する。この政策がバブル崩壊の決定打ともいわれている。
日本のバブル経済を軟着陸させる政策は結果的に失敗し、失われた20年と言われる状況になったわけだが、一連の経緯を読むにつけても実態経済活動の中でなにが起こり、経済の底流にどんな影響を与えるのかについて既知の理論的な範囲でしか想定出来なかったのが、大蔵・日銀の俊英たちの限界であったと著者は見ている。経済を解く方程式は複雑であることは事実であリ、経済政策においては何が良い政策で、何が悪い政策かを判断するのは簡単なことではない。常に外部の要因(国際情勢・エネルギー・災害・国家破綻・気候変動等)で左右される。それだけに、経済政策・金融政策のキープレーヤーである政治とりわけ総理大臣・大蔵大臣を中心とした官邸、大蔵省、日本銀行が各々の思惑を持ちつつ政策決定がされていく姿や、国外(米国)からのプレッシャーによって翻弄される姿が見て取れる。
そこにあらわれてくる各国交渉のしたたかさを見るにつけ、日本の国中では省庁間、省内局間のせめぎ合いや政治家の顔色を観つつ日銀との折衝をするといった行動では総力戦とは言い難い部分でエネルギーが割かれていたと言わざるを得ない。同時に、組織ありきの志向を支える人事制度の問題も見えてくる。本書の捉えている時代を中心とした10年間(1984年から1994年)で日銀総裁は澄田・三重野の二人であるが、同じ時期に大蔵大臣は竹下登から藤井裕久まで8名、大蔵次官は山口光秀から斉藤次郎まで8名が名を連ねている。大蔵大臣と大蔵事務次官がほぼ毎年変わっていくという実態は、各種国際会議や会合で毎年顔の変わるメンバーで濃密な対話や信頼が生まれるわけはないし、必然的に責任感も生まれないと思わざるを得ない。
「三重野はこう語っている、『まあ旧法の時代ですし、なかなか自分の思い通りにはいかないこともありましたけども、とにかく私は自分の思ったことは大体やったので・・・』旧日銀法とは戦時立法であり、政府の日銀に対する『一般的な業務指揮権』が定められていた。公定歩合についても『日銀の専管事項』と言っていたものの実質は日銀と大蔵の合議であり、加えて官邸がそこに口をはさむといった状況だった。この中で、三重野が『2年3ヶ月』にわたる史上最低の公定歩合(2.5%)を続けたことによる『金融政策』としてのバブル生成の責任については認めている。しかし、バブル崩壊後の10年間の日本経済の低迷について金融の引き締め過ぎが原因ではなく、新しい構造に日本経済が対応しなければいけないのに、それが遅れた事、企業が変化に対応するという前向きな努力を怠っていたため」といっている。
なかなか微妙な言い回しではあるが、しっかりと「金融政策」だけで国家経済は支えられないと三重野は言っている。その視点は現在の日本銀行、ひいては黒田総裁について、著者の思いを間接的に伝えていると捉えるのは評者の思い過ごしだろうか。
思えば、1989年、三菱地所によるNYのロックフェラーセンターの買収はアメリカ人にショックを与え、評者の体験で言えば、日本の生保が企画・開発した豪華なゴルフコースの会員権を買う報告を米国本社に伝えたところ「ゴルフ場を買うのか」と確認が来たり、日本興業銀行が大阪の割烹料理屋の女将に貸し込んだあげく4000億円を超える負債の詐欺事件の発生に仰天したりしたものだ。こうしてみるとバブルのシグナルは多々あったのだが、日本が良かれ悪しかれ世界に注目されていた時期において、そのピークを制御することが出来ず日本経済は沈んで行った。
その後、長きに亘りあらゆる業種で業績が低迷しリストラと新卒採用の低下が社会全体を不安な方向に引きずって行ったといえる。しかし、著者があとがきに書いている「大蔵官僚や日本銀行の当事者の多くは、退職後も比較的恵まれた生活を送れた」とするメッセージは蛇足だろうと考える。もし、その点を強く指摘するのであれば本書の視点はまた変わったものになるはずだ。著者は、責任のある立場の人間は「能力のあるなし」ではなく、「プロとして誠実に判断し行動したのか」が問われるのだと訴えていると思うのだが。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





