グリニッチ・ヴィレッジにフォークが響いていた頃【デイヴ・ヴァン・ロンク】
グリニッチ・ヴィレッジにフォークが響いていた頃
| 書籍名 | グリニッチ・ヴィレッジにフォークが響いていた頃 |
|---|---|
| 著者名 | デイヴ・ヴァン・ロンク他 |
| 出版社 | 早川書房(392p) |
| 発刊日 | 2014.05.15 |
| 希望小売価格 | 2,700円 |
| 書評日 | 2014.07.16 |
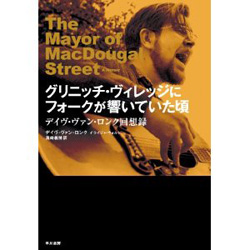
高校時代の一時期、ピーター、ポール&マリーが好きだったことがある。『グリニッチ・ヴィレッジにフォークが響いていた頃』(原題:The Mayor of MacDougal Street)を読んでわかったのは、この本が描く1960年代ニューヨークのグリニッチ・ヴィレッジの空気に僕がはじめて触れたのはPP&Mの歌を通してだったことだ。
東京近郊に暮らす高校生がPP&Mに惹かれたのは、いま考えると理由が二つある。ひとつはマリー・トラヴァースの声と姿が魅力的だったこと。20代後半のマリーは、真っ直ぐなブロンドとぶ厚い唇が魅力的な「年上の女」の風情をたたえていたし、その声は低音がちょっとしゃがれ、それまで聞いていたアメリカン・ポップスの歌い手とはちがう大人の気配が感じられた。
もうひとつの理由は言うまでもなく彼らの曲。「悲惨な戦争」「花はどこへ行った」「天使のハンマー」「風に吹かれて」(PP&Mのカヴァーが世界的にヒットしたことでディランが売れた)なんかで、60年代半ば、ベトナム反戦が燃え上がりはじめた時代のメッセージ・ソングだった。うぶな高校生はころりといかれて、PPMフォロワーズ(小室等)のソノシートを買ってきて、その頃習っていたクラシック・ギターから転向して独習でコードを覚えたりした。どこにでもいるフォーク少年のひとりだったわけだ(やがてジャズにのめりこむのだが)。
そのPP&Mは1960年代初頭のグリジッチ・ヴィレッジで結成された。本書の著者、デイヴ・ヴァン・ロンクのマネージャーでもあった人物が女性1男性2のトリオをつくろうと人選をしていたころ、ブルース&フォークの歌手として評判だったデイヴにも声をかけたという。でもデイヴはそれを断った。ソロでやっていける自信があったからだ。PP&Mのデビュー・アルバムにはデイヴが作曲した「バンブー」が収録されている。
YouTubeで聞くとデイヴの歌は荒削りで、ブルースっぽい節回しとシャウト。やがて世界的スターになる後輩のボブ・ディランとちょっと似てる。トリオの一員としてマリーの背後でハーモニーをつける役どころには、どのみち向いてなかったろう。デイヴ自身、「ピーター、デイヴ&マリーなど、なぶり殺しの目にあっていたはずだ。声でも見た目でも(注・ひげもじゃの熊みたいな風貌だ)、とにかく私は浮いてしまったろう」と語っている。
そんなこともあってだろう。日本の高校生がファンになるほど世界中で売れたPP&Mに対して、デイブは複雑な胸の内を吐露している。「あれ(『バンブー』)は私が書いたなかで唯一カネになった曲だが、大嫌い」。その一方で、「お上品ではあったがひと味ちがうグループだったし、いまとなっては彼らが人気になったのも当然だと思う」とも言う。本書は、2002年に亡くなったデイヴが晩年に友人で作家のイライジャ・ウォルドに語ったものを、デイヴ没後にイライジャがまとめたものだ。
デイヴ・ヴァン・ロンクは1936年、ブルックリンでアイルランド系労働者の家庭に生まれた。祖母や育ててくれた叔母が音楽好きで、ラジオからはデューク・エリントンやファッツ・ウォーラーが流れていた。ウクレレを演奏するようになり、ブルースにも目覚めた。
ブルースを聞くようになって初めての夏休みに衝撃を受けた曲が「セント・ジェームズ病院」だった。コードとメロディを覚え、夏休みの終わりには「いまだかつて誰も耳にしたことのないくらいファンキーな『セント・ジェームズ病院』のウクレレ・ヴァージョンが弾けるようになっていた」。ちなみにYouTubeでもデイヴのこの曲を聞くことができる(もちろんギター・ヴァージョン)。とてもいい雰囲気。僕もこの曲は好きで、レッド・ガーランド・トリオの名演(「When There Are Grey Skies」収録)は今でもよく聞く。
やがてウクレレをギターに持ち替え、15歳でグリニッチ・ヴィレッジのワシントン・スクエア・パークで開かれるフーテナニー(注・自由参加の音楽パフォーマンス)に出かけた。これがプロのミュージシャンへの第一歩だった。やがて彼は家を出て、ヴィレッジにいついてしまう。
ヴィレッジのデイヴがどんなだったかは、この本を原作にしてつくられた映画『インサイド・ルーウィン・デイヴィス』がその空気をすごくよく伝えている。映画ではルーウィン・デイヴィスという名前になっているが、知り合いの家にころがりこみ、追い出されると次の知り合いを探し、仲間の女性に手を出し、プロデューサーに歌を聞かせても「カネの匂いがしないな」とすげなくされ、どこへ行くにも無銭のヒッチハイク。そんな貧乏生活をしながらジャズやブルースにのめりこむ。やがてジャズをやっていた頃は「田舎者のへぼ音楽」と軽蔑していたフォーク・ミュージックにも惹かれてゆく。
映画では触れていないし、この本で初めて知ったのは、ヴィレッジには極少数派だろうけど共産党員、アナキスト、トロツキスト、サンディカリストといった50年代のマッカーシズムを生き延びたさまざまな左翼が存在していたことだ。デイヴも自由意思主義連盟(リバタリアン・リーグ)に所属するアナキスト、あるいはトロツキストとして政治集会に出席して歌っている(今ではリバタリアンと言えば右派自由主義者のことだけど、リバタリアンは右から左までさまざま)。
いかにも彼らしいのは、共産党系「スターリニスト」シンガーが政治的な歌を好んだのに対して、「純粋に美学に基づく決断」から政治をテーマにした曲は「ほとんど歌わなかった」ことだ。デイヴ曰く、「左翼の家具職人だからといって左翼の家具を作るとは誰も思わないだろう?」 こういうのがデイヴ・ヴァン・ロンクの素敵なところだ。
1950年代から60年にかけてのグリニッチ・ヴィレッジには政治的にいろんな潮流が流れ込んでいただけでなく、音楽もジャズ、ブルース、フォーク、文学もビートニクがいて、それらを商売に結びつけようとする人間がいて、詩の朗読やライブのカフェがあり、小さなレコード会社があり、いくつものミニコミがあり、もちろん酒とドラッグがあって、アメリカのアンダーグラウンド・カルチャーがごちゃごちゃに交じり合っていた。
住むにしても店を開くにしても、ヴィレッジは家賃が格安だった。デイヴはブルース&フォークの歌い手として評価を得て、「マクドゥーガル・ストリートの市長」(注・本書の原題)という綽名をつけられた。マクドゥーガル・ストリートとはワシントン・スクエア・パークの南、デイヴが本拠としたライブ・カフェ「ガスライト」があった通りの名前だ。
やがて公民権運動からベトナム反戦運動が盛んになり、フォーク人気に火がついた。グリニッチ・ヴィレッジはその中心となり、PP&Mやボブ・ディラン、ジョニ・ミッチェルがここから世界的なスターとなっていった。デイヴはその波に乗らず(乗れず)、少し距離をおいたところで歌いつづけた。
「私にとってあの頃最高に素晴らしかったことのひとつは、ヴィレッジを離れずに生活できたことだ。家から歩いていける距離にある何軒かのクラブで、何週間ものあいだぶっ続けで働いているので、リヴィング・ルームが楽屋で、セットの合間に家に帰ることもできた。私は気に入った音楽を聴き、友人たちに気に入ってもらえる音楽を作り、脂が乗ったシンガーやソングライターやパフォーマーの集うコミュニティに属していると感じていた……ディランのような稼ぎ方はしていないが……何か欲しいものがあってカネがなければ、1枚レコードを作るか1回ギグをすればいい、というような状況だった」
デイヴの後輩で、一時はデイヴの部屋に居候していたこともあるボブ・ディランへの評価は、やはり気になるところだ。
「彼(ディラン)はポピュリストで、現実に起きていることに敏感だった。……おそらくそれについては誰よりも上手に表現できたろう。……ボビーの手本のウディ・ガスリーは数多くの政治的な歌を書いたが、そのほかにもありとあらゆるテーマの歌を書いていて、ボビーはそれに倣っていたのだ。……ボビーは歴史上もっとも優れたソングライターというわけではないが、あのシーンではずば抜けていたし、……みんなそれがわかっていた」
デイヴ・ヴァン・ロンクはボブ・ディランにはなれなかった。早すぎた男として時代の不運もあったろうし、もちろん才能の差もあったろう。でもグリニッチ・ヴィレッジというコミュニティに属して「最後までやり抜いた」男が自分と時代と場所の記憶を語る率直な言葉は胸を打つ。
蛇足。「マット・スカダー」シリーズのミステリー作家、ローレンス・ブロックが序文を書いている。ローレンスは大学生のときニューヨークでデイヴと知り合ってつきあいが始まり、「ジョージイ・アンド・ザ IRT」という歌に詞をつけている。これもYouTubeで聞くことができる。デイヴ・ヴァン・ロンクという名前はこの本を読むまで知らなかったけれど、僕が過去に好きになった音楽や小説とどこかでつながっていたんだ。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





