孤独な鳥がうたうとき【トマス・H・クック】
孤独な鳥がうたうとき
| 書籍名 | 孤独な鳥がうたうとき |
|---|---|
| 著者名 | トマス・H・クック |
| 出版社 | 文藝春秋(464p) |
| 発刊日 | 2004.11.10 |
| 希望小売価格 | 2300円+税 |
| 書評日等 | - |
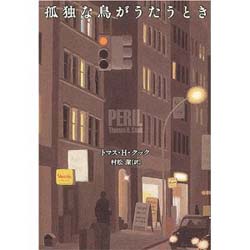
アメリカでネオ・ハードボイルドと呼ばれる一群の小説が生まれたのは1970年代から80年代にかけてのことだった。
それらの小説に特徴的なことのひとつは、探偵たちの多くが癒されることのない心の傷を抱えていて、それをタフな外面や気の利いた警句で仮装していても、時に仮装を突きやぶって傷口が露出してしまうことだった。「ハードボイルド」らしからぬ、うじうじと女々しい(←斎藤美奈子流に言えばフェミコードに引っかかるNG表現です)探偵が多かったように思う。
それ以前の探偵たち、名無しのオプやフィリップ・マーロウやリュウ・アーチャーは、依頼人や尋ね回る相手の心の傷に敏感ではあっても、そしてそのことが探偵自身なにがしかのトラウマを抱えているのかもしれないと想像はさせても、少なくとも文章上は彼ら自身そのような内省とは無縁の男たちだった。
70年代、80年代の探偵たちがそんな心の傷を抱えており、それが何らかのきっかけで吹きだしてしまうのは、ネオ・ハードボイルドがヴェトナム戦争という負け戦を経験した世代の「戦後小説」だから、というのが僕の怪しげな仮説。
確かマイクル・コリンズ描く探偵ダン・フォーチューンはヴェトナム帰りで、追いかけている男の怯えた目を見て「この目はヴェトナムで見た」とつぶやくシーンがあったはずだ。フォーチューンのほかにもヴェトナム帰りの探偵は何人もいたはずだけど、ずいぶん昔に読んだきりなので思い出せない。ヴェトナム帰りではないが、ヴェトナム反戦運動から生まれたヒッピー探偵モウゼズ・ワインなんてのもいた。
ネオ・ハードボイルドが流行らなくなるとともに、彼らの姿はミステリーや映画のなかで見えなくなってしまった。彼らはどこへ行ってしまったのか。……と思っていたら、思いがけずトマス・H・クックの「孤独な鳥がうたうとき」のなかでヴェトナム帰りの探偵とその相棒に再会した。
無免許の探偵スタークと探偵の仲介人モーティマーはヴェトナムの戦友。2人とも今では60歳近いだろう。モーティマーは肝臓ガンで余命3カ月を宣告されている。腹に焼けつくような痛みを感じて、彼はこんなふうに思う。
「いままで死に瀕したのは一度だけ、戦争中に四方から同時に攻撃を受けたときだった。地面が震え、銃弾が空気を引き裂き、燃え上がる小屋の熱気に包まれて、最後には銃弾がわき腹にくいこむのを感じた。……ふと、あのとき死んでいたほうがよかったかもしれないという考えが浮かんだ。焦らされることもなく、いきなり死んでしまうこと。なんの借りもなしに、若く愚かなうちに死ぬこと。……未来なんてものがいかに無意味かを思い知る以前に死んでしまうこと。それはいい死に方だろう、とモーティマーは思った」
一方、探偵のスタークは、ある出来事から心を石のようにしてしまった男。彼もまた死を身近なものと感じている。
「アフターシェイヴの匂いを嗅ぐと泣きたくなる日がある、というネルーダの詩の一節を思い出した。スタークにはこの詩人が言おうとしていることがよくわかった。ときには、あたりに物悲しい空気が漂っている日がある。なにもかもが黒いヴェールで覆われているように見えるのだ。……そういう日には、死がふだんより蠱惑的に見え、人生の見苦しい残骸を、この肉体というぶざまな屈辱を脱ぎ捨ててしまいたい衝動に駆られるのだ」
ひとりは「無意味な未来」といい、ひとりは「見苦しい残骸」という。ふたりとも、時間という誰にも避けられない残酷に打ちのめされ、死に怯えている。だからこの小説を20年後のネオ・ハードボイルドとして読むことも可能だ。
でも、である。モーティマーが借金のかたにギャングから人捜しを強要され、それをスタークに取り次ぐことで事件が始まるという、いかにもハードボイルド的な発端をもつこの小説は、スタイルの面ではもはやハードボイルドとはいえない。
ハードボイルドでは探偵が動き回り、人から人へと質問を発することによって事態が進展していくけれど、スタークは動き回ることをしないし、質問もしない。石のように動かず、目と耳を研ぎすまして佇んでいるだけだ。事件は勝手に向こうからやってくる。
またハードボイルドは一人称主観で叙述されることが多いけれど、この小説では9人の登場人物の目を通して代わる代わる三人称の客観描写で語られる。
例えば探偵スタークや相棒であるモーティマーの一人称のみでこの小説を語ってしまっては、なんというか時代の空気にそぐわないのだと思う。読者がリアリティーを感じられない。臭すぎるか、戯画すれすれになってしまう。時代が変わってしまったのだ。そうした意味で、今はもう古き良きハードボイルドは不可能なのかもしれない。
クックはこの小説について、ロバート・アルトマンの映画のように書きたかったと語っているらしい。ストーリーと匂いはハードボイルドなのに、視点が次々に入れ代わるアルトマンの群像劇スタイルが取られているのは、一人称主観が今では臭すぎたり戯画になってしまう危険を避けるために採用されたのだろう。
この群像劇で探偵スタークと、姿をくらました息子の結婚相手を探すマッチョなギャングは、主役とそれに対抗する悪役ではなく、いわば物語を動かす触媒にすぎない。ギャングのマッチョぶりは、こちらも戯画的なほどに型通りだし、探偵は登場人物のなかでいちばん影がうすい。この小説の主人公は、だからいかにもハードボイルドふうな2人ではなく、どこにでもいる男たち女たちだ。
ギャングの父親に反発して漁業会社を営む息子。その息子との結婚生活から逃げ出す元歌手。彼女の歌に惚れ込むジャズクラブのオーナー。ボスに命じられて彼女を追う気の弱いチンピラ。探偵の相棒モーティマーも人生に疲れ、せめて死んだ後に女房になしがしかの金を残したいと思う初老の男。
特にピアニストであることに挫折したジャズクラブのオーナーと傷ついた歌手の遠慮がちな恋は、人生の秋に向かってなだれてゆく季節のなかで小春日和のように暖かい。僕は映画「恋の行方」でピアニストと歌手を演じたジェフ・ブリッジスとミシェル・ファイファーの実らない恋を思いだしながら読んだ。
物語は、ギャングの面子と探偵のトラウマが彼らを複雑にからませて、すべての登場人物がはじめて顔をあわせるジャズクラブのクライマックスへと収斂してゆく。惨劇が起きるのか。あるいはハッピーエンドに終わるのか。
このあたりのドキドキさせ方は、「誰も知らない女」で重厚な警察小説を、「緋色の記憶」では心理的ミステリーをたっぷり楽しませてくれたクックらしい手練れの技。クライマックスも、映画好きなら、ははん、あれだなと、にやりとする。
章のタイトルには「孤独な鳥(バード・アローン)」などジャズの曲名が使われている。エピローグの曲名で結末がわかってしまうから、目次を見ないよう気をつけること。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





