風のなまえ【榎本好宏】
風のなまえ
| 書籍名 | 風のなまえ |
|---|---|
| 著者名 | 榎本好宏 |
| 出版社 | 白水社(236p) |
| 発刊日 | 2012.06.26 |
| 希望小売価格 | 2,310円 |
| 書評日 | 2012.10.03 |
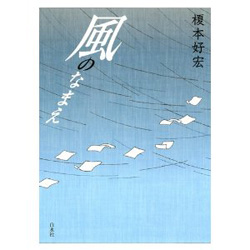
著者は昭和12年生まれ、団塊の世代より一世代上。略歴によると「杉」という俳句誌の責任者を永く務めた人で、句集に限らず幅広い著作が紹介されている。本書も俳句の季語をベースとしているものの、和歌・漢詩・民話・ギリシャ神話を始めとして、日々の生活や生業たる農業・漁業などの伝統に根付いたさまざまな「風」にまつわる話で本書はまとめられている。大きくは春夏秋冬に加えて無季節という章をつくり、五つの区分で「風」を語っている。読んでみると、意味と成り立ちを再認識したものや、初めて知った「風のなまえ」もあり面白く読むことが出来た。季節の生活習慣・行事・生業といったものに関連して名付けられているだけに日本各地の多様性も反映されて、その名前は様々につけられている。
我々は自然に依存した農業や漁業といった産業で生活を続けてきた民族だけに、こうした「風」に代表される自然現象や気候に対する繊細な感覚や生活への取り入れ方も他の文化圏よりも一段と深いものがあると思う。それにしても、未知の言葉は沢山あるものだと痛感させられた。まず、「貝寄風(かいよせかぜ)」。俳句では「貝寄風」と書いて、調子を整えるために「かいよせ」と読んでいるようだ。大阪の四天王寺で陽暦4月22日におこなわれる聖徳太子忌日のお祭りで難波住之江の浜に打ち寄せられる貝を飾ったことから、この時分に吹く、冬の名残の風を「貝寄風(かいよせ)」と呼んだ。また、子供の遊びの「通せん坊」にも通じる、「不通坊(とうせんぼう)」という春の風があるという。人の前に立ちはだかって行く手を遮るほどの春先に吹く強い北風をいうとの事。これも風の名かと驚く。こうした由来を知るに付け、なんとも豊かな気持ちになる。本書に示されている、古今東西の風にまつわる知識は教養的というか、良い意味での雑学とでも云ったら良いのか難しいところであるが、好奇心が満たされることは保証できる。
旧東海道の小田原宿を出て、箱根峠越えの手前に「風祭」という集落がある。評者が旧東海道を歩いた際も、のどかな風情を今も残している町並みと記憶している。珍しい地名とは思ったが、さして気に留めることもなく歩みを進めて行ったものだ。この「風祭」という地名の由来をこう記している。
「立春の日から数えて二百十日は農家にとって野分、今でいう台風がやってくる頃だから用心に用心を心掛けた。だから二百十日は『厄日』とも言ったし、この日に限らず二百十日の七日前から用心していたので『前七日(まえなのか)』という季語も生れた。・・・こうした二百十日を無事に送れたことを祝った」
これが、今でも五穀豊穣を守る風神を祀る奈良の龍田大社や長野の諏訪大社など、多くの神社で行われている風神のお祭り、風祭である。また、こうした神事と土着の祭りが交じり合っていったものとして、越中八尾の「風の盆」が有名だ。この祭りは風の神送りの風祭と祖霊供養の盆踊りが習合して生れた民衆芸能となったものだ。切々たるおわら節と目深に笠を被った無言の踊り手たちは二百十日が静穏に終わったこと祝う姿そのものである。近年、「風の盆」に多くの観光客が集まること自体はけして悪いこととは思わないが、妙にイベント的にならずこうした祭りが各地で続いていって欲しいものである。
「風炎(ふうえん)」という言葉が紹介されている。これは大正の末に第四代の中央気象台長となった岡田武松という気象学者が生み出したもの。春から夏にかけて太平洋高気圧から湿度の高い熱風が吹き込んできて本州の中央山系にぶつかり東日本には雨を降らせ、日本海側には湿度の低い熱風が吹き降ろすという気象現象。昔から各地で多くの山火事や大火、そして酷暑が記録されている、所謂「フェーン現象」である。この熱風を岡田は「風炎(ふうえん)」と名づけたのだ。現在では晩春の季語として確立している。よくも名付けたものだと思う。ダジャレ的、語呂合わせではあるものの、日本語の持つ柔軟性というか、それを季語として取り込んでしまう日本人のしなやかさはしたたかでさえあると思う。
「お風入れ」という言葉も洒落た言い回しだ。夏の土用に行われる「虫干し」の別称であり、歳時記には「虫払い」「土用干し」「曝書」といった言い方も書かれている。「お風入れ」という言葉の優雅さは格別である。多湿のわが国で「虫干し」は大切な行事であったわけだが、本書では「絵本江戸風俗往来」から、まさに「お風入れ」と言うべき光景を活写している文章が引用されている。
「新調の男女の衣類。子供物より大人物と、くすみしあり、また派手なるありて、座敷の隅すら縁側まで、縄張り渡して掛けし様は、谷川に紅葉のしからみしたる如く、昔の花見もかくやと知られ・・・・」
大切なとりどりの衣類を虫干しする様は、なんとも町の人たちの浮き浮きとした姿が思い浮かぶようだ。同じ「虫干し」でも東大寺正倉院では「曝涼」と言われ、秋に行われる行事である。東大寺正倉院では1880年代から限られた御物を特別な形で公開していたようであるが、本格的に「曝涼」に合わせて公開し始めたのは1946年(昭和21年)の正倉院展からとのことである。「虫干し」が御物の一般公開の後押しをしたとなるとなかなか良い風習であり、当時の文部省か東大寺に知恵者が居たに違いない。
著者が好きな季語として、初冬のころ吹く北東風をいう「星の入東風(いりごち)」を挙げている。
「ここでいう星は昴(すばる)のことで、昴が明け方に西天に没するころ吹く風」
と言っているのだが、はたしてどんな風なのか。「星の入東風」という言葉の持つ不思議な感覚は「星」と「風」を繋ぐ妖しさとでも言おうか。それは自ら昴の没する場に身を置いて「風」を体験するしかないようである。
この様に、風にまつわる季語の多様さは驚くばかりであるが、同時にもはや死語となってしまったものも多いに違いない。日常生活の中で季節毎に感じる風がいかに少なくなって来てしまったかと痛感する。特に都市生活者にとっては自然からの距離は離れるばかりだし、一方、最近の天候の乱暴さも驚く程である。急なドシャ降りや落雷、そして途轍もない暑さが続いたりと、温帯ではなく熱帯のような気候が今年も続いた。なにやら、自然の自浄作用の限界まで我々は地球を使ってしまっているのではないかと危惧する。本書に書かれている多くの風たちが、昔話になってしまわないように言葉として活用しつつ、ちょっとした風を体感する感性も大切にしたいものである。どのページからでも読める大人のエッセーだ。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





